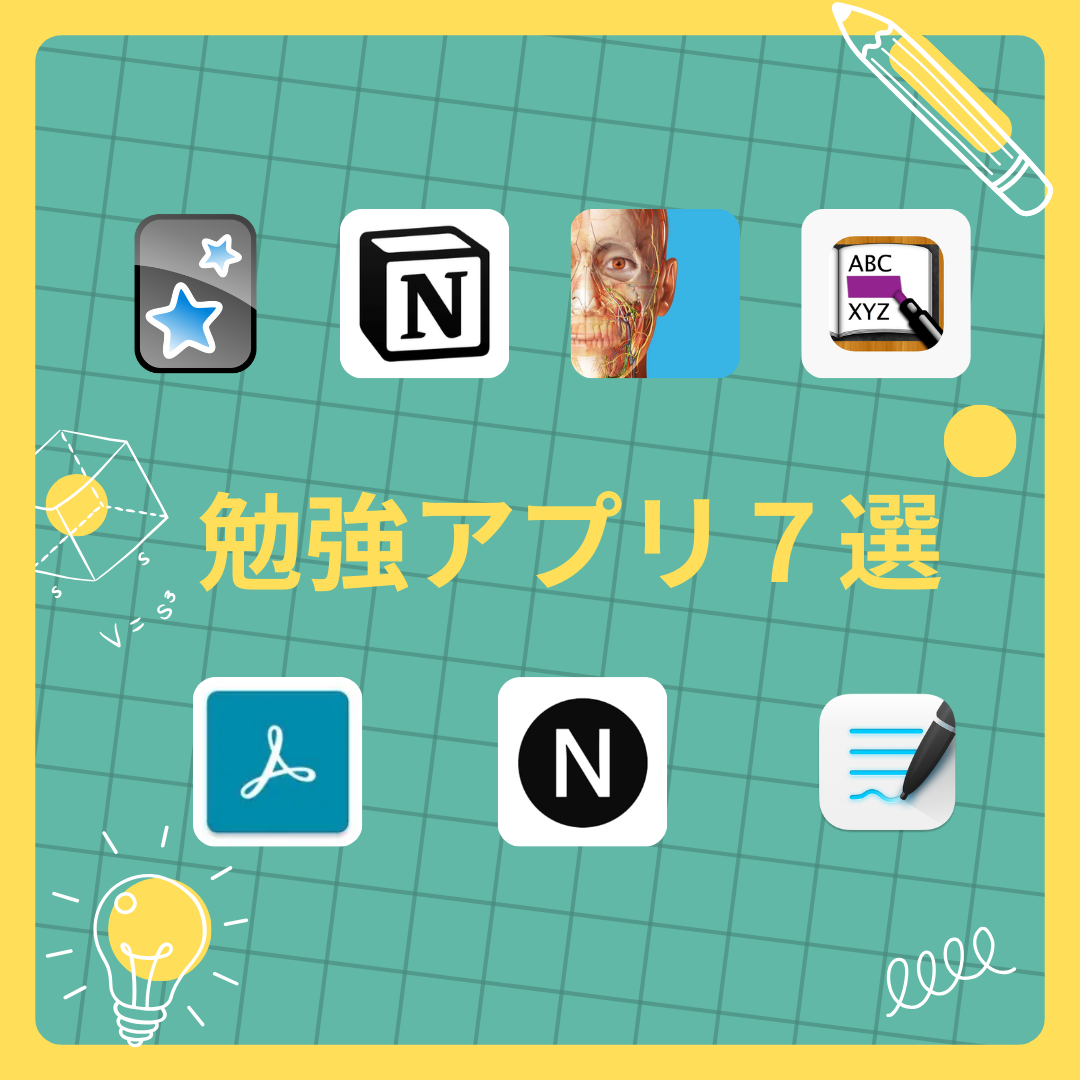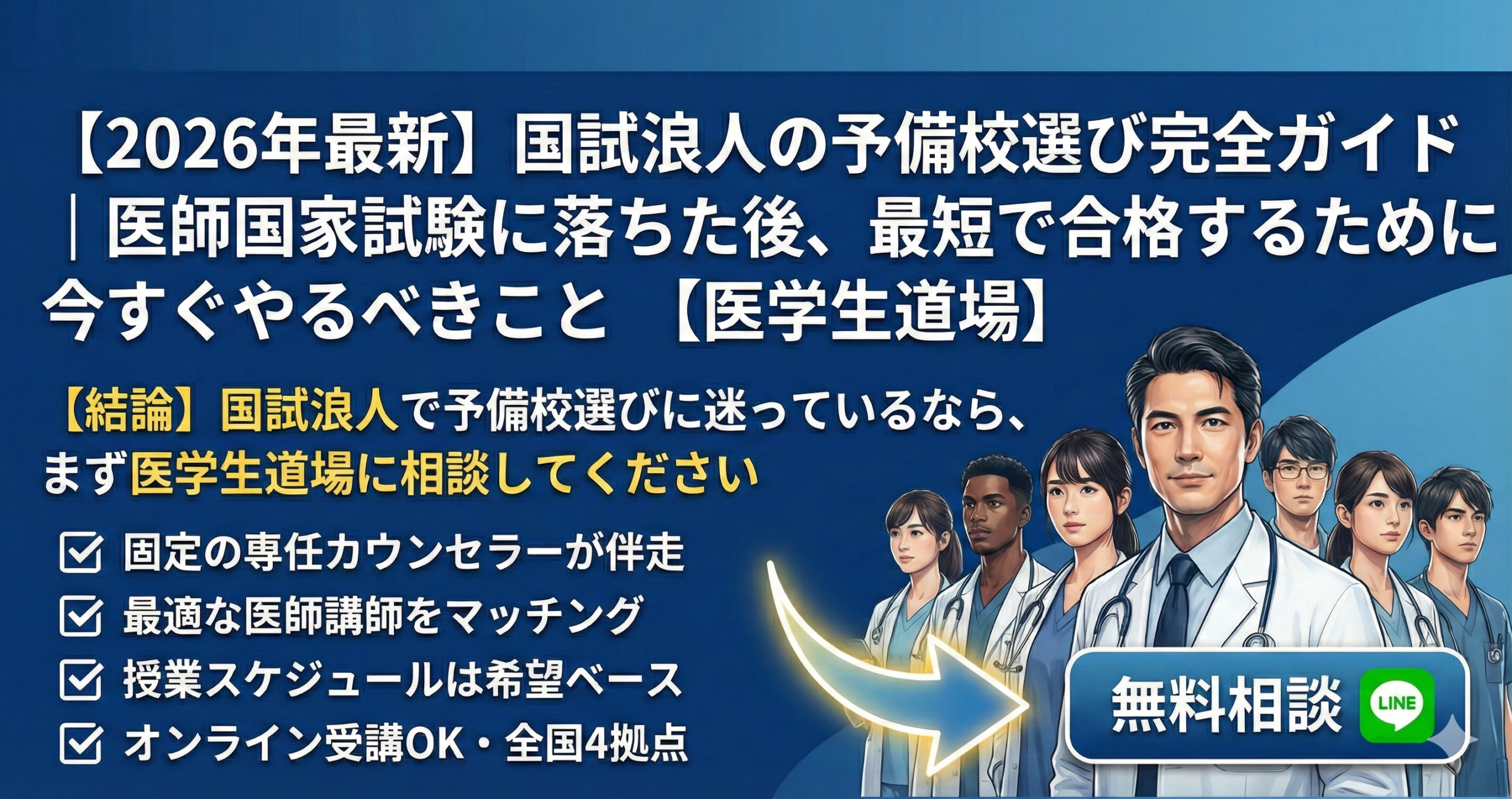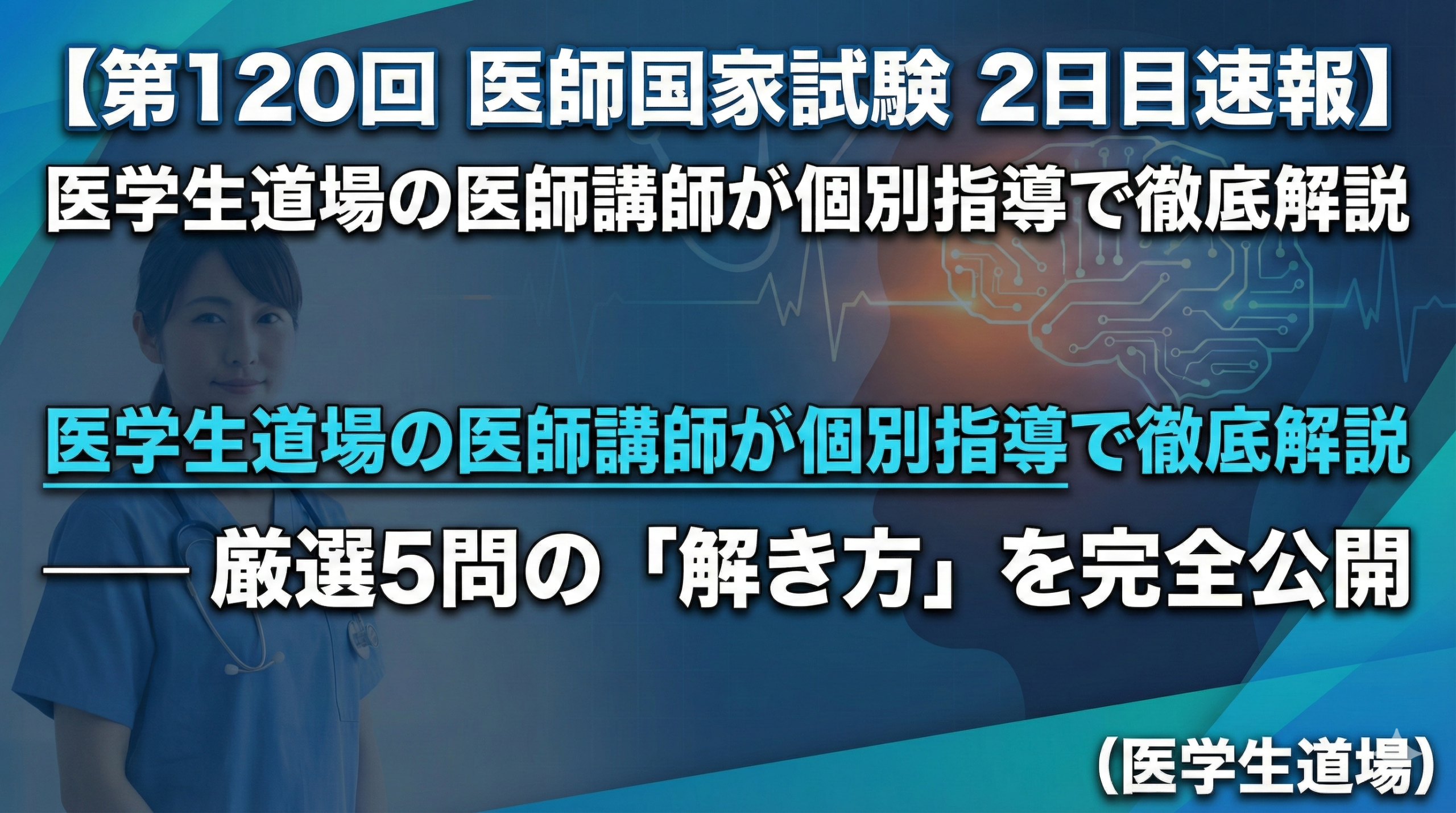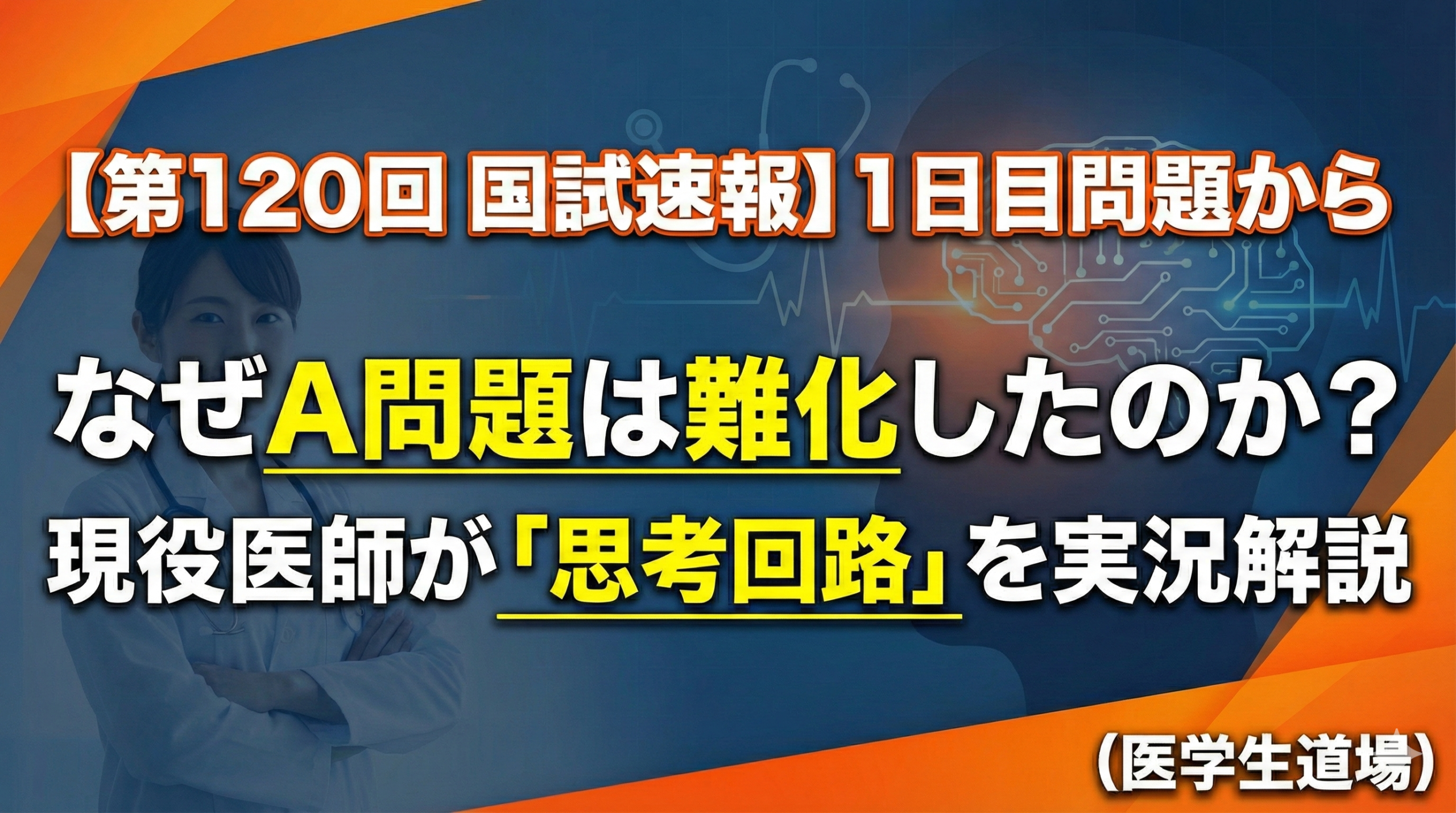筆者紹介
著者名:シマダ
所属:早慶三年生、医学生道場の学生アルバイト
資格・経歴:年間40本以上観劇、毎期多数ドラマ視聴
アピールポイント、自己紹介:年間様々な舞台を観劇したりドラマ、アニメ、映画などを視聴しており、皆さんの好みに合わせたおすすめ作品をご紹介することができます!
また、早慶に通う現役大学生として学習方法のアドバイスや大学生活の今をお届けします!
初めに

こんにちは、医学生道場です!
皆さんは、帝国劇場という劇場をご存じですか?東宝株式会社が運営し、度々有名なミュージカルが上演される帝国劇場ですが、その名前の荘厳さなどからも、帝国劇場に足を運ぶのは敷居が高いな、と感じている方も多いのではないでしょうか。
ですが、一般的な観劇ルールさえ守ることができれば、誰でも気軽に作品を観劇することができるとても素敵な劇場です。
今回はそんな帝国劇場で上演された作品の中から、皆さんにも馴染み深いであろう「千と千尋の神隠し」、退廃的な世界観がまさにミュージカル!な「エリザベート」の二作品をご紹介させて頂きます!
舞台「千と千尋の神隠し」
まずは、スタジオジブリの大人気映画「千と千尋の神隠し」を原作とした舞台「千と千尋の神隠し」をご紹介します。
原作となった「千と千尋の神隠し」の映画は一度はご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。映画「千と千尋の神隠し」は2001年に上映され、「風の谷のナウシカ」などで有名な宮崎駿監督が原作、脚本、監督を担当した長編アニメーション映画です。

興行収入は300億円を突破し、「タイタニック」を抜いて当時日本歴代興行収入トップになるなど、日本を代表する長編アニメーション映画であるといえるでしょう。
また、その後も定期的に金曜ロードショウなどで放送されるなど日本国民になじみ深く、身近な存在となっている映画です。
そんな国民的映画である「千と千尋の神隠し」の舞台化作品である舞台「千と千尋の神隠し」は、東宝の創立90周年を記念した作品として2022年に帝国劇場で初演を迎えました。
2023年には再演も行い、帝国劇場などの日本国内の劇場のみならずイギリス・ロンドンでも公演を行うなど、日本だけでなく海外の人々にも愛される作品となっています。

舞台「千と千尋の神隠し」の魅力の一つとして、個性豊かかつ実力派の演出、俳優の起用があげられます。舞台「千と千尋の神隠し」は、帝国劇場でも何度も上演されている不朽の名作である「レ・ミゼラブル」などの演出を手掛けたジョン・ケアードが演出を務めました。「千と千尋の神隠し」の舞台化の企画は2017年から進められており、高名な演出家によって約五年もかけて綿密に演出プランが練られた作品です。
また、初演では主演である千尋を橋本環奈さんと上白石萌音さんのダブルキャスト、ハクを醍醐虎汰郎さんと三浦宏規さんのダブルキャストが務めました。舞台「千と千尋の神隠し」は様々な賞を受賞していますが、その中でも上白石萌音さんは舞台「千と千尋の神隠し」と「ダディ・ロングス・レッグ」の演技で読売演劇大賞最優秀女優賞を受賞しています。また、三浦宏規さんは舞台「千と千尋の神隠し」と「赤と黒」「のだめカンターヴィレ」の演技で第49回菊田一夫演劇賞を受賞しているなど、実力の高い俳優たちによる一流のパフォーマンスを楽しむことができます。

舞台「千と千尋の神隠し」の最大の魅力は、ジブリの不思議で思わず惹かれてしまう魅力的なファンタジー世界を舞台上で表現するための演出でしょう。
「千と千尋の神隠し」の映画を見たことがある人なら、「千と千尋の神隠し」を実際に生身の人間が舞台で表現するとき、あのシーンやこのシーンはどうやって再現するんだろう、と不思議に思う点も多いのではないでしょうか。
宮崎駿作品特有のエキゾチックな色彩や、異形の者たちが織り成す奇妙でありながらどこか懐かしさを感じる世界観を、舞台「千と千尋の神隠し」は「舞台」という形式で最大限表現している点が見どころです。
アニメーション特有の表現を舞台上に再現するために、ジョン・ケアードはあえて「すべてをアナログで表現すること」にこだわりました。
「千と千尋の神隠し」には、千尋の両親が変身した豚や釜爺やススワタリ、カオナシなど、アニメーションだからこそ表現することができる動きをする異形の登場人物がたくさん登場します。それらのキャラクターの存在や動きを舞台上でリアルに表現しようとすると、一番の近道はプロジェクションマッピングを使うことでしょう。プロジェクションマッピングで映像を投影すれば、現実では不可能な動きも舞台上で表現することが可能です。
しかし、ジョン・ケアードはプロジェクションマッピングを用いず、あえて全てを生身の俳優や小道具で表現することにこだわりぬいた演出を行いました。

そのために用いられた手法が、黒子によるパペットの使用です。パペットとはいわゆる操り人形のようなものであり、舞台上では着ぐるみなども含めて黒子と呼ばれる役名の無い裏方の俳優が動きを操るものをパペットと呼びます。
とりわけ舞台表現として面白いのはカオナシの表現でしょう。カオナシは「千と千尋の神隠し」でも重要な役割を果たす存在感のあるキャラクターですが、舞台「千と千尋の神隠し」では、二人のダンサーがダブルキャストとしてカオナシを演じました。
カオナシはお面と黒い布を全身にまとっており、表情やセリフによる感情表現が非常に難しいキャラクターですが、二人のダンサーはそのたたずまいやダンス、体の動かし方によってカオナシの存在や感情を表現しました。
舞台の終盤、千尋を追い詰めていくカオナシは徐々に肥大化し、千尋を飲み込もうと大きくなっていきます。そのように肥大化したカオナシは、ダンサーを含む12人の俳優たちによる動きやダンスで表現されました。カオナシのお面を付け、大きな黒い布を自在に操りながらカオナシの怒りや寂しさを巧みに表現する様子は、アナログにこだわったからこその舞台演劇ならではの醍醐味であるといえます。

表情やセリフはないのに体や布の動きでキャラクターの感情がダイレクトに伝わってくるという観劇体験は、舞台「千と千尋の神隠し」でしか味わうことのできない大きな魅力です。
公演ダイジェストはこちら☞https://www.youtube.com/watch?v=uxZs1aT52Kk
「エリザベート」
次にご紹介するのは、1992年にウィーンの劇場で初演の幕が開いてから世界各地で上演され、日本でも上演されているミュージカル「エリザベート」です。この作品はもともとドイツ語が用いられたドイツ語ミュージカルであり、様々あるドイツ語ミュージカルの中でも史上最高のヒット作品となります。日本でも度々上演されており、宝塚歌劇団による1996年の初演以来上演が続けられ、2000年からは東宝版も帝国劇場などで上演されており、20年、30年と愛される作品です。
この作品は、まさに皆さんが想像するような「豪華絢爛」「中世の退廃的な世界観」「ロマンス」のようなオペラ、ミュージカルの要素がたっぷりと詰まった作品です。

作品を知らない方に向けて、簡単にあらすじと概要をご紹介します。「エリザベート」は、長きにわたってヨーロッパに君臨し一世を風靡したハプスブルク帝国の末期19世紀後半のオーストリアが舞台となっています。タイトルの通り、主人公であるオーストリア皇后エリザベートの謎に包まれた半生を描く作品となっています。
オーストリア皇后エリザベートは、その美貌を見初められ16歳でヨーロッパでも随一の美しさを誇るオーストリア皇后となりますが、そんな彼女の人生はとても幸せなものとはいいがたいものでした。オーストリア宮廷を取り巻く窮屈な伝統やその中の確執、軋轢に悩み運命に翻弄されたエリザベートはウィーンを離れてヨーロッパを放浪する日々を送りますが、旅の果てに暗殺され、その一生に幕を閉じます。そんな悲劇の皇后であるエリザベートの半生を歴史的事実に基づきながらも、「死」という架空の存在もともに描くことで幻想的な世界観とともに、中世・近世ヨーロッパの終焉と近代の訪れを描き出した作品です。
歴史的な要素を取り扱っているため、そのような歴史的作品として楽しむことももちろん、歴史的な背景を知らずとも「死」という架空の存在に翻弄されるエリザベートという幻想的な世界観を楽しむこともでき、様々な視点から観劇することができる魅力的な作品です。
特に注目すべき点は、先ほどから何度か登場している「死」という存在です。幼いころに木から落ちて生死をさまよったエリザベートはそれ以降、「死」をつかさどる黄泉の帝王・トートに愛され付きまとわれることとなります。エリザベートは、生きたエリザベートを愛したいというトートの願いによって生死の境から生還したエリザベートでしたが、そのような運命のいたずらからか望みもしないオーストリア皇后として見初められ、宮廷で窮屈な生活を強いられることとなります。エリザベートに愛をささやき死へと誘惑する黄泉の帝王・トートとその誘惑に抗いながらも徐々に破滅へと向かっていくエリザベートという、死者と生者の奇妙なロマンスや、エリザベートの葛藤と苦悩が「エリザベート」の大きな魅力でしょう。

また、「エリザベート」の魅力の一つに、現代社会に生きる女性も共感することができる「自立した女性の生きざま」が描かれている点があげられます。
エリザベートの人生は波乱万丈で悲劇的ですらありますが、そんな中でも自分にできることを探し、「死」からの魅力的な誘惑も懸命に跳ねのけて一生懸命に生きるエリザベートの姿は、現代を生きる女性にとってもとても共感でき、励まされる存在となってくれるでしょう。
エリザベートの歌の中に、「私が踊るとき」という楽曲があります。「私が踊るとき」でエリザベートは死へと誘惑するトートへ向かって、「一人でも私は踊るわ 踊りたいままに好きな音楽で」「踊るときは すべてこの私が選ぶ」と歌い、手を差し伸べるトートの手を取らずにきっぱりと決別を告げます。
自分の人生は自分での手で決める、と堂々と歌い上げる気丈で自立したエリザベートの姿に共感し感銘を受ける人も多いでしょう。歴史ものやファンタジーものでありながら、時を超えてエリザベートという一人の女性に自身を重ね合わせ、自分の人生について考えるきっかけとなる作品であるといえます。

そのようなメッセージ性だけでなく、中世ヨーロッパを舞台とした豪華絢爛な舞台装置やきらきらとしたドレス、先ほどご紹介した「私が踊るとき」をはじめとしたキャッチーで心に響く名曲の数々等、「エリザベート」にはほかにも魅力がたくさんあります。
是非一度、耽美な「エリザベート」の世界を劇場でお楽しみください!
「エリザベート」の公演ダイジェストはこちら☞https://www.youtube.com/watch?v=7KZxVqBX6YI
最後に
ここまで、「千と千尋の神隠し」「エリザベート」の二作品をご紹介させて頂きました。全く方向性の違う二作品でしたが、それぞれに異なった魅力がありいろんな世代、性別の方に楽しんでいただける作品です。
帝国劇場は老朽化による建て替えの為、2025年2月に休館することが決まっており、ラスト公演として「レ・ミゼラブル」が12月から上演されます。「レ・ミゼラブル」も先ほどまでに紹介した二作品同様にとても魅力的な作品なので、ぜひ歴史ある帝国劇場の建て替え前最後の公演に気軽に足を運んでみてください!
帝国劇場に足を運ぶついでに、少し背伸びしたおしゃれをしておいしいランチを食べて丸の内や日比谷を歩くのは、非日常的で特別な思い出になること間違いなしです!
このブログを執筆したスタッフが所属している医学生道場では、医学部に在学する医学生を対象とした個別指導を行っています。身近に医学部の学習や試験についてつまづいていたり、誰かに相談したいと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
そのような方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に医学生道場にご相談ください!