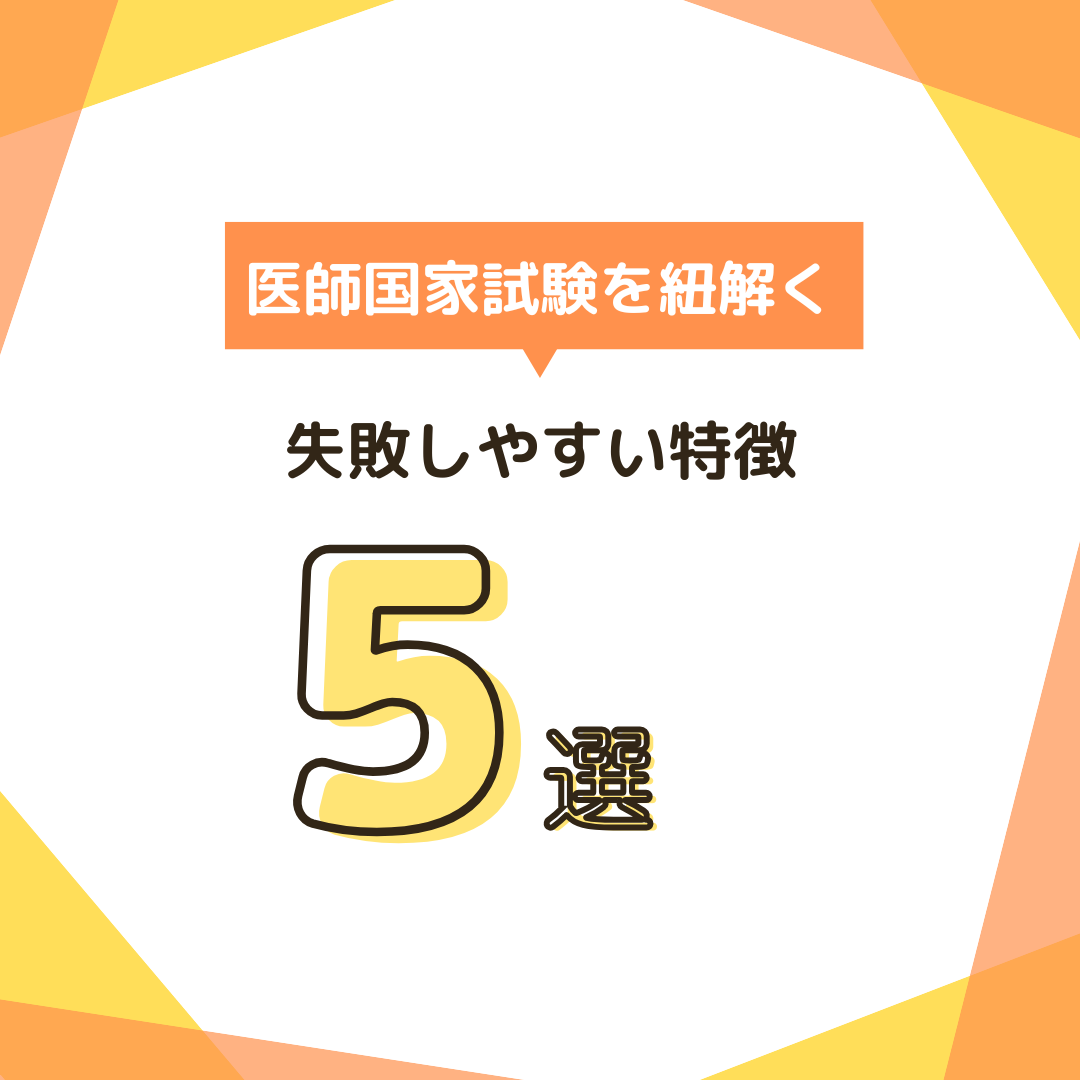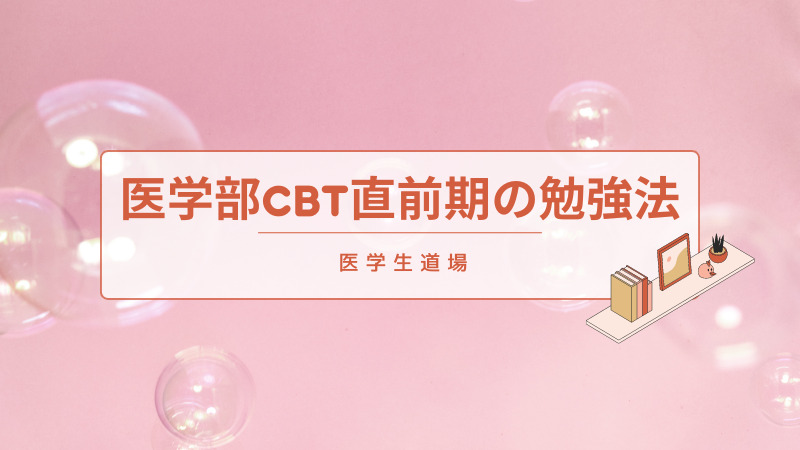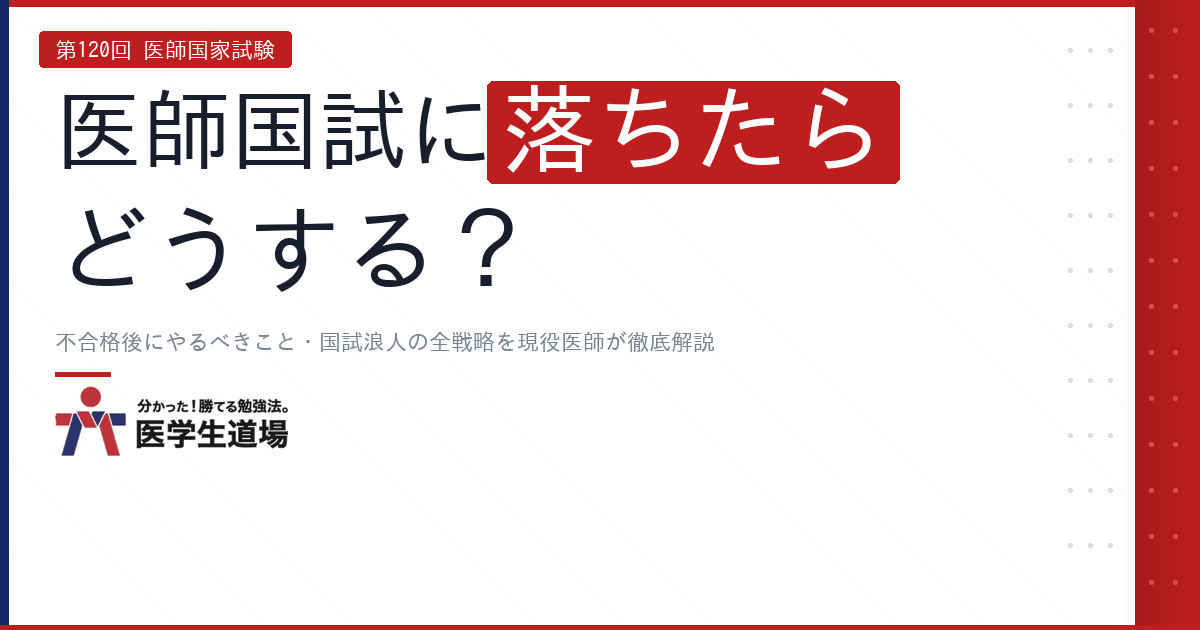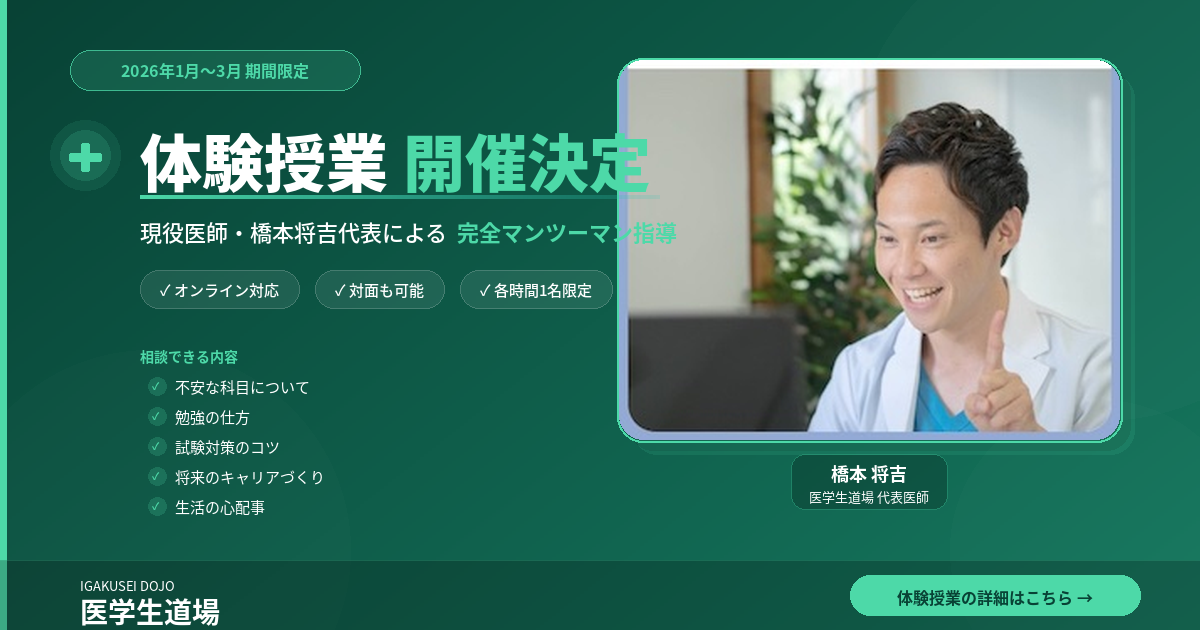【著者紹介】
田邊まき 医学部在学
~過去ブログ~
・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策
・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!
・【医学生道場】【医学部4年】いよいよ臨床実習!この時期何する?
医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪
目次
はじめに
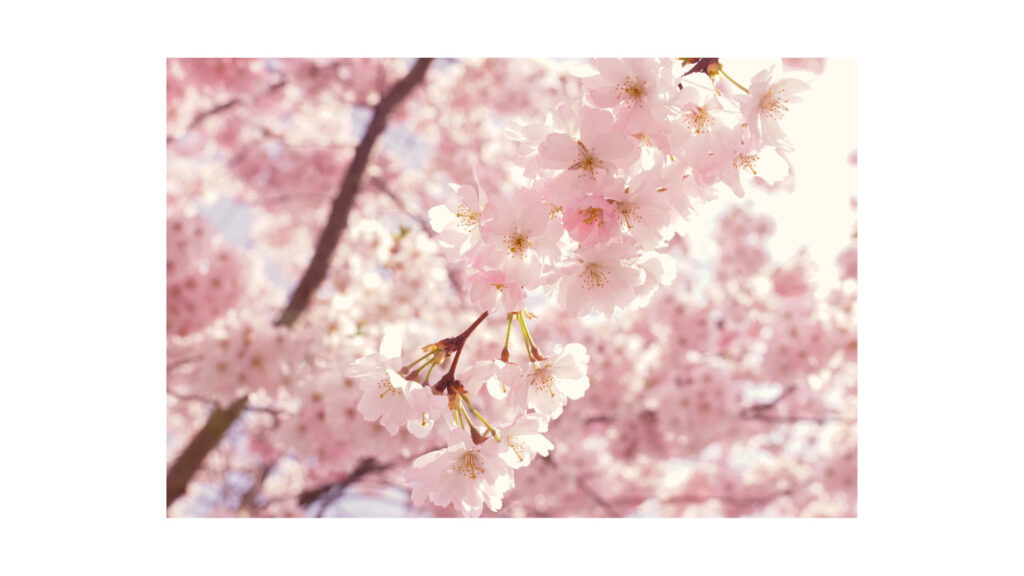
こんにちは!医学生道場です。いよいよ新年度が始まりますね。気持ち新たに新年度を迎えたいところですが、、、すでに定期試験の心配が出てきている方もいるのではないでしょうか?勉強を今年こそは頑張ろうと思っても、自分のやり方が果たしてあっているのか、失敗しはしないかと不安に思う気持ちは、痛いほどわかります。
そこで今回は臨床医学が苦手な筆者が、定期試験やCBTを乗り越えた勉強法をお伝えしたいと思います!勉強法に自信が無い方は、たくさん調べ、多くある勉強法の中から自分に合ったものを選ぶのがいいのではないかと思っています。邪道な勉強法ももしかするとあるかもしれませんが、1例として皆さんの参考になれば幸いです!
悩んだ末たどり着いた勉強法
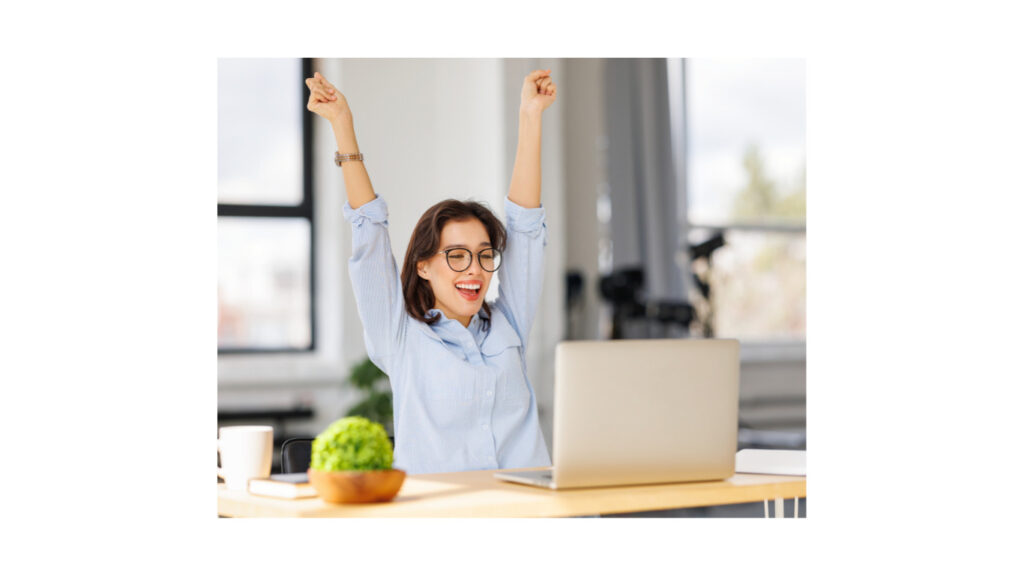
まず単刀直入に結論からお伝えします。たどり着いた勉強法は以下の通りです。
・第一に暗記。機序の理解は暗記の後。
・過去問を周回して傾向を掴む。
・教材を絞る。
詳しい説明は『勉強法』の項目でお話しします!まずはどのようにしてこの勉強法にたどり着いたのかお話しします。
当初の悩み
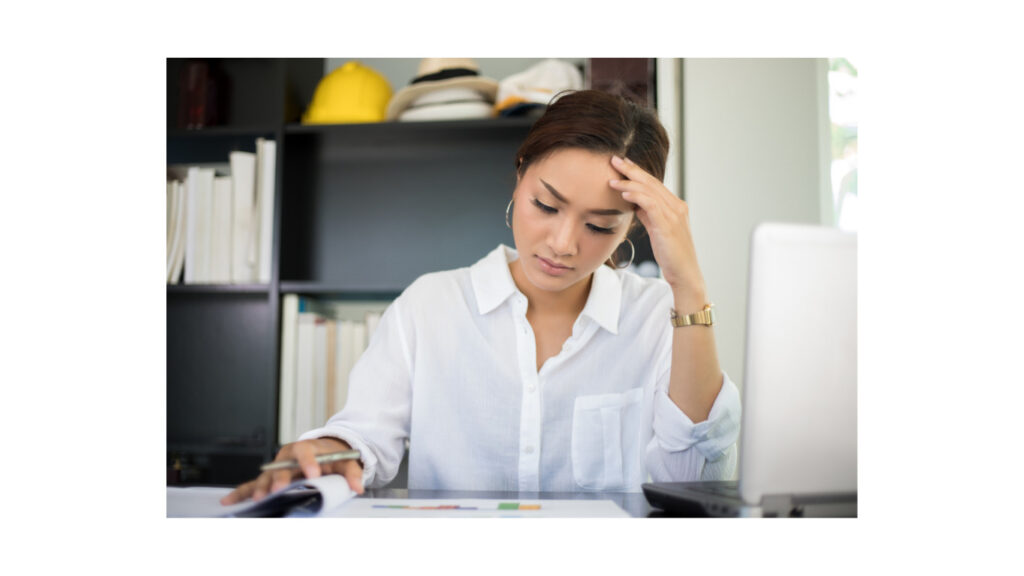
<医学部志望理由>
私が医学部を志望した理由は多くの人が理由とするであろう「医師として誰かを助けたい」ということではなく、「人体について学びたい」と思ったからです。高校生の時に学んだ生物で、細胞がヒトの体の中で様々な働きをしていることに感動し、ヒトの解剖や生理をもっと知りたいと思うようになりました。人体について学ぶには他の学部では学ぶことができず、医学部でしか学べなかったため、医学部に入学したいと考えていました。もちろん医師となるのであれば医学を用いて貢献したいとは思ってはいましたが、特別強い思いがあるわけではありませんでした。
このように、医師の仕事というより基礎医学に限局して興味を持っていた私は入学後どうなるかおわかりでしょうか、、、?
そうです。2,3年生から始まる臨床医学でつまずくのです。
<医学部1,2年生>
医学部1,2年生では皆さんご存じの通り基礎医学を学びます。基礎医学は私が最も学びたいことの一つであったので、ご褒美も同然でした。憧れの医学部に入学でき、ずっと学びたかった学問を学ぶことができていたため、毎日楽しく授業を聞いていました。勉強にかなり時間を割いていたこともあり、定期試験では9割を切ることはほとんどありませんでした。
その時の勉強方法は以下の通りです。
・授業をしっかり聞きく
・授業終了直後、その授業の要点を箇条書きにして頭を整理する
・試験前は機序の理解を中心に、レジュメをもれなく理解する
・機序や覚えるべき項目は空で言えるようにする
・過去問を使って重要なところを掴む
基礎医学ではこの勉強法がしっかりとはまり、うまくいっていました。しかし臨床医学に入るとこの勉強法が一気に通用しなくなったのです。泣
<医学部2,3,4年生>
大学によっても異なるとは思いますが、2,3年生あたりで臨床医学が始まります。
1,2年生は難なく乗り越えることができたため気が緩み、部活やバイトに打ち込む日々に。。。自然と勉強時間をも少なくなっていました。勉強時間が減った割には勉強方法は1,2年生と同様にやっていました。間に合うと思って立てた計画が全く間に合わず、ついには再試にかかるようになってしまったのです。
では何が問題だったのか?今までとの1番の違いは、
臨床医学になり、覚える量が膨大になったこと
です。
基礎医学に比べ覚える量が増えたにも関わらず、まずじっくりと時間をかけて理解をするという勉強をしていました。理解することに時間をかけすぎて、過去問演習に時間を取れていなかったことが問題でした。私が思う問題点を以下にまとめます。
・過去問演習を疎かにした
・理解に時間をかけすぎた
・症状や検査、治療法など覚える量が膨大になり、どこから手を付けて良いかわからなくなった
・授業スライドが多すぎて知識がまとまらなかった
勉強法
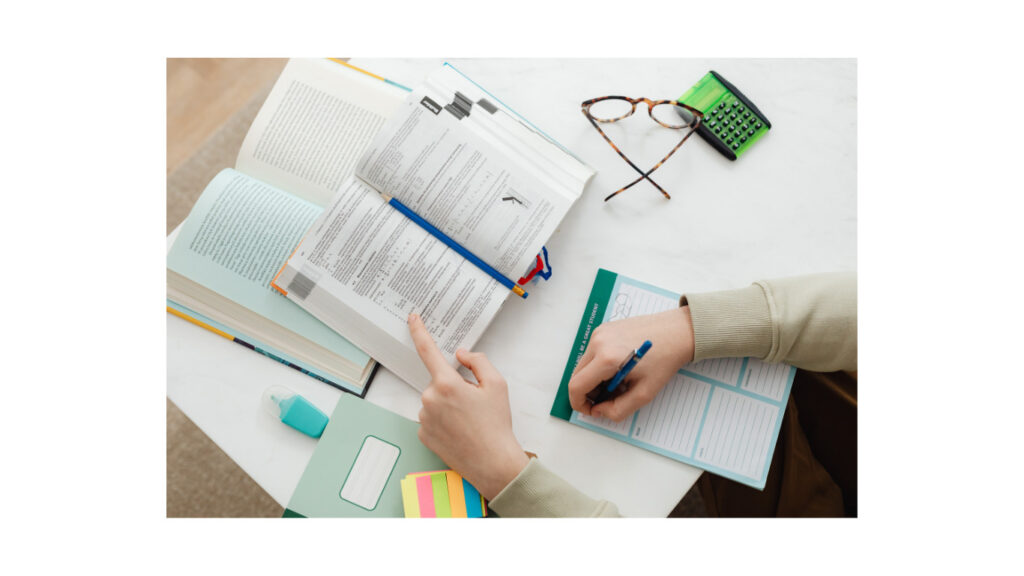
ではどのような勉強法をすればよかったのでしょうか?
先述した内容は、
・第一に暗記。機序の理解は暗記の後。
・過去問を周回して傾向を掴む。
・教材を絞る。
でしたね。私だけの意見では心配だったので、直近の医師国家試験である第119回の国試を合格した6年生にも話を聞いてまとめました!具体的にご説明します。
~ 第一に暗記。機序の理解は暗記の後。 ~
これはいわゆる大学の先生たちが言う、きれいな勉強法からはずれているかもしれません。しかし!理解なんて二の次です!
膨大な暗記量なのに、逆に理解せず暗記なんて無理では、、?そう思われるかもしれません。確かに何も要領を得ないでひたすら暗記するのは非効率ですしほぼ不可能です。そこで大事なのは、
「それぞれの疾患の要点をまず暗記する」
ということです。
<原因>
暗記量が膨大になり覚えられなくなる原因の一つとして、一度に詳細なところまで覚えようとしていることが挙げられます。1つの疾患に対してすべての症状を覚えようとしてもなかなか覚えられません。またなぜこのような症状が出るか詳細な機序を理解してから覚えようとしても、逆に覚える量が増え時間もかかるし知識がこんがらがってしまう可能性があります。それに加え症例問題では疾患から症状を考えるのではなく、症状から疾患を考えなければなりません。つまり症状からいくつかの疾患を素早く想起する必要があり、1つの疾患をじっくり理解することよりも、どれだけ多くの疾患をポイントを押さえて覚えられているかが求められるのです。
そこで、「それぞれの疾患の要点をまず暗記する」 ということが大切です。国試やCBTではそれぞれの疾患で問われる特徴的な症状や検査、治療法がだいたい決まっています。定期試験では大学によって少し異なるかもしれませんが問われる重要なポイントはそこまで大きく変わらないでしょう。その要点をまず暗記して疾患の全体像を掴んだ上で、なぜそうなるのか理解をすればいいと思います。
<方法>
①疾患の要点を把握:授業や過去問演習を通して出やすいポイントを把握しましょう。授業なんて全部寝てて聞いてないよ、、、って人はQ Assisitなどの予備校の国試・CBT対策教材がおすすめです!すごく端的にポイントがまとまっています。
②まず暗記
③暗記をしたうえで機序等を理解
④1つの症状から鑑別疾患を挙げられるようにする:1つの症状の鑑別疾患は実は山ほど出てきます、、、これを1からすべて覚えようとするのは困難です。優先順位を決めて覚えるのがとても大事です!!覚える優先順位は、「見逃してはいけない重症疾患→頻度の高い疾患→頻度の低い疾患」です。
~ 過去問を周回して傾向を掴む。 ~
やはり医学部の勉強はひたすら問題演習をすることがとても大事です。理由としてはも述べたようにどの試験でもよく聞かれる重要なポイントというのはあまり変わらないからです。過去問を繰り返し解くことで要点を掴むことができることに加え、暗記した知識をアウトプットできるのです。
<原因>
CBTや国試の失敗原因としてよく耳にするのが、過去問の演習不足です。講義動画は見ていたけど時間が無くて過去問を繰り返し解けなかった、、、という話はよく聞きます。逆に過去問演習ばかりしすぎていてもあまり身につきません。したがってCBTや国試突破には、講義動画をみる「インプット」と過去問演習をする「アウトプット」の両方が欠かせないのです。これは定期試験においても同様です。
<方法>
①講義動画でインプットする:大学の授業を聞くのでも、Q Assist等の映像教材を使うのでもご自身のやりやすい方法でやるといいと思います。
②過去問3~5年分を繰り返し解く:大学によって過去問が何年分あるかは異なるかもしれませんが、3~5年分解けば間違いないでしょう。これを1回解くだけでは身につかないので、繰り返し解くようにしましょう。※ただ単に選択肢を暗記するのではなく、どのようにして答えにたどり着くか、なぜこの選択肢は不正解なのか丁寧に解く必要があります!
~ 教材を絞る。 ~
3つ目の勉強法は教材を絞ることです。教材を絞るというのは、友達や先輩に聞いて良いと言われた教材を何個も使わずに1つに絞るということです。
<原因>
これもCBTや国試の失敗としてよくありますが、不安になってさまざまな教材に手を出してしまうということです。すると知識が様々なところに散らばり、いざ問題を解いた後振り返るために教材を見ようにも、どこに書いてあるか思い出せず余計に混乱してしまうのです。また結局どれも最後までできないまま試験を迎えてしまう可能性が高いです。
<方法>
①最初は様々な教材を見てみる
②どれか一つに決め、それを信じる!:医学生御用達の有名な予備校の教材であったり、先輩や多くの同級生が使っている教材であれば基本的にどれを選んでも間違いはないはずです。大切なのは、それを信じて極めることです!
自分に合った勉強法をみつけるには?

では自分に合った勉強法を見つけるにはどのようにすればよいのでしょうか。それは、
・勉強法の情報収集をする
・余裕を持って勉強を始め、調べた勉強法を試してみる
・勉強を進める中で自分に合った方法を見つける
です。
やはり勉強法は人それぞれですので、必ずしも先輩や友達のやり方が自分に合うとは限りません。今回私がご紹介した勉強法も一例にすぎません。そのため情報収集を十分にしたうえで、試行錯誤して自分に合う勉強法を見つける必要があります。ただ試行錯誤をするにはかなり時間が掛かります、、、「勉強を始めたはいいけどやっぱり合わなかったみたいだから他を試してみよう」となったらまたプラスで時間が掛かります。そのためなるべく余裕を持って始めることをおすすめします!
さいごに

いかがでしたでしょうか。今回は医学部の試験を乗り越える勉強法についてお伝えしました。あくまで一例ですのでぜひたくさん勉強法を調べてみてください♪きっと皆さんに合った勉強法を見つけられるはずです。
試験を乗り越えて楽しい医学部ライフを過ごしてくださいね~!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
医学生道場は医学部の勉強でお悩みの方のお力になるべく、試験対策・留年対策など各種対策にはとても力を入れています。
これまで多くの医学生の方にご利用いただいているため実績も豊富です!
安心してご利用いただける環境が整っておりますので、少しでも「医学生道場が気になる!詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、公式LINEもしくはお問合せフォームからご相談ください。
相談料は一切かかりませんから、気になることやお悩みなどお気軽にご相談・お問合せください。
また、LINEでお得な情報も配信しておりますので、お友達追加もよろしくお願いします♪