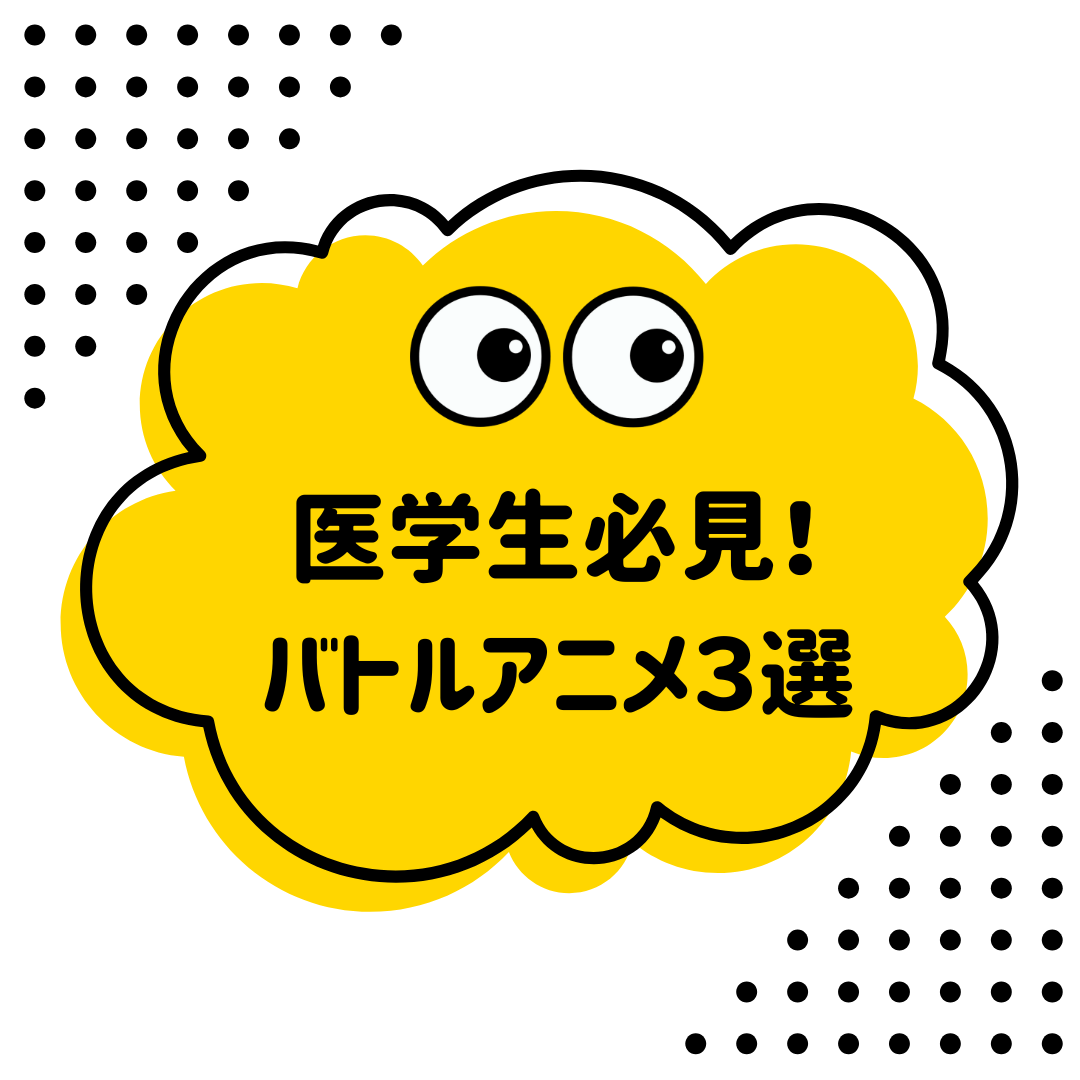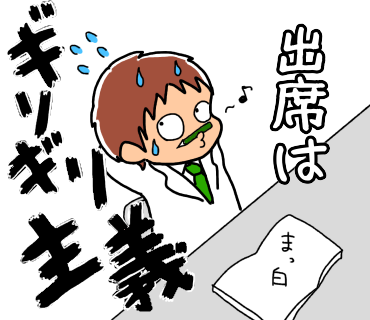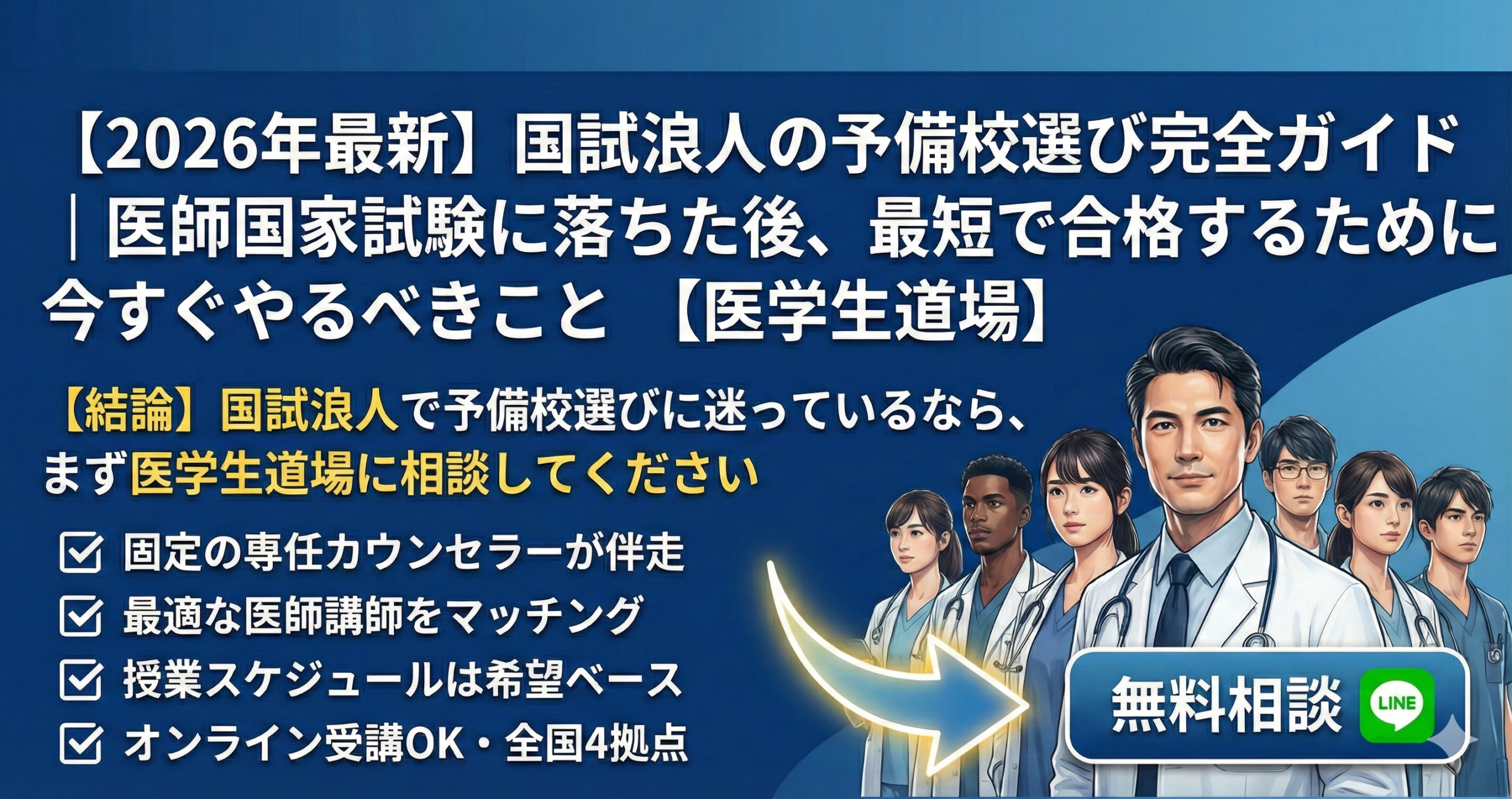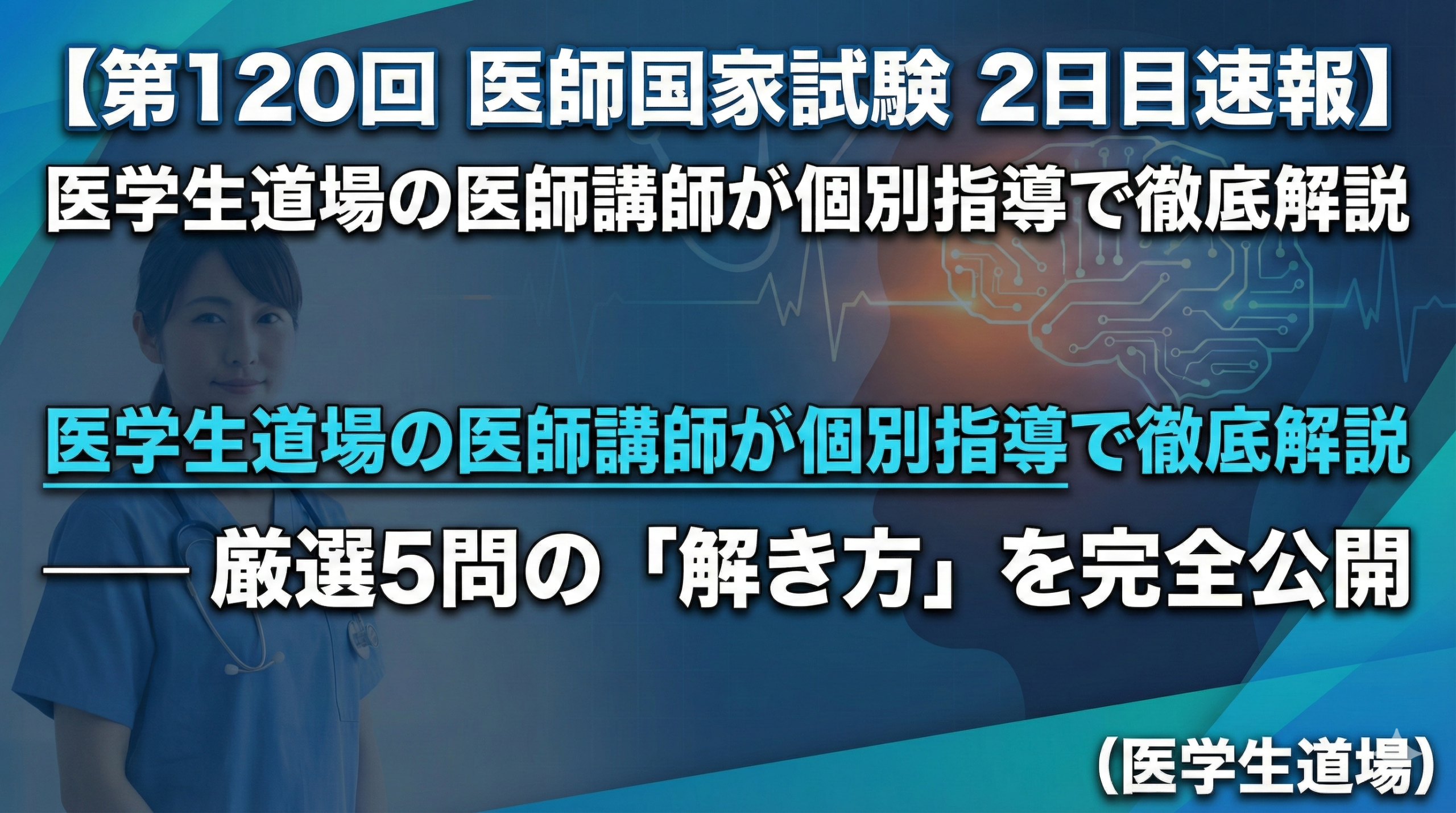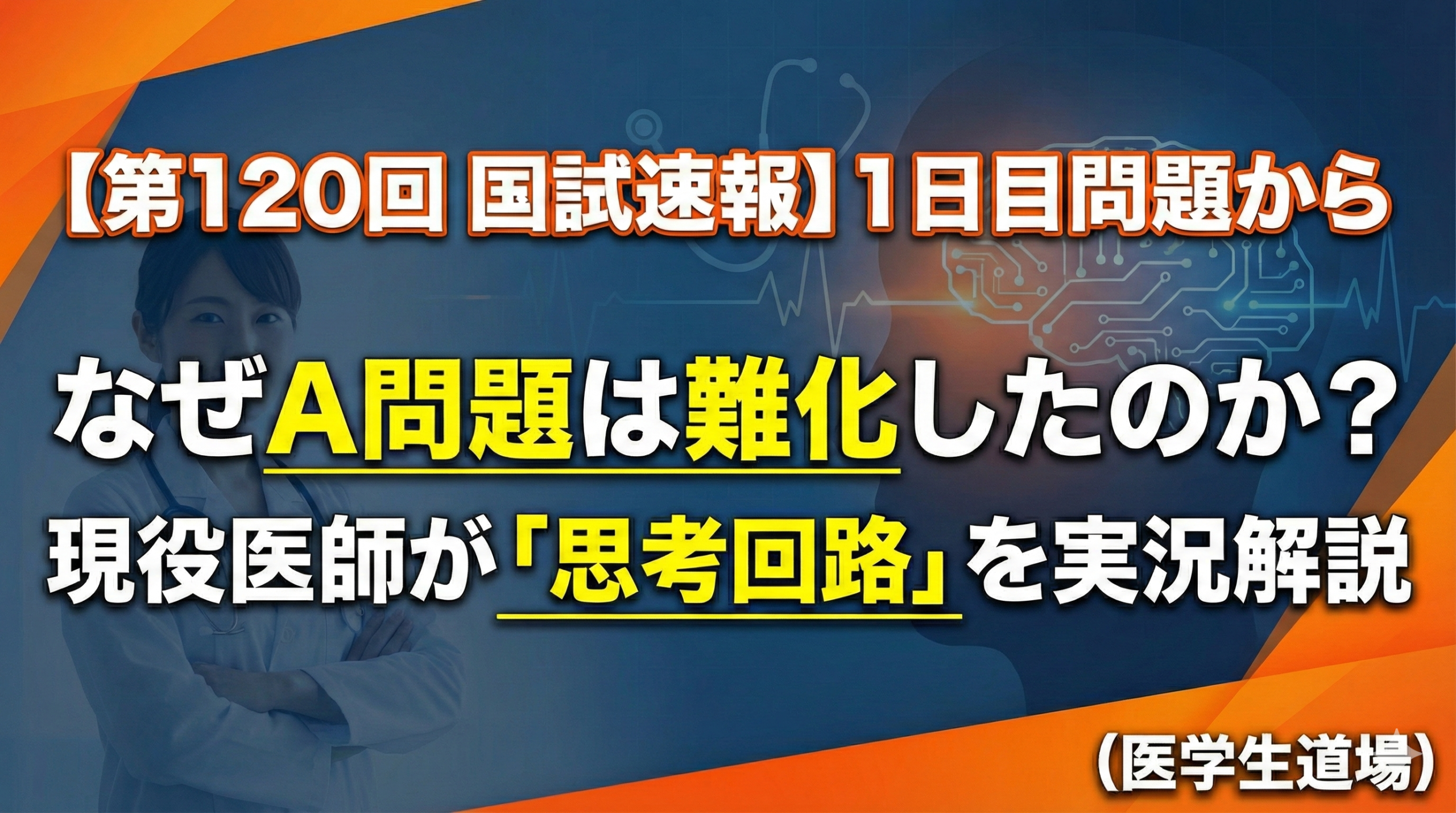【著者紹介】
田邊まき 医学部在学
~過去ブログ~
・【医学生道場】【医学部4年必見】意外と知らない!Pre-CC OSCE医療面接対策
・【医学生道場】【2024年CBT最新】もう噂に惑わされない!CBT受験直後の4年生が「実際」をお伝えします!
・【医学生道場】【医学部4年】いよいよ臨床実習!この時期何する?
医学部の試験や実習の情報を実体験を交えてご紹介します!皆さんと医学生あるあるの悩みを共有しながら一緒に解決できたらいいなと思っています。親近感のあるブログになっているかと思いますのでお気軽にご覧下さい♪
目次
はじめに
こんにちは、医学生道場です。新年度が始まってから約一か月が経ちましたが、みなさんの医学生生活は順調でしょうか。医学部cbtを受ける4年生の皆さんは前期の試験対策に、医学部cbt対策と忙しくなってくる頃かと思います。そこで今回はcbtで差が付きやすい「4連問」についてお話します!4連問は対策を後回しにしがちなので私もかなり手を焼きました、、、。どのように勉強して乗り越えたか、そして振り返ってみてどのようにすればより良かったのかをお伝えします♪ポイントを押さえて効率よく勉強していきましょう!
医学部cbtについて

4連問について詳しくお話する前に、、、4年生の皆さんはcbt対策を進めていますか?もしも始めていなかったらいますぐ始めてください!今始めればまだ全然間に合います。cbtの勉強スケジュールや使うべき教材等の勉強方法は以下の記事をご覧ください♪
医学部cbtの4連問とは

医学部cbtは6ブロックに分かれており、合計320問あります。ブロック1~4は単純に5つある選択肢の中から1つ選ぶ形式で、ブロック5は6つ以上ある選択肢の中から1つ選ぶ形式、そしてブロック6が1つの症例問題に対して4問連続で答え一度解答したら前には戻れないという形式です。
医学部cbtを受験したときの小話
実をいうと5,6月のこの時期は私は4連問というものを知りませんでした、、、。お恥ずかしながら4連問の存在を知ったのはcbtの1,2か月前でした。情報集めを全くしておらず、また過去問を解くスピードの遅かった私は試験直前期になって初めて4連問に触れ、当初は全く点数が取れなかったのです。
しかし要点を押さえて勉強することで短期間でも足を引っ張らないレベルに上げることはできました。cbtで高得点を目指す人も満点を狙うのはかなり難しいでしょうから8割ほど取れるレベルでもかなり十分だと思います◎
私が4連問について知ってから行った勉強、そしてのちのち先輩や同輩に聞いてすればよかったと思った勉強法をお伝えしますのでぜひご覧ください!
医学部cbtの4連問で問われる内容

4連問の各設問で問われる内容を以下にあげます。
1問目 医療面接で問うこと
2問目 身体診察
3問目 検査
4問目 病態生理
具体的な内容は、厚生労働省に記載の4連問の1例はのちほどお示しします。第2~4設問目は実は一つ前の設問の答えが問題文に記載されています。したがって問題を解いている最中に自分が合っていたのか間違っていたのかわかってしまうのです。これは間違いが続くとかなり精神的に追い込まれました💦
医学部cbtの4連問でのつまづきポイント

では4連問のどこにつまづきやすいのでしょうか?
①鑑別をする必要がある
4連問の一番のつまづきポイントだと思います!最初に各論を習うときは、「疾患→症状」というように、各々の疾患ではどのような症状が出るのか、必要な検査・治療は何かを覚えると思います。しかし4連問では逆に、「症状→疾患」というように症状から複数の疾患を思い浮かべ鑑別をする必要があります。各論を学ぶ時とは逆の考え方をするが難しく、私も大変苦戦しました、、、。
②CBTで一番最後のブロックである
先ほど述べたように4連問は6ブロックあるCBTの最後のブロックです。CBTは1日がかりで緊張もしますのでかなり疲れます。その中で最後のブロックでかなり頭を使う問題が出てくるので集中力を保つことが大変です。
③解いている最中に答えが分かる
こちらも先ほど述べたように4連問では問題文の中に1つ前の設問の答えが大抵載っています。したがって問題を解いている途中で自分がどれだけ間違えたか分かってしまうので、メンタルに来てしまう場合があります。
医学部cbt4連問の勉強法

お待たせしました!4連問のつまづきやすいポイントまで抑えたところで、勉強法をお伝えします!
結論から述べると、「各論をしっかり覚える+それぞれの設問の特徴を捉える+誤った選択肢の検討」です。
<各論をしっかり覚える>
まず各論でそれぞれの疾患にはどのような代表的な症状があり、診断するための所見や検査はなにか、治療法は何かをしっかりと覚えます。この土台が無いと4連問のような症例問題に太刀打ちできなくなってしまいます💦
各論をしっかり覚えた後に、総論で症状から何の疾患を想起できるか練習します。
<それぞれの設問の特徴を捉える~疾患 鑑別~>
設問1
設問1で問われることは前述した通り「医療面接で問うこと」です。ここで必要とされる力は症状から疾患を推論することです。今まで学んできた各論では疾患にはどのような症状があるかという考え方でしたが、4連問では逆の考え方が必要になります。
具体的に問題を見ていきましょう!
52歳の女性。午前4時頃に右肋骨の下の方が重苦しく、
時々差し込むような痛みを感じて目覚めた。痛みがだん
だんひどくなってきたため午前5時に救急外来を受診した。
吐き気はあるが吐いてはいない。小太りである。
この患者にまず聞くことはどれか。
A 血尿があるか。
B 黒色便があるか。
C 残尿感があるか。
D 昨夜、脂っこい食事を摂ったか。
E 家族にも同じ症状の人がいるか。
(正解:D)
上記の問題ではまず『右肋骨下に時々差し込むような痛みがある』というところに注目します。右季肋部痛であれば代表的な疾患として胆石症、胆嚢炎・胆管炎、肝炎などを思い浮かべます。胆石症や胆嚢炎は高脂肪食が原因であることが多いので、A~Eの選択肢の中だったらDが最も適した医療面接の質問となります。
このように「症状→疾患」という考え方を用いて問題を解きます。この考え方を身につけるにはまず、「各論をしっかり覚える」ことが大切なのです!
各論をしっかり覚えた上で、主要な症候をきたす代表的な疾患を重症度・頻度の高いものから覚えましょう!
例えば腹痛であれば部位別に覚えるといいと思います。下図のように心窩部痛であれば、急性冠症候群や胃十二指腸潰瘍、右上腹部痛であれば胆道刑や肝疾患、左上腹部痛であれば急性膵炎、側腹部痛であれば尿路結石、右下腹部痛であれば急性虫垂炎、下腹部痛であれば婦人科系疾患などです。
図:腹痛の部位 (診察ができる vol.2 鑑別診断 第1版)
他にも「問診で最も重要な質問はどれか」、逆に「最も重要性が低いものはどれか」などが問われます。
設問2
52歳の女性。午前4時頃に右肋骨下の重圧感と差し込むような
痛みを感じて目覚め、痛みが増強したため午前5時に救急外来
を受診した。悪心はあるが、嘔吐はない。昨夜は中華料理を食
べた。身長 152cm、体重 65kg。体温 37.8℃。脈拍 76/分、
整。血圧 124/78 mmHg。心音と呼吸音に異常は認めない。
腹部は平坦で、肝・脾を触知しない。
予想される身体所見はどれか。
A 金属性の腸雑音
B 肋骨脊柱角叩打痛
C Murphy徴候
D Blumberg徴候
E McBurney徴候
(正解:C)
設問2では身体所見が提示されます。設問1で胆石症、胆嚢炎が示唆されたことから、2つの疾患で特徴的なMurphy兆候を選びます。
設問1と同様に、「身体所見→疾患」という考え方を用いて解きます。今回は疾患を想起したうえで、それに当てはまる症状、身体所見を選びました。
設問3
52歳の女性。右肋骨下の重圧感と差し込むような痛みを感じて 目
覚め、痛みが増強したため救急外来を受診した。昨夜は中華 料
理を食べた。身長 152cm、体重 65kg。体温 37.8℃。脈拍 76/分、
整。血圧 124/78mmHg。腹部は平坦で、肝・脾を触知しない。右肋
骨下領域に圧痛があり、軽く叩打すると痛みが増強する。 Murphy 徴
候を認める。血液学所見:赤血球 510万、 Hb 14.5g/dL、Ht 46%
、白血球 14,000、血小板 18万。血液生化学所見:総ビリルビン
1.8mg/dL、直接ビリルビン 1.5mg/dL、AST 38 IU/L、ALT 37
IU/L、アミラーゼ 80 IU/L(基準37~160)。
まず行う検査はどれか。
A 腹部単純CT
B 腹部超音波検査
C 腹部エックス線撮影
D 上部消化管造影
E 上部消化管内視鏡検査
(正解:B)
設問3では検査所見に着目します。今回は白血球、ビリルビン、胆道系酵素の数値が高いことに注目します。やはり胆嚢炎や胆石症が疑われると考えることができます。検査としてはCTも必要ではありますが、『まず』という言い回しがあるため、侵襲性が低い、腹部超音波検査が答えになります。
設問1と2同様、「検査所見→疾患」という考え方をすることがポイントです。また、『まず行う検査』というように問われたら、侵襲性が低い・金額が安価なものなどから選ぶようにしましょう!
設問4
52歳の女性。右肋骨下の重圧感と差し込むような痛みを感じて目覚め、
痛みが増強するため救急外来を受診した。昨夜は中華料理を食べた。
身長 152cm、体重 65kg。体温 37.8℃。脈拍 76/分、整。血圧
124/78mmHg。腹部は平坦で、肝・脾を触知しない。右肋骨下領域に
圧痛があり、軽く叩打すると痛みが増強する。 Murphy 徴候を認める。
血液学所見:赤血球 510万、 Hb 14.5g/dL、 Ht 46%、白血球
14,000、血小板 18万。血液生化学所見:総ビリルビン 1.8mg/dL、
直接ビリルビン 1.5mg/dL、AST 38 IU/L、ALT 37 IU/L、アミラー
ゼ 80 IU/L (基準37~160)。腹部超音波像 ( 白黒表示 ) を示す。
この患者で脂っこいものを食べた後に起こっ
た腹痛の発生機序に関わるホルモンはどれか。
A モチリン
B ガストリン
C セクレチン
D ソマトスタチン
E コレシストキニン
(正解:E)

設問4の画像より、胆石症であることが分かりました。本症例の腹痛は胆嚢が原因であった為、胆嚢収縮作用を持つコレシストキニンが答えとなります。
設問4は推論する力というより、各論で学ぶ知識を問われています。他にも「この疾患はどれか」「好発部位はどこか」などが問われます。
< 誤った選択肢の検討 >
さいごにとても重要なのが、 誤った選択肢の検討 をするということです。
設問2を例に挙げると、
金属性の腸雑音:イレウス
肋骨脊柱角叩打痛:腎盂腎炎
Murphy徴候:胆嚢炎、胆石症
Blumberg徴候:腹膜刺激症状
McBurney徴候 :虫垂炎
というように、それぞれの選択肢がどの疾患や症状に当てはまるのか検討します。このように解いた後に必ず正解以外の選択肢も見ることで、知識を増やしていくことができます◎
さいごに
4連問の勉強法についてお話してきましたがいかがでしたでしょうか。皆さんの力になれたらうれしいです!
医学生道場は医学部の勉強でお悩みの方のお力になるべく、試験対策・留年対策など各種対策にはとても力を入れています。
これまで多くの医学生の方にご利用いただいているため実績も豊富です!
安心してご利用いただける環境が整っておりますので、少しでも「医学生道場が気になる!詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、公式LINEもしくはお問合せフォームからご相談ください。
相談料は一切かかりませんから、気になることやお悩みなどお気軽にご相談・お問合せください。
また、LINEでお得な情報も配信しておりますので、お友達追加もよろしくお願いします♪
また、LINEでお得な情報も配信しておりますので、お友達追加もよろしくお願いします♪