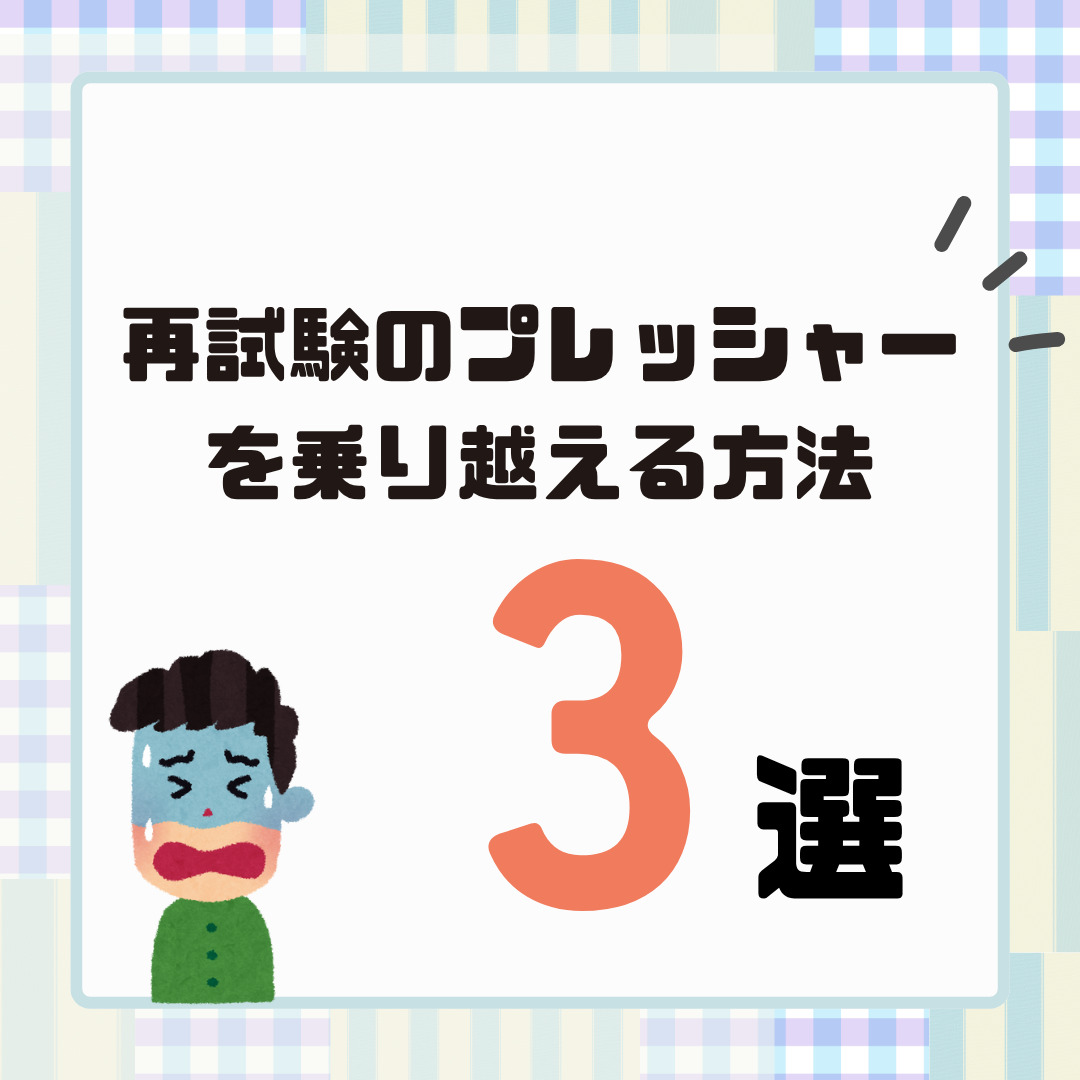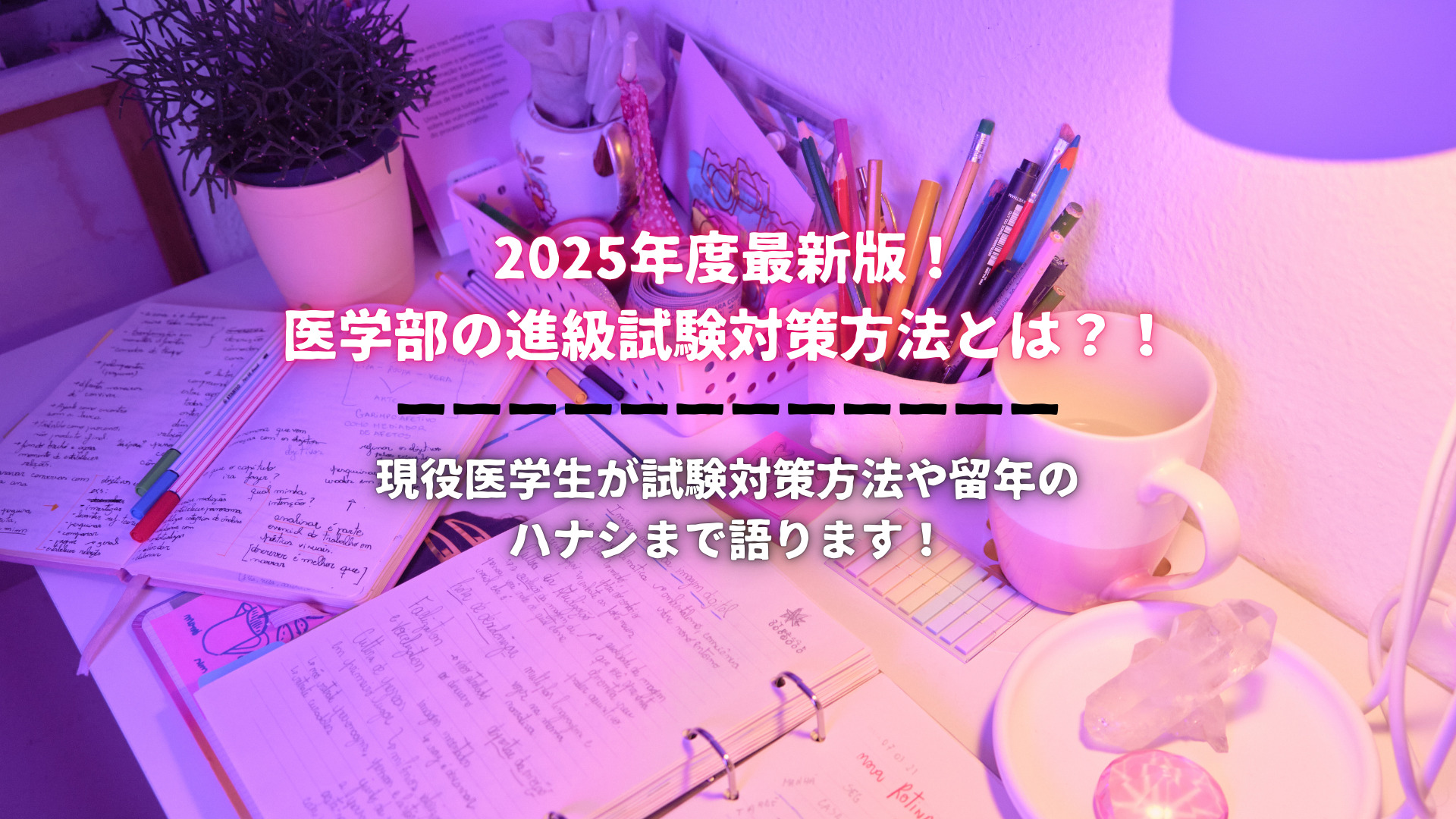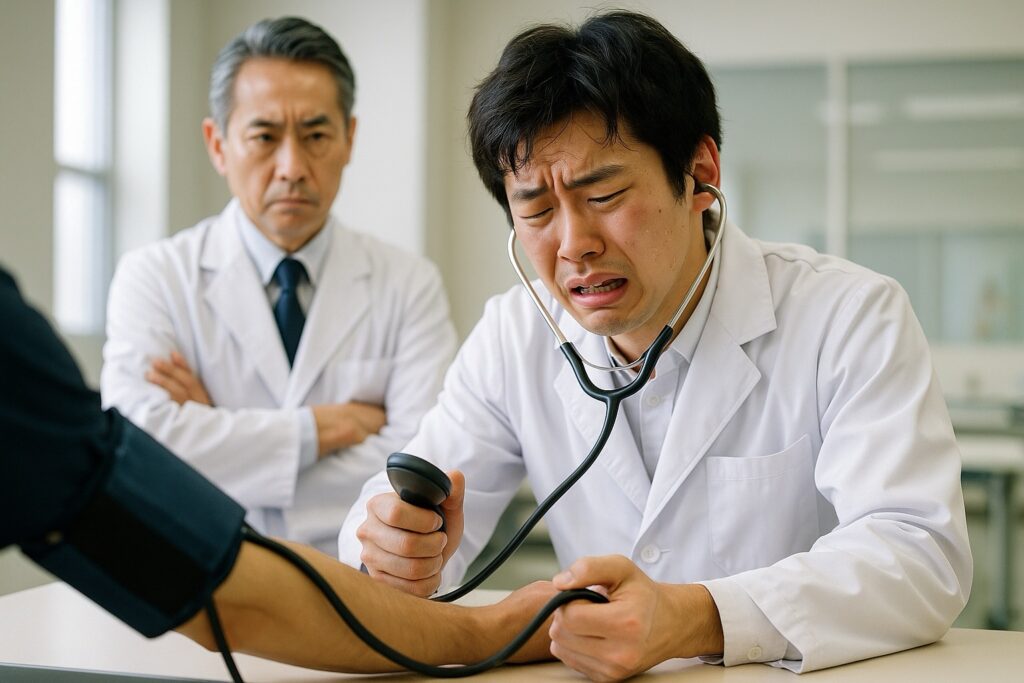
目次
👤 著者プロフィール
著者:原田
所属:株式会社リーフェホールディングス 経営企画室 部長
資格・経歴:
法学部卒|政治学研究科 修士・博士|政治学教員
自己紹介:
幼少期より病気がちで、こんにち無事に生活できているのは、医療とそれに関わる人たちのお陰です。将来の医師として、社会に貢献できる医学生の方を積極的にサポートしていきます。
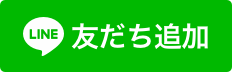

医学部OSCE対策 重要ポイント3選
医学部OSCEで落ちないための対策とは?
1. 単一領域評価項目に特に注意を払う
OSCEの評価カテゴリーの中で、「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」は単一領域として評価されるため、一つのミスが致命的になる可能性があります。これらの項目は他の評価で挽回することができないため、特に重点的に対策が必要です。医療面接では時間管理と必須質問項目の把握、手技では正確な手順の暗記と感染予防の意識、救急では迅速かつ的確な判断と処置の練習を徹底しましょう。これらの単一領域で高評価を得ることが、OSCE合格への近道です。
2. 患者さんへの配慮と適切なコミュニケーションを実践する
OSCEでは医療技術だけでなく、医療者としての態度やコミュニケーション能力も重要な評価対象です。患者確認(名前と生年月日)の徹底、診察前の説明と同意の取得、診察中の声かけ(「冷たいかもしれません」「痛かったら教えてください」など)、適切な相槌や共感の言葉など、細かい配慮の積み重ねが高評価につながります。特にデリケートな質問の前には「皆さんにお聞きしていることなのですが」などのクッション言葉を使うこと、患者さんの言葉を繰り返すことで理解を示すことなど、コミュニケーションの質を高める工夫が必要です。
3. 反復練習と時間管理の習得が成功の鍵
OSCEの合格には計画的な反復練習と厳格な時間管理の習得が不可欠です。試験の1ヶ月前から本格的な対策を始め、複数人でのグループ練習や模擬試験形式での練習を重ねることが効果的です。特に医療面接では10分間での時間配分(例:8分で現病歴・生活歴、2分で解釈モデル・クロージング)を意識し、各診察・手技でも制限時間内に終わらせる練習を繰り返し行いましょう。練習の様子を録画して客観的に評価することや、先輩に患者役を依頼して実践的な練習を行うこともおすすめです。「やって終わり」ではなく、毎回の練習後に反省会を行い、改善点を次回に活かす姿勢が重要です。
はじめに – OSCEの恐怖とは
医学部4年生の皆さん、こんにちは。医学生道場です。
「OSCEに落ちる」というワードを聞くだけで、胃が締め付けられるような不安を感じていませんか?
「OSCE、落ちたらどうしよう…」
「公的化されたから、去年より厳しくなったって本当?」
「再試験になったら、臨床実習に間に合わなくなるかも…」
このような不安は、医学部4年生の誰もが抱えるものです。特に2023年4月からOSCEが公的化され、全大学で統一基準での試験実施となった今、合格率の低下を懸念する声も聞こえてきます。
しかし、そんな不安を抱える皆さんに朗報です。本記事では、OSCEの基礎知識から合格率、そして落ちないための具体的対策までを徹底解説します。
最後まで読めば、あなたのOSCE対策が大きく前進すること間違いありません。
医学部OSCE合格のためのチェックリストを作成しましたのでご活用ください。
📞 お問い合わせ・お申し込みはこちら
無料相談実施中
- 期間:随時受付(水木曜日をのぞく13ー20時まで ※ただし社内休暇期間をのぞく)
- 特典:個別相談・学習計画作成
連絡先
- 電話:0422-26-7222
- メール:https://igakuseidojo.com/official_2025/contact/
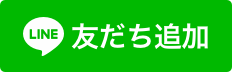
絶対に合格するためのOSCEチェックリスト
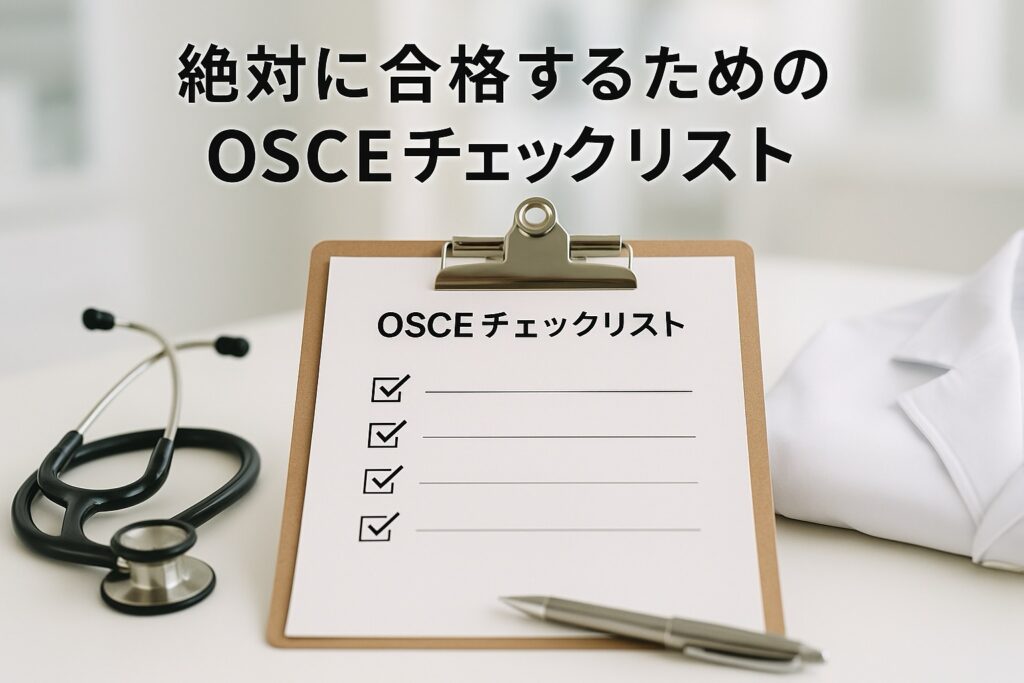
事前準備編(試験1ヶ月前~)
学習計画
- [ ] 試験日から逆算した学習スケジュールを立てる
- [ ] OSCE評価表の各項目を確認し、評価ポイントを把握する
- [ ] CATOの公式ガイドラインや動画を視聴する
- [ ] 大学から提供される課題や評価基準を確認する
グループ学習
- [ ] 練習パートナーを確保する(最低3~4人のグループを作る)
- [ ] 週に最低2回以上の練習セッションを設定する
- [ ] 先輩に患者役をお願いする機会を作る
- [ ] 練習の様子を録画し、後で振り返る習慣をつける
医療面接対策編
基本構成の習得
- [ ] 問診の基本フロー(導入→現病歴→生活歴→解釈モデル→クロージング)を完全に暗記する
- [ ] OPQRSTの各項目を具体的な質問文で言えるようにする
- [ ] 「さしすせそ」「かきくけこ」の生活歴質問項目を暗記する
- [ ] 解釈モデルの質問パターンを3種類以上用意する
コミュニケーションスキル
- [ ] 適切な相槌の打ち方を練習する
- [ ] デリケートな質問前のクッション言葉を用意する
- [ ] 共感の言葉(「お辛いですね」など)を自然に使えるようにする
- [ ] 患者の言葉を繰り返す技術を身につける
- [ ] 明るく親しみやすい声のトーンを意識する
時間管理
- [ ] 10分間での時間配分の目安を設定する
- [ ] 時計を見ながら練習する習慣をつける
- [ ] 8分で現病歴・生活歴を終え、2分で解釈モデル・クロージングができるようにする
- [ ] メモを取りながら問診する技術を磨く
身体診察・手技対策編
全診察項目共通
- [ ] 患者確認(名前・生年月日)を必ず行う習慣をつける
- [ ] 各診察の開始前と終了時の声かけパターンを決めておく
- [ ] 手洗い・消毒のタイミングを確認する
- [ ] 聴診器など器具の使用前の声かけを練習する(「冷たいかもしれません」など)
- [ ] 各診察・手技の制限時間を把握し、時間内に終わらせる練習をする
個別項目チェック
- [ ] バイタルサイン測定の手順を完璧に覚える
- [ ] 頭頚部診察の全項目を順序通り行えるようにする
- [ ] 胸部診察の聴診点と順序を確認する
- [ ] 腹部診察の4ステップ(視診→聴診→打診→触診)を順序通り行う
- [ ] 神経診察の反射テストなどの手順を確認する
- [ ] 基本手技(採血、点滴など)の手順と感染予防策を徹底する
- [ ] 救急対応の手順(意識確認→気道確保→呼吸・循環確認)を体に染み込ませる
試験直前対策編(1週間前~)
メンタル面
- [ ] 十分な睡眠と栄養摂取を心がける
- [ ] リラックス法(深呼吸など)を練習しておく
- [ ] 本番さながらの模擬試験を経験しておく
- [ ] 失敗した場合の切り替え方を心の中で準備しておく
身だしなみ・持ち物
- [ ] 白衣のクリーニングとアイロンがけ
- [ ] 髪型の確認(長い場合は束ねる準備)
- [ ] 聴診器、ペン、時計など必要物品の確認
- [ ] 爪を短く切り、アクセサリー類は外しておく
- [ ] 試験会場への行き方と所要時間の確認
試験当日チェック
朝の準備
- [ ] 十分な朝食をとる
- [ ] 余裕をもった起床と出発
- [ ] 身だしなみの最終チェック
- [ ] 持ち物の再確認
各ステーション直前
- [ ] 深呼吸で落ち着く
- [ ] 課題文を丁寧に読む
- [ ] 「患者確認」を最初に行うことを意識する
- [ ] 時間配分を頭に入れる
試験中
- [ ] 一つのステーションが終わったら、次に切り替える
- [ ] 失敗しても動揺せず、次の行動に移る
- [ ] 時間が足りなくなりそうな場合、優先順位の高い項目から行う
- [ ] 患者さんへの配慮の声かけを常に心がける
特に「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」の単一領域評価項目は重点的にチェックしておくことをお勧めします。
医学生道場では、このチェックリストの項目一つひとつについて、医師講師が丁寧に指導し、あなたの弱点を強化します。OSCE対策で不安なことがあれば、ぜひご相談ください。
1. OSCE(オスキー)とは – その目的と重要性

OSCEは「Objective Structured Clinical Examination(客観的臨床能力試験)」の略称で、医学部4年生(Pre-CC OSCE)の臨床実習前に行われる実技試験です。
CBTが医学的知識を評価するペーパーテストであるのに対し、OSCEは医療面接や身体診察、基本的臨床手技などの実践的スキルを評価します。これは、臨床実習(クリニカル・クラークシップ:CC)に進むための”仮免許”試験として法的に位置づけられています。
2023年4月からは、OSCEとCBTはともに公的化され、全国の医学部で同一の基準で実施されるようになりました。つまり、従来は各大学の裁量で行われていた評価が、より厳格かつ統一的になったということです。
OSCEの主な評価領域
OSCEでは主に以下の領域が評価されます:
- 医療面接 – 患者さんとの対話を通じて情報を収集する能力
- 身体診察 – バイタルサイン測定、頭頚部診察、胸部診察、腹部診察、神経診察など
- 基本的臨床手技 – 採血や注射などの医療技術
- 救急 – 救急時の対応能力
これらの能力が、実際の臨床現場に足を踏み入れる前に十分であるかを確認するのがOSCEの役割です。
2. OSCEの合格率と再試験の実態
合格率は本当に下がっているのか?
「公的化でOSCEの合格率が下がった」という噂を耳にしたことがあるかもしれません。実際のところはどうなのでしょうか?
実は、OSCEの合格率は約90%前後と依然として高い水準を保っています。例えば令和5年度の共用試験の実施状況によると、不合格率は3.4%(欠席を含めても4.2%)となっています。
つまり、10人に1人程度が不合格になるという計算です。決して無視できる数字ではありませんが、適切な準備をすれば十分に合格可能な試験であることも事実です。
再試験のルールと注意点
OSCEに不合格となった場合は再試験を受けることができますが、いくつか重要な注意点があります:
- 再試験は不合格となった領域のみ – たとえば神経診察が不合格だった場合、再試験は神経診察のみです。
- 再試験料は高額 – CBTとOSCEの受験料の合計額をもう一度支払う必要があります。
- 実習準備への影響 – 再試験のために実習準備が遅れると、その後のスケジュールにも影響します。
これらの理由から、初回の試験でしっかり合格することが重要です。
3. OSCEの評価方法を理解する
OSCEの評価方法は意外と複雑です。以下の5つのカテゴリーに分けて評価されています:
- 「医療面接」:A1,B1(単一領域として評価)
- 「患者への配慮」:A2~A7
- 「診察テクニック(身体診察)」:B2~B6
- 「診察テクニック(基本的臨床手技)」:B7
- 「救急」:A8,B8(単一領域として評価)
このうち特に注意すべきは、単一領域で評価される「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」です。これらは他の評価項目で挽回することができないため、一つのミスが致命的になる可能性があります。
一方、「患者への配慮」と「診察テクニック(身体診察)」は複数の診察・手技での評点を合計して判定されるため、1つの項目で失敗しても他でカバーできる可能性があります。
4. OSCEに落ちる人の特徴とは?

OSCEに落ちる人には、いくつかの共通する特徴があります。あなたは当てはまっていませんか?
1. 時間管理ができない
OSCEは各ステーションで厳格な時間制限があります。特に医療面接は10分という限られた時間内に、多くの情報を収集する必要があります。時間配分を練習せずに本番に臨むと、重要な項目を聞き忘れたり、時間切れになったりするリスクが高まります。
2. 手順を誤ってしまう
特に手技系の試験では、手順を間違えるとその時点で不合格になる可能性があります。例えば、採血の際に針を抜く前に駆血帯を外してしまうなどの基本的な手順ミスが致命傷となります。←とくに注意が必要です(毎年このミスでOSCE落ちする方がいらっしゃいます)
3. 患者確認を怠る
患者さんの名前と生年月日の確認は、どの課題でも必須です。この基本的なステップを忘れると、それだけで大きく減点されます。
4. 配慮に欠ける言動
患者さんへの配慮の声かけ(例:「聴診器が冷たかったらおっしゃってください」など)を忘れると評価が下がります。医療者として当然の配慮ができているかどうかは、重要な評価ポイントです。
5. 専門用語の多用
患者さん(模擬患者)に対して専門用語を多用すると減点対象となります。わかりやすい言葉で説明する能力も臨床能力の一つとして評価されます。
5. 医療面接の対策 – 合格するための具体的アプローチ

医療面接はOSCEの中でも特に対策が必要な領域です。10分間という限られた時間の中で、必要な情報をすべて収集しなければなりません。
医療面接の基本フロー
効率的な医療面接のために、以下のフローを覚えておきましょう:
- 導入
- 患者さんの本人確認(フルネームと生年月日)
- 医療面接の同意を得る
- 自己紹介
- 主訴・現病歴(OPQRST)
- O(Onset): いつから症状があるか
- P(Palliative/Provocative): 何かで良くなる/悪くなることはあるか
- Q(Quality/Quantity): どのような症状か、どの程度か
- R(Region): 場所はどこか
- S(Symptoms): 随伴症状はあるか
- T(Time course): 時間経過、これまでの対応
- 生活歴(さしすせそ、かきくけこ)
- さ「酒・タバコ(程度・頻度)」
- し「職歴、食事内容」
- す「睡眠、ストレス」
- せ「生理(最終月経)、性活動」
- そ「その他(生活などについて)」
- か「家族歴(血縁者の病気、同居人の症状)」
- き「既往歴」
- く「薬→常用薬(薬の容量・回数は守っているか)、アレルギー」
- け「健診、他の病院にかかっているか」
- こ「渡航歴」
- 解釈モデル(かきかえ)
- か「解釈モデル」:患者さんが予想・心配している病気
- き「検査や治療の希望」
- か「感情」:病気に対する感情
- え「生活への影響」
- クロージング
- 要約:「お話を整理すると…」
- 質問の有無確認
- 次の予定の説明と配慮の言葉
【医療面接のコツ】
- 時間配分を明確に:8分で現病歴と生活歴を聞き、残り2分で解釈モデルとクロージングを行うなど、時間配分の目安を持ちましょう。
- 適切な相槌を打つ:患者さんの言葉を繰り返したり、「お辛いですね」などの共感の言葉を適宜挟みましょう。
- メモを取る練習:話を聞きながらメモを取る練習も重要です。完璧に記録する必要はありませんが、要点は押さえましょう。
- オープンクエスチョンから始める:「今日はどうなさいましたか?」という開かれた質問から始め、徐々に具体的な質問に移行しましょう。
- プライバシーへの配慮:デリケートな質問の前には「皆さんにお聞きしていることなのですが」などのクッション言葉を入れましょう。
6. 身体診察・手技の対策

身体診察や手技においては、正確な手順と患者さんへの配慮が評価ポイントです。
【身体診察のコツ】
- 声かけを忘れない:「これから〇〇の診察をします」「痛かったら教えてください」など、診察の各段階での声かけが必須です。
- 手順を完全に暗記する:診察の手順は完全に体に染み込むまで練習しましょう。順番を間違えると大きく減点されます。
- 時間を意識:各診察項目の所要時間を把握し、時間内に終わらせる練習をしましょう。
- 手洗いを徹底:診察の前後での手洗いやアルコール消毒は基本中の基本です。
- 聴診器の扱い:聴診器を当てる前には「冷たいかもしれません」と一言添え、必ず自分の手で温めましょう。
【手技のコツ】
- 感染予防を意識:手袋の着脱、針刺し事故防止など、感染予防の観点も評価されます。
- 説明と同意:手技を行う前には必ず説明し、同意を得ましょう。
- 物品の確認:必要な物品が揃っているか必ず確認しましょう。
- 廃棄物の処理:使用済みの物品の適切な処理も評価対象です。
7. OSCE対策の実践ポイント
【練習のコツ】
- ①複数人での練習:医師役、患者役、評価者役を交代で行い、お互いに評価し合いましょう。
- ②録画して自己評価:自分の診察の様子を録画して、客観的に評価することも効果的です。
- ③時間を計る:必ず時間を計りながら練習し、時間感覚を養いましょう。
- ④模擬試験の活用:可能であれば、模擬試験や学校のOSCE対策講座に積極的に参加しましょう。
- ⑤先輩からのアドバイス:OSCEを経験した先輩からのアドバイスは非常に貴重です。具体的なコツや注意点を聞きましょう。
先輩から聞いた「やっておいてよかったこと」8選
- ①先輩・先生にすぐ相談! – 困ったらまず、経験者に頼ろう。
- ②いろいろな友達と問題を出し合う – 部活・実習班・近くの席の人など、様々な人と練習しよう。
- ③医療面接の練習は特に厳しめに! – 細かい言葉づかい・流れに注意。
- ④練習の様子を録音・録画して後でチェック! – 自分の癖を客観的に知るチャンス。
- ⑤練習直後に反省会! – 「やって終わり」ではなく「改善→成長」へ。
- ⑥いろいろな人に見られながら練習する – 緊張感に慣れることが大切!
- ⑦先輩に頼んで患者役をしてもらう – リアリティある練習ができる!
- ⑧3〜4人でチーム練習 – 医師・患者役でない人からの客観的フィードバックが効果絶大!
8. 試験当日の心構え

【精神面の準備】
- ①適度な緊張は必要:緊張しすぎは禁物ですが、適度な緊張感は集中力を高めます。
- ②失敗してもクヨクヨしない:一つのステーションで失敗しても、次のステーションに切り替えましょう。
- ③深呼吸を意識:緊張したら深呼吸を。酸素を取り入れることで冷静になれます。
【身体面の準備】
- ①前日は十分な睡眠:疲れた状態では実力を発揮できません。
- ②朝食はしっかり取る:低血糖状態では集中力が落ちます。
- ③身だしなみを整える:白衣はアイロンをかけ、髪型も整えましょう。第一印象も評価の一部です。
おわりに – 自信を持ってOSCEに臨むために
OSCEは確かに緊張する試験ですが、しっかりと準備すれば90%以上の学生が合格している試験でもあります。
重要なのは、計画的な準備と反復練習です。特に「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」の単一領域評価項目は、重点的に対策しましょう。
また、手順の暗記だけでなく、患者さんへの配慮や医療者としての態度も評価対象であることを忘れないでください。これらは単なる試験のためではなく、将来の医師としての基本的な姿勢を身につけるための大切な学びです。
医学生道場では、現役医師講師による個別指導を通じて、OSCEの対策を全力でサポートしています。不安や悩みがある方は、ぜひご相談ください。
みなさんがOSCEを無事に合格し、充実した臨床実習へと進めることを心より願っています。
医学生道場 医学部OSCE対策コースの詳細はコチラ
少しでも興味をお持ちの方は、公式LINEもしくはお電話、ご相談フォームからお気軽にお問合せください! 相談料は一切かかりません!
お役立ち情報満載の各SNSもぜひチェックしてください!
📞 お問い合わせ・お申し込みはこちら
無料相談実施中
- 期間:随時受付(水木曜日をのぞく13ー20時まで ※ただし社内休暇期間をのぞく)
- 特典:個別相談・学習計画作成
連絡先
- 電話:0422-26-7222
- メール:https://igakuseidojo.com/official_2025/contact/
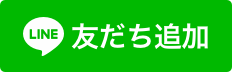
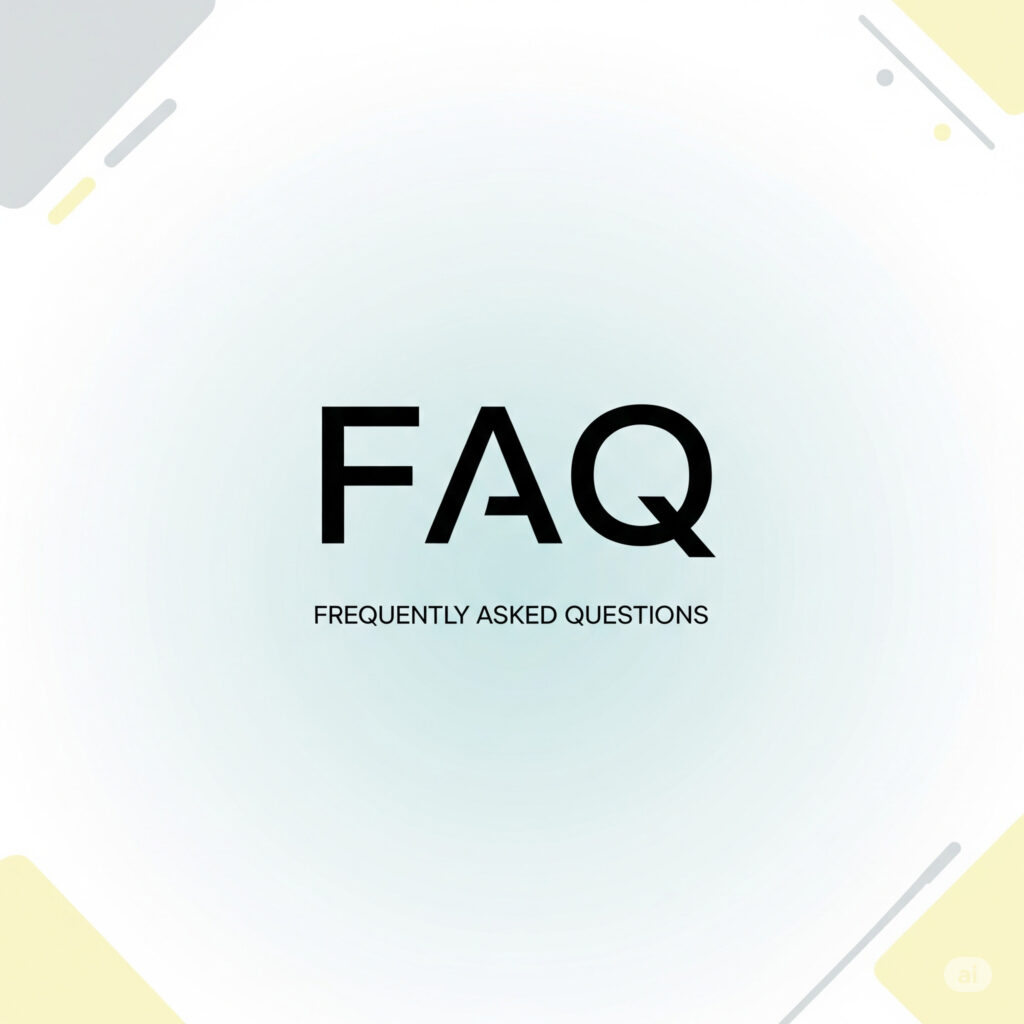
よくあるご質問(FAQ)
Q1: OSCEの合格率はどのくらいですか? 公的化されてから難しくなったのでしょうか?
A: OSCEの合格率は約90%前後と比較的高い水準を維持しています。令和5年度の共用試験実施状況によると、不合格率は3.4%(欠席を含めても4.2%)となっています。
2023年4月からOSCEが公的化され、全大学で統一基準での試験実施となりましたが、極端に合格率が下がったというデータはありません。ただし、評価がより客観的かつ厳格になったため、これまで各大学の裁量で「大目に見られていた」部分については、しっかりとした準備が必要になったと言えるでしょう。
100人のクラスで約10人が再試験を受けることになりますが、適切な準備と練習を行えば、十分に合格可能な試験です。特に「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」の単一領域評価項目は重点的に対策しておくことをお勧めします。
Q2: OSCEの対策はいつから始めるべきですか? 準備期間の目安を教えてください。
A: OSCEの対策は、本番の約1ヶ月前から本格的に始めるのが理想的です。アンケート調査でも、「1ヶ月前から」という回答が約半数、次いで「2週間前から」が多いという結果が出ています。
ただし、基本的な手技や診察法については、普段の実習や授業の中で少しずつ身につけておくことが重要です。特に手技の正確な手順や、患者さんへの声かけなどは日頃から意識しておくと良いでしょう。
準備のタイムラインとしては以下を目安にすると良いでしょう:
- 1ヶ月前:評価表の確認、グループ学習の開始、基本項目の確認
- 3週間前:各ステーションの練習開始、時間を測りながらの練習
- 2週間前:集中的な反復練習、弱点の強化
- 1週間前:模擬試験形式での練習、メンタル面の調整
- 前日:軽い復習のみ、十分な睡眠の確保
CBT直後からOSCE対策を始める場合も多いですが、焦らず計画的に取り組むことが成功の鍵です。
Q3: OSCE再試験になった場合、どうなりますか? 臨床実習に影響はありますか?
A: OSCE再試験になった場合の流れと影響は以下の通りです:
- ①再試験の範囲:不合格となった領域(≒手技)のみを再受験します。例えば、神経診察が不合格だった場合、再試験は神経診察のみです。
- ②再試験料:再受験料としてCBTとOSCEの合計金額をもう一度支払う必要があります。これは経済的負担となりますので、初回合格の重要性が高いと言えます。
- ③臨床実習への影響:大学によって対応は異なりますが、多くの場合、再試験に合格するまで臨床実習に参加できません。タイミングによっては実習の開始が遅れ、カリキュラムの調整が必要になることもあります。
- ④留年との関係:再試験のタイミングと結果によっては、臨床実習に十分な期間参加できず、留年につながるケースもあります。特に年度末近くの再試験で不合格となった場合はその可能性が高まります。
- ⑤実習準備への影響:再試験対策に時間を取られるため、臨床実習の事前準備が十分にできないこともあります。
このような理由から、初回のOSCE試験でしっかり合格することが非常に重要です。もし不安がある場合は、早めに対策を始め、必要に応じて医学生道場のようなサポートを活用することをお勧めします。