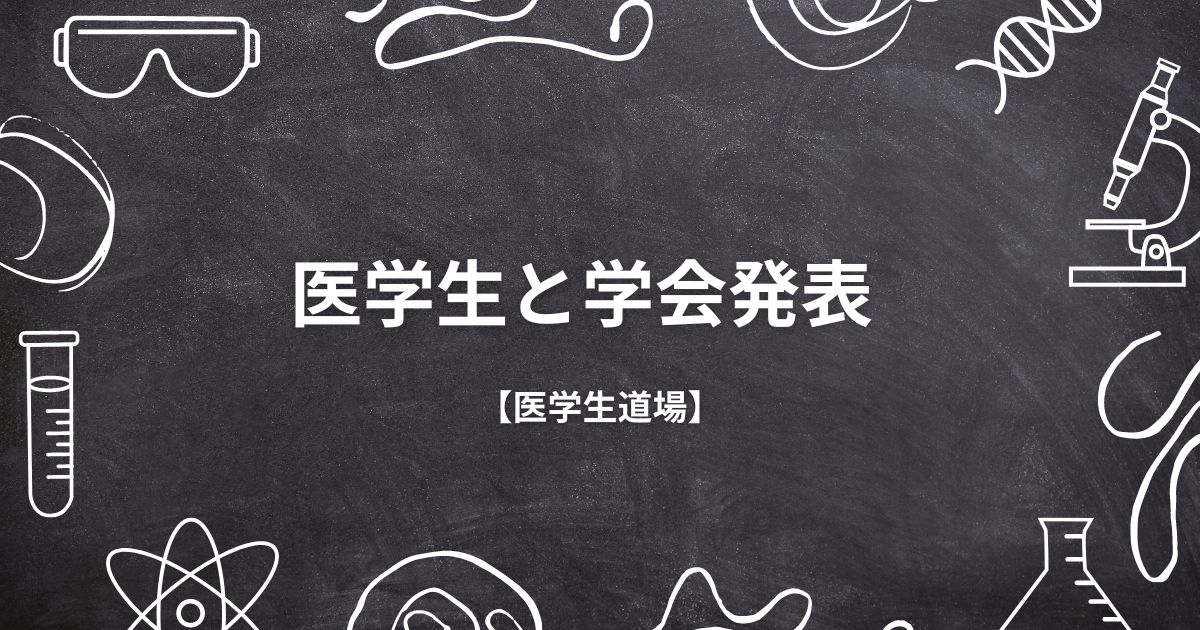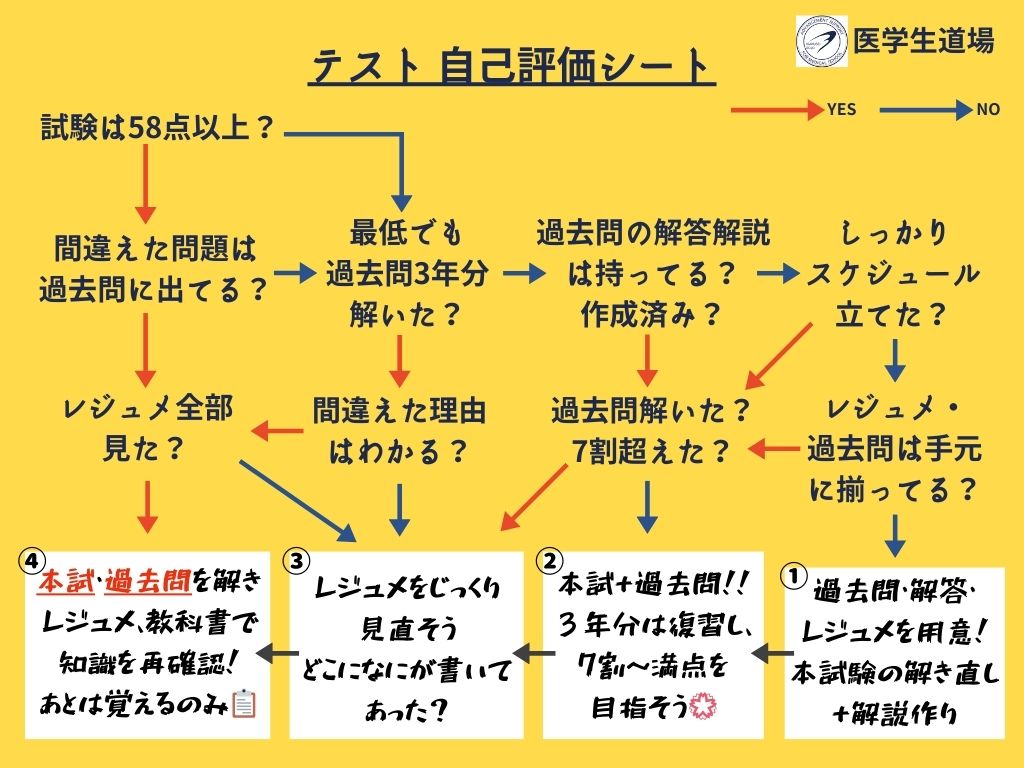著者名:松下🌙
所属:関東私立大、経営
資格や経歴:経営学科在学中、アメリカ交換留学、簿記二級📕
過去のブログ:
・【医学生勉強法】有意義な学生生活の為に!現役医師講師と医師を目指す💉
・医学生の為のもふもふ癒しスポット【サモエドカフェ】で試験勉強の不安やストレスをリフレッシュ🐶
・医学生必見!学習効率を向上させるおすすめ【勉強アプリ】7選📱
医学に関する情報を経営学で培った知識で効果的に伝達していく。このことを意識しながら、将来医学を牽引される方に有益な情報をお届けするサポートがしたいと思っております✨
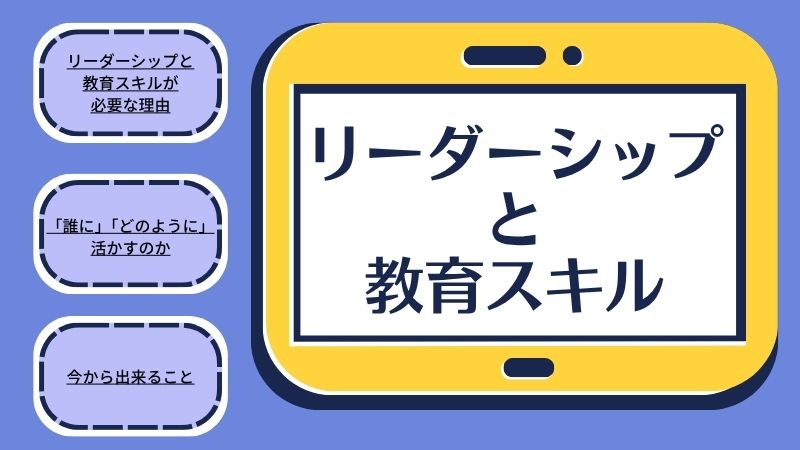
目次
重要ポイント👀
・未来の医師には、医学知識に加え「リーダーシップ」と「教育スキル」が不可欠
・リーダーシップとは「チームメンバーが能力を最大限に発揮できる環境を作る力」である
・教育スキルとは「相手の主体性を引き出す対話力」である
※お勧めの本も掲載📚
はじめに
医学生の皆さん、こんにちは🌞医学生道場です💉
突然ですが、皆さんが考える「いい医師」の定義はどのような医師でしょうか?医学知識や技術が優れている医師、患者さんから信頼されている医師、チームを上手くまとめられる医師……
様々挙げられると思います📜では、そのような「いい医師」に必要なものは何でしょうか❓❓
今回、皆さんにぜひ考えて頂きたいのは、
「リーダーシップ」と「教育スキル」という、医学知識や技術とは少し異なる、しかし未来の医療を担う上で不可欠なスキルです📚
「リーダーシップ?」「教育スキル?」「それは、ベテラン医師になってからでしょ?」そう思った人もいるかもしれません💦
しかし、これらは医学生である今だからこそ、育て始めるべき重要なスキルなんです‼️なぜ、リーダーシップと教育スキルが必要なのか?

皆さんが医師になる頃、医療の現場は今とは大きく様変わりしているでしょう🛸高齢化の加速、多死社会への突入、そしてAIやデータサイエンスの活用がより盛んになります。そんな複雑で変化の激しい時代を生き抜くために、そして、より良い医療を創造していくためにも、リーダーシップと教育スキルが不可欠となってくるのです。
⇓⇓ 理由を具体的に見ていきましょう ⇓⇓
理由1:医療がチーム戦へとシフトしているから昔の医療は、一人の医師がすべての責任を負う「個人戦」の側面が強かったかもしれません🧑⚕️しかし、現代の医療は多職種連携が当たり前の「チーム戦」です。医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門家が協力し合い、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供しています💊
このチームの中心となり、全体を統率するのが医師の役割です。医師には、チームメンバーそれぞれの専門性を理解し、尊重し、適切な役割分担を行うリーダーシップが求められます⭐
❓どういうリーダーシップが求められる❓
📍目標設定力: 患者さんの治療目標をチーム全体で共有し、具体的な行動計画を立てる。
📍コミュニケーション力: チームメンバーと円滑な対話を行い、意見を調整し、建設的な議論を促す。
📍問題解決力: チーム内で発生した課題や衝突を円満に解決し、前向きに進める。
📍ファシリテーション力: カンファレンスやミーティングで、誰もが意見を出しやすい雰囲気を作り、議論を活性化させる。
一口にリーダーシップと言っても、様々な要素が求められます。
理由2:患者さんの「主体性」を引き出すことが重要になっているからこれからの医療は、「医師がすべてを決める」という一方的なものではなく、患者さんが自らの治療に積極的に関わる「患者主体の医療」へと移行していきます🩺
患者さんに治療法をただ説明するだけでなく、なぜその治療が必要なのか、どんなメリット・デメリットがあるのかを理解してもらい、患者さん自身が納得して選択できるように導くことが重要です⚠️
これはまさに、患者さんを「教育する」プロセスと言えます✍
また、生活習慣病の予防や慢性疾患の管理においては、患者さん自身が日々の生活の中で健康的な習慣を身につけることが不可欠です。医師は、患者さんが自ら行動を変えられるように、知識を伝え、モチベーションを高め、行動を促す教育者としての役割を担います📚
理由3:変化の激しい時代に、自らも学び続ける必要があるから医学は日進月歩で進歩しています。皆さんが医師として働き始めてからも、新しい治療法や薬、技術が次々と登場します。医師は生涯にわたって学び続けることが宿命です📜
しかし、ただ情報をインプットするだけでは不十分です❌複雑な情報を整理し、本質を理解し、自分の言葉で他者に伝える「教育スキル」は、自分自身の学習効率を高める上でも非常に役立ちます👍
また、後輩医師や研修医を指導する立場になったとき、どのように知識や技術を教えれば、相手が効果的に学べるのかを理解していることは、日本の医療全体の質の向上に直結します⬆️
リーダーシップと教育スキルを「誰に」「どのように」活かすのか?
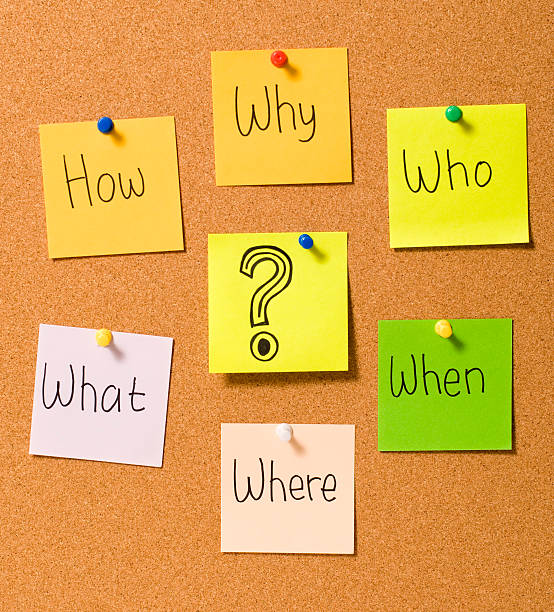
ここからは、具体的なシチュエーションを想像しながら、リーダーシップや教育スキルがどのように役立つのかを見ていきましょう🔍
1.対患者 – 健康を一緒に考える医師として
患者さんとの対話は、医師の仕事の大部分を占めます。この対話の中で、教育スキルは極めて重要な役割を果たします💉
📌疾患教育: 診断名だけでなく、その病気のメカニズム、なぜその症状が出るのかを、患者さんが理解しやすい言葉で説明する。
📌治療選択のサポート: 治療の選択肢を複数提示し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明する。患者さんの価値観や生活スタイルを尊重し、意思決定をサポートする。
📌行動変容の支援(病気予備軍・慢性疾患患者): 「健康診断で血糖値が高いと言われたけど、どうしたらいいかわからない…」という患者さんに対し、ただ「食事に気を付けて」と言うのではなく、具体的な食事のアドバイス(例:野菜から先に食べる、ご飯を半分にする)や、運動の提案(例:一駅分歩いてみる)など、スモールステップで実行可能な方法を提示する。
ここで大切なのは、
「一方的に教える」のではなく、「患者さんが自ら考え、行動できるように導く」
という姿勢です。質問を促し、患者さんの不安や疑問に耳を傾け、共感的な態度で接することが、信頼関係を築く第一歩となります👣
2.対医師・対医療従事者 – チームの統率役として
医療チームを円滑に動かすためには、医師のリーダーシップが不可欠です。
📌 カンファレンスでのファシリテーション: カンファレンスで、医師が一方的に指示を出すのではなく、看護師やセラピストの意見を積極的に引き出す👂「何か困っていることはありますか?」と問いかけ、チーム全体で情報を共有し、最適な治療方針を決定する。
📌 インシデント・アクシデント時の対応: 医療事故が発生した際、冷静に状況を把握し、チームメンバーの安全を確保しつつ、原因究明と再発防止策をリードする📢非難するのではなく、チーム全員で学び、改善していく姿勢を示す🚩
📌 後輩指導: 研修医や後輩医師に対し、ただ知識を教え込むのではなく、「なぜそうするのか?」という理由や、思考プロセスを共有する。問いかけを通じて、自律的に思考する力を育む🧠
⚠️リーダーシップは、決して「カリスマ性」や「威圧感」を意味するものではありません⚠️
「チームメンバーが安心して、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境を作る力」
こそが、真のリーダーシップです。
3.対社会 – 地域の健康を守る医師して
医療の役割は、病気を治すことだけではありません❌病気を未然に防ぎ、社会全体の健康レベルを底上げすることも重要なミッションです🎯この役割を担うのが、社会全体に向けた「健康教育」です。ここでも教育スキルが極めて重要になってきます。
📌 メディアでの情報発信: インターネットやSNSを通じて、医学的に正しい情報を、一般の人にもわかりやすい言葉で発信する🌐
📌 地域での講演活動: 高齢者向けの健康講座や、学校での性教育、生活習慣病予防の講演会などを通じて、地域住民の健康リテラシー向上に貢献する👆
📌 予防医療の普及: 「特定健診」や「がん検診」の重要性を啓発し、早期発見・早期治療の意識を高める🩺
医師の言葉には大きな影響力があります。その影響力を活かし、社会全体の健康を守るために、積極的な教育活動を行うことは、未来の医師に求められる重要な役割です⭐
今からできること~実践的アドバイス~

「ここまで読んできて、リーダーシップも教育スキルも必要なことは分かったけど、どうやって身につければいいの?」そう思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事実、これらは座学で身につくものではありません❌
大切なのは、「誰かのために動く」という経験の中で、失敗を恐れずにフィードバックを受け取ることです📩そこでここでは、単なる「アルバイトをする」「サークルの役員になる」といったありきたりなアドバイスではなく、皆さんが今日から始められる具体的なアクションをいくつか提案させて頂きます⇓⇓⇓⇓
【リーダーシップ強化編】
リーダーシップは「統率力」だけではありません❌「チームを機能させる力」です。チームを裏から支える経験が、真のリーダーシップを育みます😮😮
📒「会議の議事録係」に徹する📒
アクション: チームやグループワークで、議事録係に徹する
鍛えられるスキル: 目標設定力、ファシリテーション力
チームの議論を「誰が」「何を」「なぜ」決めたのか、そして「次のアクション」は何かを第三者視点で客観的に整理し、記録します。これにより、チームの議論の迷走を防ぎ、常に目標地点へ再設定する能力が劇的に向上します👆完成した議事録が「これがあれば大丈夫」とチームを安心させる力こそ、真のリーダーシップです✨
⛓️💥「チーム内フィードバックのハブ」になる⛓️💥
アクション: チームメンバー間の小さな不満や、建設的なフィードバックを集約し、感情を排した「事実ベースの課題」としてチーム全体に共有する
鍛えられるスキル: 問題解決力、コミュニケーション力
チーム内の衝突は感情が絡むことがほとんどです💦そこで皆さんは、メンバーの要望や意見を客観的な事実として集約・共有し、チームの不協和音を解決に導く冷静な仲介役としての能力が身につきます👍
🪜「 専門性の橋渡し役 」として貢献する🪜
アクション: 知識背景や優先順位が異なる複数の関係者が関わるプロジェクトにおいて、各メンバーの意見や専門用語を、全体が理解できるように再構築し、会議や文書を通じて共有する役割を担う✍
鍛えられるスキル: コミュニケーション力、目標設定力
医療は、医師、看護師、薬剤師など、それぞれが異なる専門知識と職務上の優先順位を持つ多職種連携で成り立っています🎨この役割を担うことで、異なる専門領域を越えて情報を整理し、すべての関係者が共通の目的意識に向かって動けるよう導く能力を養成します。これは将来、医療チーム全体を円滑に機能させる上で不可欠な基礎能力となります🤗
【教育スキル強化編】
教育とは、「相手が自ら変わるためのヒントを与えること」です。医師がすべてを決める時代は終わりました🍂
相手の価値観を尊重し、行動を促す「対話力」を磨きましょう✨
🎤「複雑な医学概念の1分プレゼン」を習慣化する🎤
アクション: 毎日、一つ複雑な医学用語を選び、医学知識ゼロの人に「なぜそれが大切なのか」を交えて1分で説明してみる
鍛えられるスキル: 疾患教育スキル、情報の本質理解力
専門用語を一切使わず、誰でもわかる例え話や比喩を使って説明する訓練です🤗これは、患者さんに疾患を理解してもらうための基礎練習となり、さらに複雑な情報を自分の中で整理し、本質を掴むという自己学習の効率も飛躍的に向上します👆
📢「行動変容を促す声かけ」を生活で試す📢
アクション: 身近な人(ダイエットしたい友人、勉強を習慣化したい後輩など)に対し、具体的な「スモールステップ」のアドバイスだけを行い、その後の変化を観察する🔍
鍛えられるスキル: 行動変容の支援、モチベーション喚起
ただ「頑張れ」と言うのではなく、「まず今日の夜ご飯のお米を半分にしてみよう」「教科書をまず5ページだけ開いてみよう」といった、失敗しにくい具体的な行動を提示し、成功体験を積ませることに注力します👀このスキルは、生活習慣病の患者さんを指導する際に最も不可欠な力になります。
🧠相手理解に基づいた説明力のトレーニング🧠
アクション: 難解な医学論文やニュース記事を読み、それを「小学生向け」「ビジネスパーソン向け」「高齢者向け」の3つの異なるトーンと語彙で要約し、ブログやSNSの下書きとして保存してみる📜
鍛えられるスキル: 情報発信スキル、多様な患者理解。
伝える相手によって、何を強調すべきか、どんな言葉を使うべきかを意識的に変える訓練です。これは、将来メディアで健康情報を発信する際や、地域の講演会で話す際に、聴衆の心に響くメッセージを作成する土台となります🪵
「医学生道場」は、未来を担う医学生の皆様に、最適な学びの場を提供しています。
医学生道場とは、医学生向けの個別指導塾で、医学部の進級試験、CBT試験、OSCE対策、卒業試験、医師国家試験対策などを専門にサポートしています。医学教育に精通した医師が講師となり、マンツーマンの指導を行うのが特徴です!
📘おすすめの一冊
今回強調した「リーダーシップ」と「教育スキル」は、「失敗から学ぶ力」と表裏一体です😮医療はミスが許されない現場ですが、人間である以上、失敗は避けられません。大切なのは、それを隠さず、チームで共有し、改善に繋げることです💡
そこで、この重要な学習姿勢を深く理解するために、ぜひ読んでいただきたいのがこの一冊です🤗
『失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織』 マシュー・サイド (著)
この本をおすすめする理由:
この書籍は、医療業界と、対照的に失敗を学習に活かす「航空業界」などの事例を対比させながら、失敗を「データ」として捉え、組織全体の成長に変えるメカニズムを解き明かします✍
失敗を隠蔽する文化から脱却し、学習し続ける組織をリードするために、必読の一冊です📚
おわりに
医学の学びは、膨大な知識と技術の習得だけではありません❌それは、人々を助け、社会に貢献するための人間力を磨くプロセスでもあります🙆
リーダーシップと教育スキルは、未来の医師が持つべき「人間力」「スキル」です。これらはすぐに身につくものではなく、日々の意識と小さな実践の積み重ねによって育まれていきます📚
医学生の皆さんには、ぜひ、医学知識を学ぶことと同じくらい、これらのスキルを意識して学生生活を送ってほしいと思います🤗
患者さんとの対話、仲間との協力、そして自分自身の学びのすべてが、将来の皆さんを形作る貴重な経験となることでしょう✨
❓ FAQ(よくある質問) ❓
Q1. リーダーシップって、結局は「空気を読んで、目立たないように動く」ってこと?
A: 空気を読むのは大事ですが、真のリーダーシップは「空気を変える力」です。「議事録係」に徹するのは、議論が白熱して迷走した時に、冷静にゴールを再設定するためです。ただ見守るのではなく、いざという時にチームを正しい方向に動かす力を鍛えていると捉えてください。
Q2. 難しい病気を専門用語なしで説明すると、患者さんをバカにしてると思われませんか?
A: それは全くの誤解です。逆に、相手の理解度に合わせた言葉を選ぶのは、プロとしての誠実さです。専門用語を並べるのは簡単ですが、患者さんの不安を減らし、「自分が治療の主役だ」と思って参加してもらうには、彼らの生活に響く言葉を選ばなければなりません。
Q3: 慢性疾患の患者さんに「食事に気を付けて」じゃダメで、「スモールステップ」が大事とのことですが、例えば、友達にダイエットを勧める時、どんな声かけが効果的ですか?
A: 「頑張って痩せて!」は一番言ってはいけない言葉です! それは努力の押し付けになってしまいます。重要なのは「挫折しにくい、極めて小さな成功体験」を提案すること。「明日から毎日1時間運動」ではなく、「まず今日、帰りのエスカレーターを使わずに階段を上ってみませんか?」というように、小さな一歩で「自分にもできた!」という自信に繋げられることが、患者さんの行動を変えるための鍵になります。