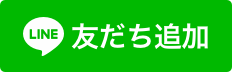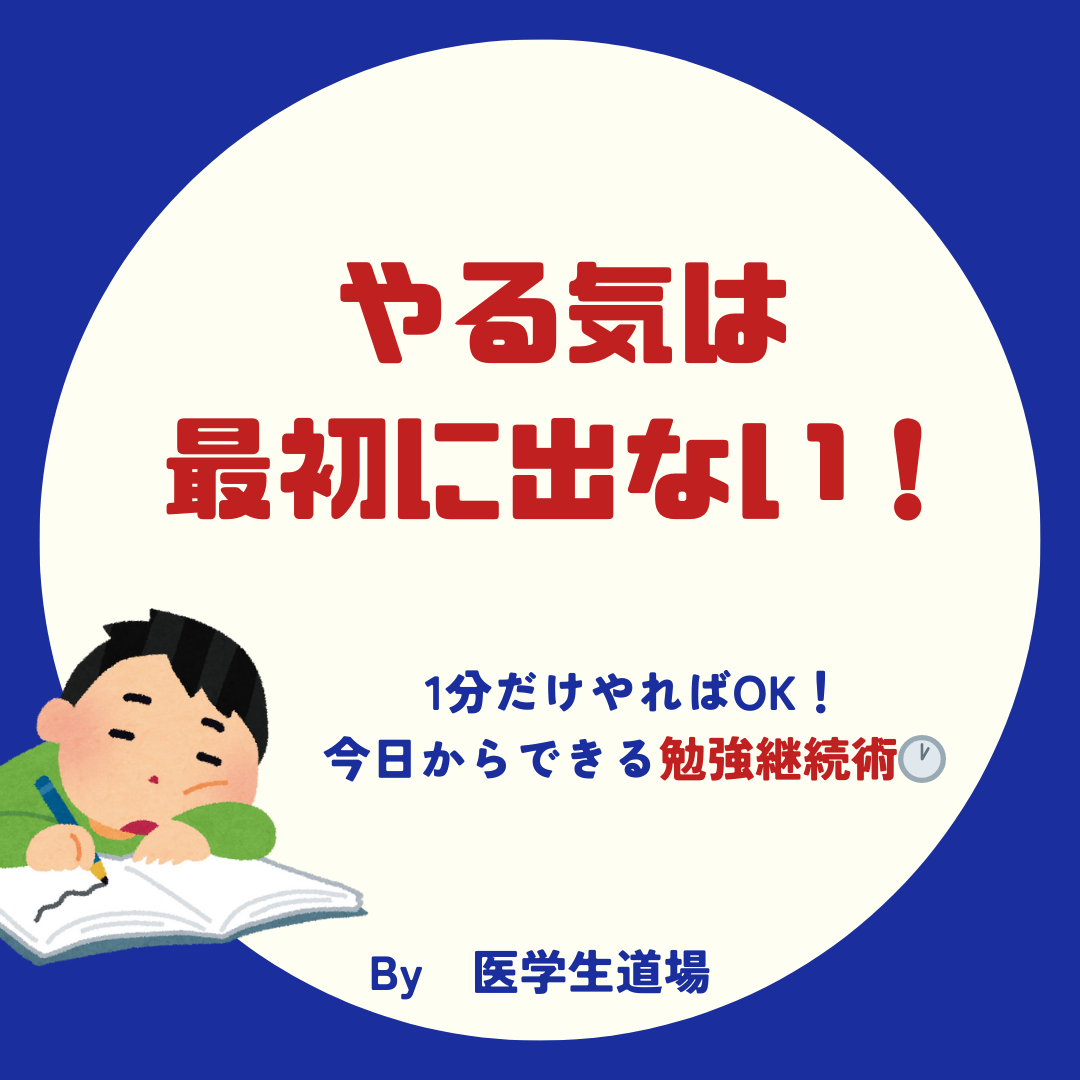目次
✓このブログのポイント
☞医学生にこそ「教養」が必要な理由
☞アートと文学が教養を育てる💡
☞教養を育むことで最強の医師に!
■ 筆者紹介
著者名:シマダ
所属:早慶三年生、医学生道場の学生アルバイト
資格・経歴:年間40本以上観劇、毎期多数ドラマ視聴、FP3級、証券外務員一種
アピールポイント、自己紹介:年間様々な舞台を観劇したりドラマ、アニメ、映画などを視聴しており、皆さんの好みに合わせたおすすめ作品をご紹介することができます💡
また、FPや証券外務員一種の資格取得の際に学んだ知識を生かして金融の豆知識をお伝えしたり、早慶に通う現役大学生として学習方法のアドバイスや大学生活の今をお届けします!
過去のブログ➡【医学生道場】忙しい日常やCBTの息抜きに! おすすめの2025年夏アニメ、【完全ガイド】FP3級の勉強法と対策まとめ 初心者でも合格できる効率的な方法とおすすめの理由、【医学生道場】医学生のための解剖学勉強ガイド:基礎から実践まで徹底解説!など
📞 お問い合わせ・お申し込みはこちら
📍無料相談実施中
- 期間:随時受付(水木曜日をのぞく13ー20時まで ※ただし社内休暇期間をのぞく)
- 特典:個別相談・学習計画作成
📍連絡先
- 電話:0422-26-7222
- メール:https://igakuseidojo.com/official_2025/contact/
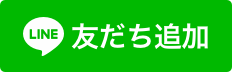
■ はじめに:医学だけを学ぶ人になっていませんか?
「医学部の勉強は終わりがない」というのは、医学部の皆さんなら身をもって体感していることなのではないでしょうか。
解剖、薬理、生理、病理など、一つの科目を学ぶだけでも膨大な知識を覚えなければならず、テストや実習に追われる日々。
医学生の多くが、「勉強以外のことに使う時間なんてないし、あったとしてもほかのことに時間を使うのは罪悪感がある」と感じているかもしれません💦

でも、ふと立ち止まって考えてみてください。あなたが将来、医師として患者さんと向き合うとき、必要なのは医学の知識だけではありません。
患者さんの言葉の裏側を感じ取る感性や、人の人生を想像し優しく寄り添う想像力。さらに、自分自身の内的な豊かさなど、実は医師に求められるスキルは医学知識以外のものも多いのです💡
それらを育むのは、教科書の中ではなく、アート・音楽・文学といった「教養の世界」📚このブログは、そんな「教養の世界」に皆さんが触れるきっかけとなるようなブログです。ぜひ一緒に「教養の世界」を覗いてみましょう!
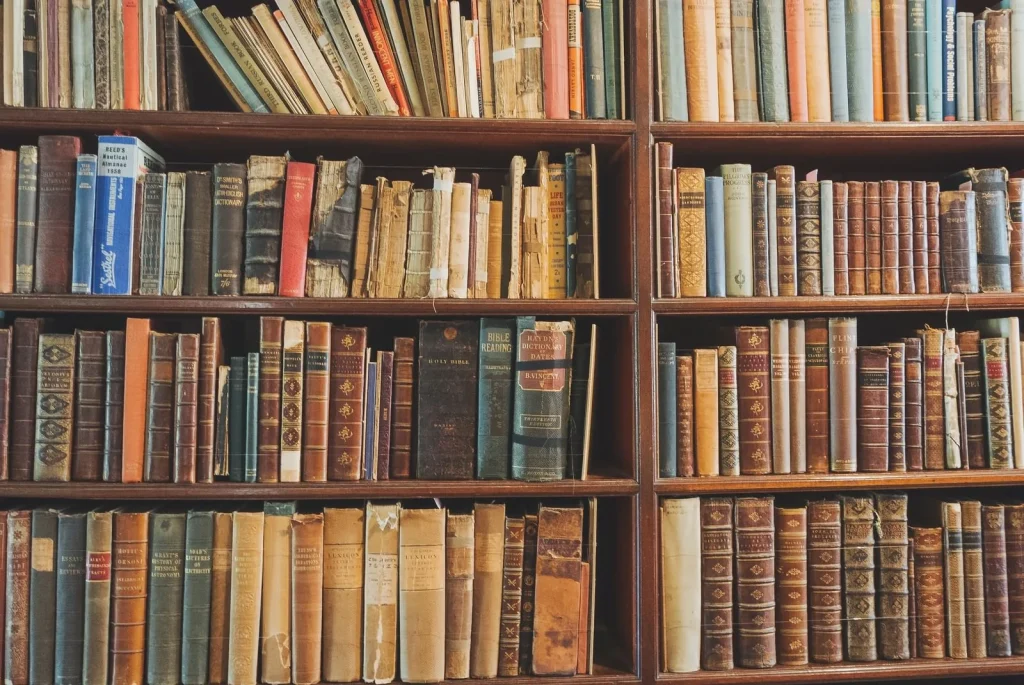
第1章:なぜ医学生に「教養」が必要なのか
まずは、医学に携わる医学生、そして医者に「教養」が必要になる理由について、一緒に考えてみましょう👀
医学生といえば、一に勉強、二に勉強な勉強漬けの日々が当たり前ではないでしょうか。あなたは、いつから「勉強すること」が日常になりましたか?
高校時代の受験勉強、医学部に入学した後の医学知識の暗記、テスト前の徹夜など、勉強しなければならない場面が容赦なく襲い掛かってくるのが現状。気づけば一日が「覚える・解く・整理する」で終わってしまうことも多いのではないでしょうか💦
もちろんそれは、医師になるために必要な努力です!誰よりも努力してここまで来た医学生の皆さんは、すでに立派な医療人です✨

でも、心のどこかで「勉強ばかりで、自分の人間らしさが薄れている気がする」と感じている人も多いのではないでしょうか。
実はその感覚は、まったく間違っていません。医学部のカリキュラムは、圧倒的に「科学」に寄っているものだからです📚
人体を分解して理解し、データを分析して判断する、そのような知識を身に付けていく過程で、いつの間にか「人を診る」よりも「病を診る」視点が強くなってしまっているからです。
もちろん、「病を診る」という姿勢や医学の知識を習得することは必要不可欠。しかし実際の臨床の現場で出会う患者さんたちは、教科書のように単純ではありません。
同じ病気でも、家族との関係性やその人の生い立ち、学歴や仕事、おかれている環境など、患者さん一人一人としっかり向き合っていく必要があります💡
この「人を診る」ために必要となる力。それこそが、「教養」なんです✨
📝教養は「他人の人生を想像する力」
「教養」と聞くと、難しい本を読んだり、歴史を語ったり、膨大な知識を披露するようなイメージがあるかもしれません。
しかし教養の本質は、そのような表面的なものとは少し違ったものではないかと筆者は考えています!
教養に対して様々な考え方、イメージをそれぞれが持っていると思いますが、筆者が思う教養とは、「様々な世界の知識を取り入れ、他人の人生を想像することができる力」です📝

小説を読めば、登場人物の痛みや後悔を追体験できます。音楽を聴けば、言葉では説明することのできない感情を知ることができます。絵画を見れば、画家の人生や描かれた人の想いに思いを馳せることができますよね。
そうやって、「教養を養う=他人の人生を想像する練習」を積むことが、臨床の現場で患者さんと向き合うときの原点になるはずです✨
あなたが将来、医者という立場で患者さんと向き合った際に悩むことも多くなるでしょう。
その答えを探すヒントは医学書ではなく、もしかしたらアートや文学の世界の中にあるかもしれません!
📝教養のない医師は冷たく見えることも
医学は正確さと知識がとても重要です。けれど、正しさだけでは患者さんの心は動かせません。
どんなに理屈が通っていても、患者さんが「この先生、冷たいな」「本当に自分のことを考えてくれているのかな」と感じた瞬間、信頼関係は崩れてしまいます。そして信頼を失えば、治療の成功率も下がります😿
「正しいことを言う」ことも大切ですが、「伝わる言葉を選べる」ようになることは人生において重要です。そんな「教養の力」は一朝一夕では身につきません!
日常の中で、いろんな人の感情に触れ、考える習慣を日ごろから養うことが大切です✨
📝科学だけでは、人の痛みは測れない
医学の本質は、「人を治す」ことはもちろんのこと、「人を支える」ことにあります。
そのためには、向き合う人間の喜びや悲しみ、孤独、希望といった「奥底の感情」を理解できる医師である必要があります🔍
医学は病気を理解するために必要な知識であり、それと同時に教養は、人間を理解するために必要不可欠なものです。
どちらか一方だけでは、真の意味で患者さんに向き合うことはできませんよね!
医学生である今だからこそ、「教養」というもう一つの大切な知識を学び始めてほしいのです💡

📝教養を身に付けるための一歩は、少し立ち止まること
教養を身につける第一歩のためには、何か大それたことをする必要はありません!
スマホを置いて静かに音楽を聴く、小説を一章だけ読んでみる、美術館に立ち寄って一枚の絵をじっくりと見るなど、そうした「ゆっくりと立ち止まる時間」が、教養を身に付ける第一歩になります✨
勉強に追われる日々の中でこそ、少しだけゆったりとしたの世界に触れる機会を持ってみてください!
それが、未来の医師のあなたを「知識だけに偏った冷血な医師」ではなく、「人の痛みを感じ取って寄り添うことができる医師」にしてくれるはずです。
第2章:アートが教えてくれる「観察」と「想像」
「観察力を鍛えなさい」 医学生なら、必ず一度はこの言葉を耳にしたことがあるはずです。 診察実習でのフィジカルチェック、画像読影、検査データの解釈など、医学の世界では、「ものごとを正確に観察すること」が非常に重要です。
けれど私たちは「見ているつもり」で、実はしっかりとは「見えていない」ことが多いもの。アートは、「観察力」を鍛え、応用する方法をその姿をもって教えてくれる最適な教材といえるでしょう✨
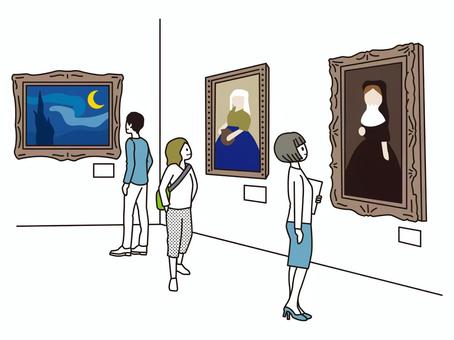
📝 観察とは、「見ること」ではなく「気づくこと」
たとえば、美術館で一枚の絵の前に立っている自分を思い浮かべてみてください💭
最初は「綺麗」「暗い」「不思議」といった印象だけが浮かんでくるかも。
でも、じっと見ているうちに、「なぜこの人物は笑っているんだろう」「光が当たっているのはどの部分だろうか」「この背景の色はどんな感情を表しているんだろう」
そんな問いが次々と湧いてくるはずです!
この「問い」が生まれる瞬間こそ、「見ること」から「気づくこと」に変わる瞬間です✨
医学でも同じことがいえます。患者さんの顔色や声のトーン、沈黙の長さといった一見何気ないサインの中に、身体の不調や心の痛みが隠れているケースが多くあります。
つまり、アートを観る練習とは、「人を診る練習」でもあるということです👀
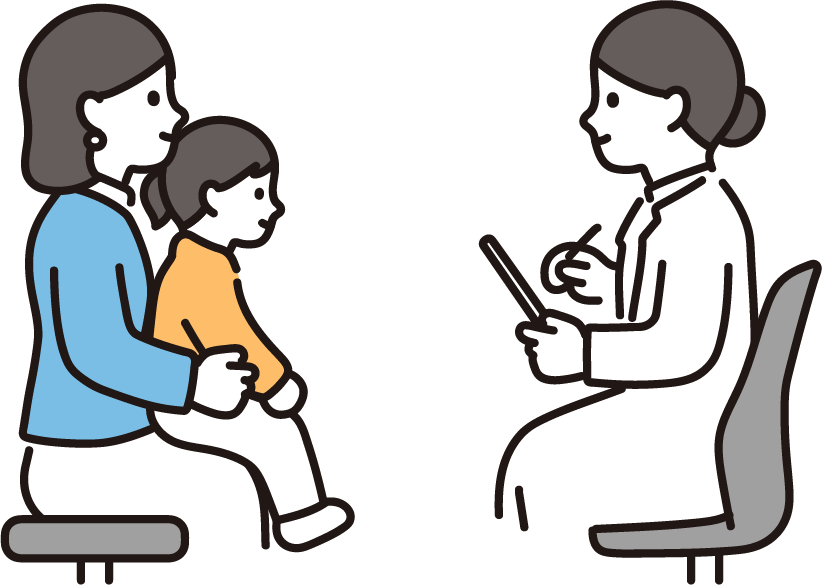
📝美術教育を導入する医科大学が増えている理由
実は近年、欧米の医科大学では「アート×医学」の授業が増えており、医学生が美術館に出向き、絵画をじっくり観察する授業が実際に行われています。
日本においても、岡山大学が医師として必要な診断力や患者に寄り添う心を育むことを目的として「ビジュアルアート教育」を行い、注目されています👀
このような医学教育にアートを導入する試みは、2000年前後から欧米で発達してきたもの。米エール大での研究によれば、「ビジュアルアート教育」を受けた学生は受けていない学生に比べ高い診断能力が示された、という分析もされているなど、美術教育が医学生にもたらす影響はとても大きいといえるでしょう✨
「ビジュアルアート教育」にて行われる、それぞれの意見を述べそれについてプレゼンや議論を行うというトレーニングは、患者さんに対するヒアリング能力の向上にもつながります!
「患者さんが語らない隠された何か」を感じ取る力、それは医師にとって必須の真の観察力と言えるでしょう。
📝想像力は診察でも生かせる
診察室では、患者が黙り込む瞬間があります。言葉にならない感情や、「これは口にしてもいいのかな」という迷い、深層心理に潜む恐れなど、その沈黙をどう受け止めるかは、医師の力量に関わります🔍

アートを観る経験は、そうした「沈黙と向き合う訓練」にもなるでしょう!
絵画も音楽も、見方や解釈に正解はないですし、「これ!」といった明確な答えを与えてはくれません。「これはどういう意味か?」と考え続ける中で、私たちは「わからないことに対して考え続ける思考力」を養うことができるのです✨
医学は、「わからないこと」を前提とする学問でもあるといえるでしょう。人の体も心も、たとえ自分自身であっても完全には理解することは難しいもの。だからこそ、想像力が必要になるのです💡
📝 医学生におすすめの「アートとの関わり方」
では、忙しい医学生がどうやってアートに触れればいいのでしょうか?なんだか小難しい知識や特別な資格が必要な気がしてしまいますよね💦
「アートを観る」ために、特別なセンスや知識は必要ありません。むしろ大切なのは、「じっくりと作品と向き合う気持ちと想像力」です!
たとえば次のような小さなことから始めてみることがおすすめです👇
✓授業帰りに、美術館の一室に立ち寄る。
→ 作品に対する知識は必要ありません!10分でもいいので、一枚の絵の前で立ち止まり想像力を膨らませる習慣をつけましょう。
✓医学書の横に、写真集や詩集を置く。
→ 普段触れている世界とは異なる世界のものに触れることで、思考の幅が広がります。
✓SNSではなく現物を観る
→ スマホ越しの画像では伝わらない色・質感・空気を感じることは非常に重要な経験です。
✓観察記録を残す。
→ 「この作品を見て何を感じたか」をノートに書くだけで、その時の感情を記録しておくことができるとともに、感情を言語化するための表現力も磨かれます。
これらは一見、医学部の勉強とは関係なさそうに見えますよね。でも、実はすべて「診る力」「聞く力」「伝える力」を養うトレーニングになります✨

第3章:文学が育てる「共感」と「言葉の力」
アートが「観察と想像の力」を育てるのだとすれば、文学は「共感と表現の力」を育ててくれる重要な教材です📚
人を診る仕事において、「言葉」は医師にとって最大の武器ともいえるでしょう。けれど私たちは、医学教育どころか義務教育の中で知識としての言葉ではなく、「人に伝えるための言葉」を深く学ぶ機会がほとんどありませんよね💦。
患者の心に真に届く言葉を選ぶ練習は、実はほとんどしていないのです。

✓ 「正しい説明」より「伝わる言葉」を
たとえば、患者に病気を伝えるときを想像してみましょう。
「○○という疾患で、今後は化学療法を検討します」というような、事実を淡々と伝える説明は模範的な回答といえるでしょう。でも、病気を患い不安を抱える患者さんの心に響く言葉ではないですよね。
相手が感じる不安や怒り、孤独を想像し、その上で「どのように伝えるか」を考える、そんな「相手に寄り添う」力を育ててくれるのが、文学なのです✨

小説や詩の中には、人が言語化できない思いを、丁寧に、慎重に、でも確実に表す表現がたっぷりと詰まっています!
医療の現場でも、同じことが求められます。相手の心情を察するとともに、ただ説明するだけでは伝わらない思いを的確な言葉選びで支える力。それが、文学が育ててくれる感性なのです💡
✓文学がくれる「他者の人生を生きる時間」
文学を読むということは、自分以外の人生をしばらく借りて生きてみることと同義です。「自分が物語の主人公になって物語に入り込んだような感覚」を味わったことのある人は多いのではないでしょうか。
貧困に苦しむ人や差別を受ける人、病気と闘う人、孤独に苛まれる人など、自分は感じたことのない苦しみを小説は言語化して私たちに伝えてくれます。小説を通して、私たちはその「他人の痛み」の中に入り込むという体験ができるのです📚
この「他人の痛み」の中に入り込むという体験こそ、「患者さんに共感する」力の基礎になります!
患者さんの話を聞くときに、「この人は、どうしてこんな言葉を選んだのだろう」「この沈黙の裏側にはどんな気持ちが隠れているんだろう」 と考えることができるかどうか、その力を育てることができるのが「文学」という教養なのです✨
✓「読む」ことは「書く」ことに通じる
文学に触れると、自然と「書きたくなる」瞬間が訪れます。それは長編の小説を書く、というような話ではなく、自身の感情や気持ちを言語化して残しておきたくなるということ。その手段は日記でも、短いメモでもかまいません📝
患者さんにかけた一言や、今日の診察で感じた戸惑い、自分の中で引っかかった小さな不安などのネガティブなことから、患者さんからもらった嬉しい言葉、治療がうまくいった際の高揚感など、患者さんと向き合う中で生まれる感情は様々。
それを言葉にして残すことは、自分を理解するための第一歩にもなります!
近年の医療現場では「ナラティブ・メディスン(物語医療)」という考え方が広がっています。これは、患者と医師が互いの「物語」を共有しながら医療を進めるというもの。
つまり、「聴く」と「語る」両方の力が求められるのです💡

文学を読むことは「聴く力」を、書くことは「語る力」を育てるために非常に有効な手段であるといえるでしょう!
そのどちらも、治療やカウンセリング、患者さんやその家族への説明の場面で確実に生きてくるスキルです✨
✓「言葉の温度」を感じ取る感性を磨こう
医師の言葉には重みがあります。もちろんその一言が患者さんの希望になることもあれば、逆に絶望を深めてしまうという事態にもなりかねない、非常にデリケートなものです。
たとえば、治療の施しようがないと伝える際に、「あなたにもうできることはありません」と告げなければならない場面を想像してみましょう。
その事実のみを淡々と伝えるのか、「これから一緒に考えていきましょう」と添えて患者さんに寄り添うことができるのか。その小さくも大きな違いを生むのが、言葉の温度です!

文学に触れることで、「言葉の温度」を感じ取る感性が磨かれます✨
同じ言葉でも、使い方によって人を傷つけたり、逆に寄り添うことができます。その微妙なニュアンスを学ぶことが、医師として必要な表現力を育てるのです!
✓ 医学生におすすめの文学作品
文学に触れるといっても、いきなり難解な長編小説などを読む必要はありません!
まずは、医学部で勉強をする皆さんの身近にある「医療」をテーマにした医療小説に手を伸ばしてみることをお勧めします✨
医療問題を扱ったスリリングな作品から思わず泣ける感動作まで、筆者厳選の医療小説をまとめた記事を貼っておくので、ぜひ一冊目の参考にしてみてくださいね👀
☞筆者おすすめの医療小説はこちら📚
💬FAQ:よくある質問
Q1. 医学生がアートや文学に時間を使うのは無駄ではありませんか?
A. いいえ、むしろ医学生にとって意味のある学びです!アートや文学は「観察力」「共感力」「想像力」などのスキルを養い、診察やコミュニケーションの質を高めます。
医学の知識だけでなく、「人を診る目」を磨くために必要な教養です🔍
Q2. 教養や感性を磨くには、具体的に何から始めればいいですか?
A. いきなり難解な本や美術館巡りをする必要はありません!おすすめは「小説を月1冊読む」「映画を観て感想をメモ」「美術展に年1回行く」など。コツは気負わず、日常の中に教養に触れる機会を小さく取り入れることです💡
Q3. 医学の勉強だけで精一杯。どうやって時間を作ればいいですか?
A. ポイントは「勉強の延長で楽しむ」こと📝たとえば、医学生の皆さんに身近な病気や医療をテーマにした文学を読むと、学問と感性の両方を同時に磨くことができて一石二鳥!
「息抜きの時間」を少しだけ「教養に触れる時間」に変えるとが継続しやすいです。
■ おわりに:「教養のある医師」は、最強の医師!
「勉強マシーン」で終わらずに教養に触れることができる医学生は、 医学の外の世界からも積極的に学び、自分だけの感性を育てていくことができる人です!
様々な仕事がAIにとってかわられると危惧される近年において、医学知識はAIでも代替できますが、人の心を理解する力や感情に共感する力、言葉の温度を感じられる力は、決してAIにはとってかわることのできない、人間だけが持つ医療に必要不可欠な力です✨
だからこそ、忙しい医学生生活の中でもほんの少しでいいので、教養に触れることで「自分の心が動き感性を育む時間」を持つことをおすすめします!
一枚の絵をじっくり見てみたり、気になった小説を手に取ってみたり。もっと身近なところでは好きな音楽を聴いたり、映画やドラマを視聴してみるなど、「教養に触れて自分の心を動かす瞬間」は日常のすぐそばに隠れているものです👀
そんな日常の小さな積み重ねが、将来患者さんの人生に寄り添う力に必ずなるはずです!
■ 最後に
このブログを執筆したスタッフが所属している医学生道場では、医学部に在学する医学生を対象とした個別指導を行っています。身近に医学部の学習や試験についてつまづいていたり、誰かに相談したいと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
そのような方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に医学生道場にご相談ください!
📞 お問い合わせ・お申し込みはこちら
📍無料相談実施中
- 期間:随時受付(水木曜日をのぞく13ー20時まで ※ただし社内休暇期間をのぞく)
- 特典:個別相談・学習計画作成
📍連絡先
- 電話:0422-26-7222
- メール:https://igakuseidojo.com/official_2025/contact/