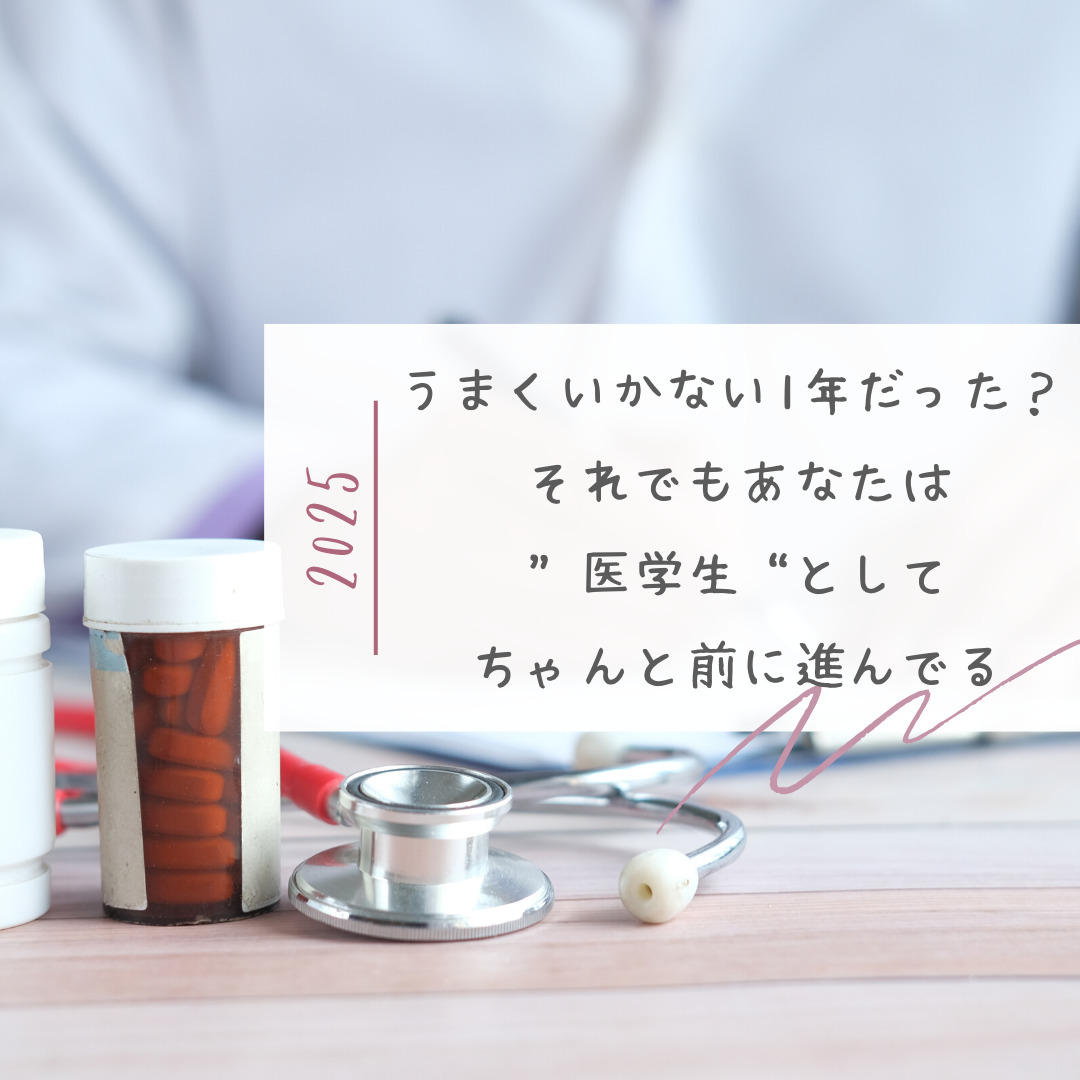目次
著者紹介・概要
🖊著者紹介
竹田美穂 (都内私立医学部医学科4年生)
3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次には大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。
留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!
留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!
【過去に著したブログ】
【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】
【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】
👉 学校生活のことや日常のことなど、どんな不安や悩み、質問もOK!24時間メッセージ受付中!

🖊今回の概要
・医学部生活の中で挫折を経験した筆者が、再起の過程で得た“5つの学び”をランキング形式で紹介する。
・留年・浪人経験のある筆者だからこそ語れる“リアルで実用的な学び”が中心。
・医学生にありがちな落とし穴を可視化。
はじめに
こんにちは!気づけば、今年も残り僅かになりました。
皆さんは、この一年をどのように過ごしたでしょうか?
さて、来年からは心機一転。来年こそ、成績を伸ばしたい。そう決意している人も多いと思います。
そこで今回は、一度挫折を経験した私が、その過程で学んだことをランキング形式でご紹介します。
ぜひこの記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
医学生道場では、全国の医学生を応援しています。
勉強の不安やメンタル面で悩みがある方は、
ぜひ公式LINEへご相談ください。
24時間いつでも無料相談受け付け中です。
1位:丸暗記よりも理解を大切にする
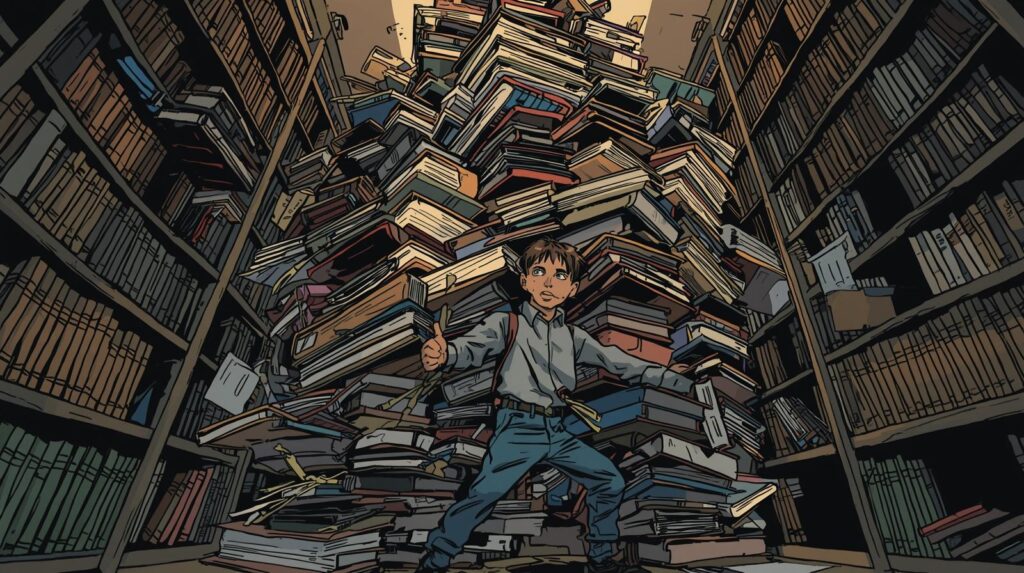
結論から言うと、医学部の勉強は暗記より理解が大事です。
入学後しばらくの私は、「医学部=暗記量が勝負」と思い込み、基礎医学の難しい部分を誰にも質問せず、そのまま丸暗記で進めていました。
しかし当然、暗記だけでは量が多すぎて、覚えられるはずもありません。
記述問題も書けず、再試が続き、私は留年してしまいました。
翌年、基礎医学を再度一から学びなおしましたが、まだ医学部の勉強法についてよくわかっておらず、理解があいまいなままでした。
その後臨床科目がはじまりましたが、より一層ついていくことが困難になってしまいました。
臨床は、基礎医学の知識を土台にして進んでいくからです。
だからこそ、なぜこうなるのか、どうしてそうなるのか、ということを常に考える姿勢が重要です。
仕組みを理解すると、覚える量が減り、知識がつながり、試験でも応用が利くようになります。
2位:過去問依存は危険。レジュメ依存も危険。
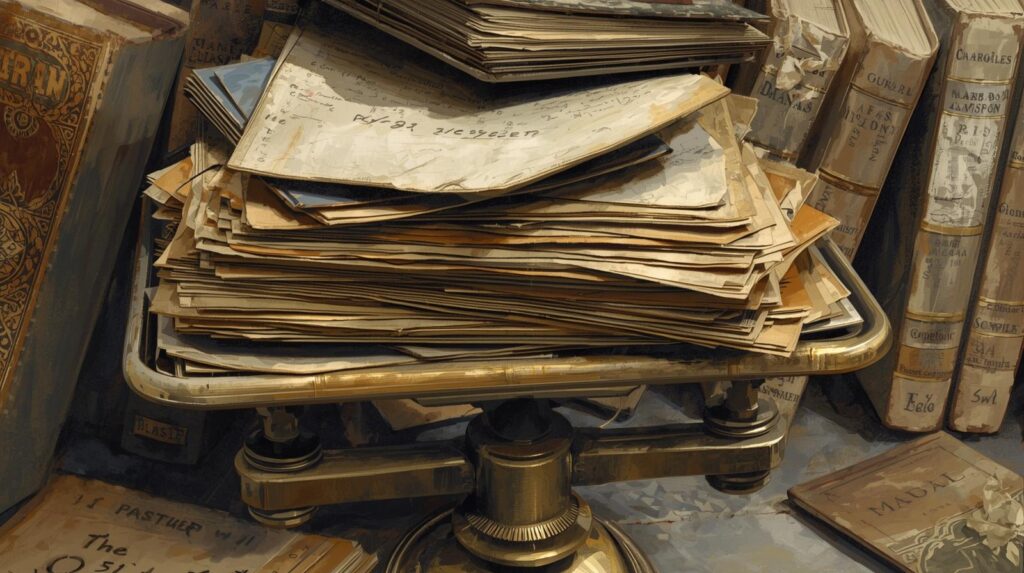
やみくもに過去問題を解いていても、試験本番で少し問い方を変えられるだけで急に解けなくなることがあります。
パターンに慣れても、本質がわかっていないと応用が効きません。
また逆に、レジュメばかり勉強していても、試験範囲の量が多すぎて、時間が足りなくなります。
本番の出題傾向もつかめません。
大切なのは、どちらか一方だけではなく、どちらもうまく両立させることです。
まずはレジュメと照らし合わせながら過去問を解きます。
すると、「先生がどこを重視しているのか」が見えてきます。
その後、もう一度過去問を解きなおします。
解けた問題にはチェックを付け、解けなかった問題だけを2週目で解きましょう。
最終的に間違えた問題も含め全部解ける状態になれば大丈夫です。
CBTや国家試験も同様です。
やみくもにQBやモントレを解きまくるだけでは、成績は伸びません。
講義動画やイヤーノート、レビューブックなどの参考書などを用いて、周辺知識もきちんと頭に入れることが大切です。
3位:情報共有しない孤独勉強は圧倒的に不利

一人で抱え込む勉強は、圧倒的に不利です。
1年生の時、私は試験前に友達と勉強会を開きました。
私としては、物理選択であったこともあり、基礎がほぼゼロの状態であったため、その勉強会で一から勉強するつもりでした。
しかし、その時点で友達は講義内容をある程度理解していて、互いにわからないところを聞きあっていました。
私は話についていけず、会話の内容も理解できませんでした。
ここで「なにそれ!?おしえて!」と教えを乞うことができたらよかったのですが、「邪魔をしたくない」という気持ちが強く、その場ではひたすら過去問だけを解き続けました。
案の定、試験は落ちることになります。
再試の勉強中、友達の一人が私の勉強をのぞき見して、「そこ試験範囲外だよ」と言いました。
この時、出題情報を何も知らずに、無駄な勉強をしていたということに気づき、情報共有の重要性を痛感しました。
医学部は範囲が広く、時間も限られています。
試験に出るところ、出ないところはもちろん、
友達がつまずいた部分、理解しやすい説明など。
これらを共有するだけで、勉強効率が大きく変わります。
知識も情報も、一人で集めようとすると限界があります。
クラスメイトや友達と積極的に会話して、必要な情報を互いに補い合うことが最短ルートです。
4位:まとめノートに時間をかけすぎると落ちる
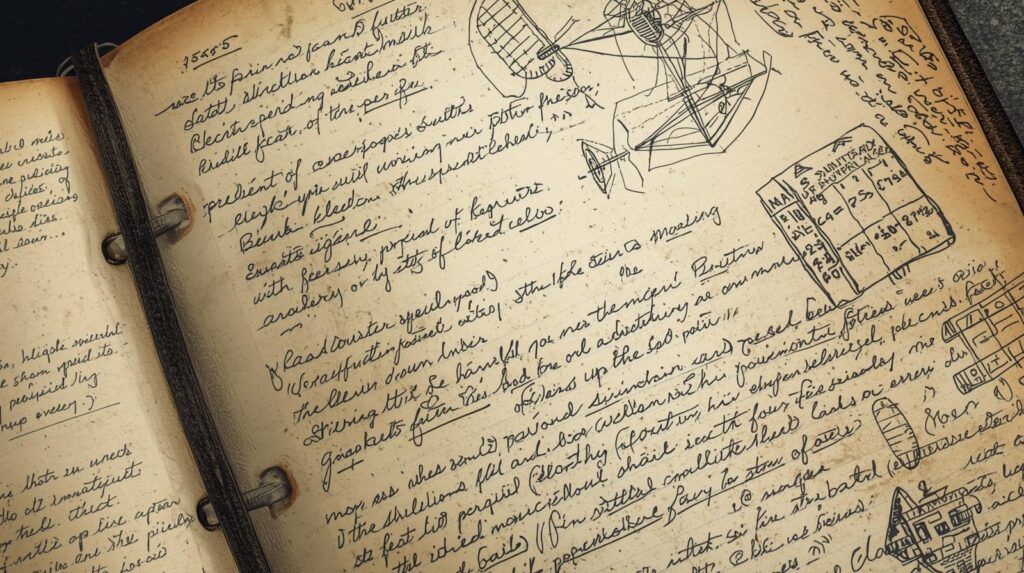
まとめノートつくりに時間をかけすぎると、落ちます。
私は2年生の時まで、受験生時代の癖でまとめノートを作成していました。
公式や化学式を整理し、試験直前に見返すことで大変役に立った経験があったためです。
しかし、医学部の試験は受験とは別物でした。
まず、ノート作りに大量の時間が奪われます。
そして、まとめただけでは知識は定着しません。
その結果、過去問や暗記に使うべき時間がどんどん失われました。
医学部の勉強は範囲が広く、時間との勝負です。
まとめノートの作成に時間を使うほど他の勉強ができなくなり、大きなロスになります。
覚えにくい部分は、レジュメに直接書き込んだり、語呂合わせや図を書き足すだけでも記憶に残りやすくなります。
覚えられないスライドは、必要な部分だけ切り取ってGoodnoteにまとめる方法もおすすめです。
私は主にノートPCで勉強しているので、Ankiのデッキにいれて、ブラウザモードからいつでも復習できる、という状態を作っています。
5位:メンタル管理が大事

メンタル管理は成績と直結する重要な力です。
試験前は、不安や焦りが一気に強くなります。
「あんなに勉強したのに間に合わない」「友達は自分よりも遅く始めたのに余裕で受かっていく」とか…
そう感じて落ち込んだり苛立つことは、何度もありました。
試験期間中、手ごたえのなさに自宅のお風呂で泣いてしまい、しばらく勉強に戻れなかったこともあります。
しかし、そうしている間にも周りの友達は翌日の試験に向けて猛勉強しています。
メンタルを病んでいる暇があったら、勉強しないとまた次の試験の手ごたえがなくなってしまい、負のスパイラルに陥ってしまいます。
まずはメンタルを病みにくい土台を作ることが大切です。
具体的には、睡眠・食事・運動の小さな習慣から大切にしていきましょう。
この3つを整えるだけで、心の耐久力が大きく変わります。
もう一つ大切なのは、とにかく勉強を続けることです。
勉強量が積みあがると、「ここまで理解できている・覚えているから大丈夫」と自信につながります。
試験後の落ち込みも軽くなり、すぐに次の科目へ気持ちを切り替えられるようになります。
さいごに
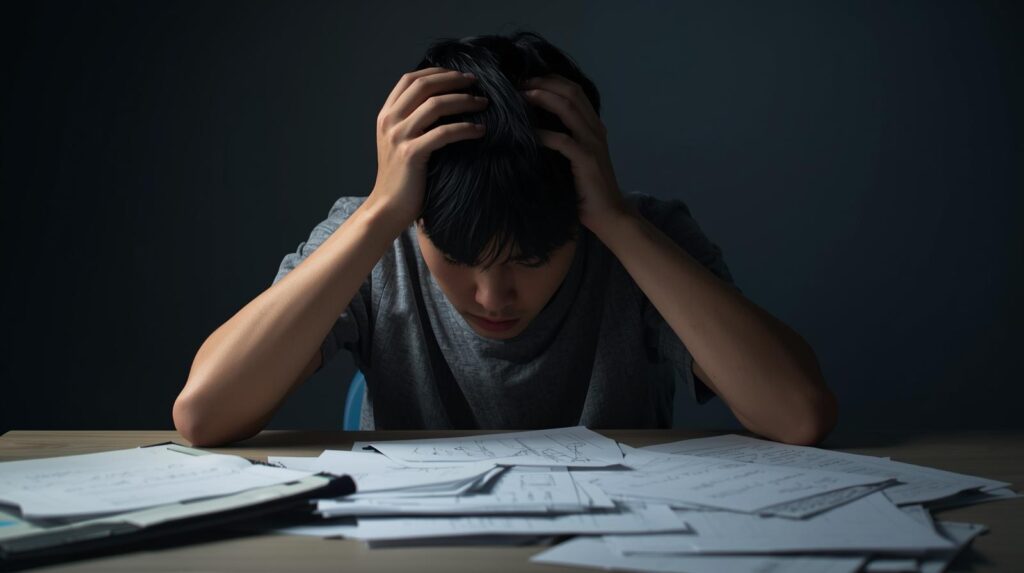
医学部の勉強は、大量の暗記や試験の連続で、誰でも一度は挫折を経験します。
けれど、挫折はむしろ自分の勉強法を見直すチャンスになります。
今回紹介した5つの学びは、どれも私が実際に失敗して、そこから得たものです。
うまくいかないときは、自分を責めすぎず、小さな改善を積み重ねてください。
その積み重ねが、必ず成績に繋がります。
そして、もし一人で抱え込んで苦しくなったら、
遠慮なく周りに頼ってください。
医学部の勉強は、仲間と支えあうことで強くなれます。
医学生道場はそんな皆さんの味方です。
勉強の不安やメンタルの悩みがある方は、
ぜひ公式LINEで気軽に相談してください。
あなたの努力が必ず未来につながるように、医学生道場は全力でサポートします。
FAQ(よくある質問)
Q1. どうして理解ベースの勉強がそんなに大切なのですか?
A.医学の知識は全て因果関係でつながっています。
理解して覚えた情報は長期記憶に残りやすく、臨床科目や国試で応用が効きます。
過去問丸暗記だけだと少し問い方が変わるだけで対応できず、再試や留年につながりやすくなります。
Q2. 過去問とレジュメのバランスはどう取ればいいですか?
A.まずは「レジュメを確認しながら過去問を解く」スタイルがおすすめです。
出題者が“何を重要視しているか”が見えるようになるため、
その後の復習量が大幅に減ります。
2周目は「間違えた問題」だけでOKです。
Q3. メンタルが弱くても医学部の勉強を続けられますか?
A.大丈夫です。多くの医学生は不安や焦りに悩み、その中で成績を伸ばしています。
大事なのは、
①睡眠・食事・運動の習慣
②小さくても「毎日やる」勉強量
③誰かに頼れる場所(友達・先輩・塾)
この3つです。
1人で抱え込まなければ、メンタルは確実に安定します。