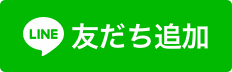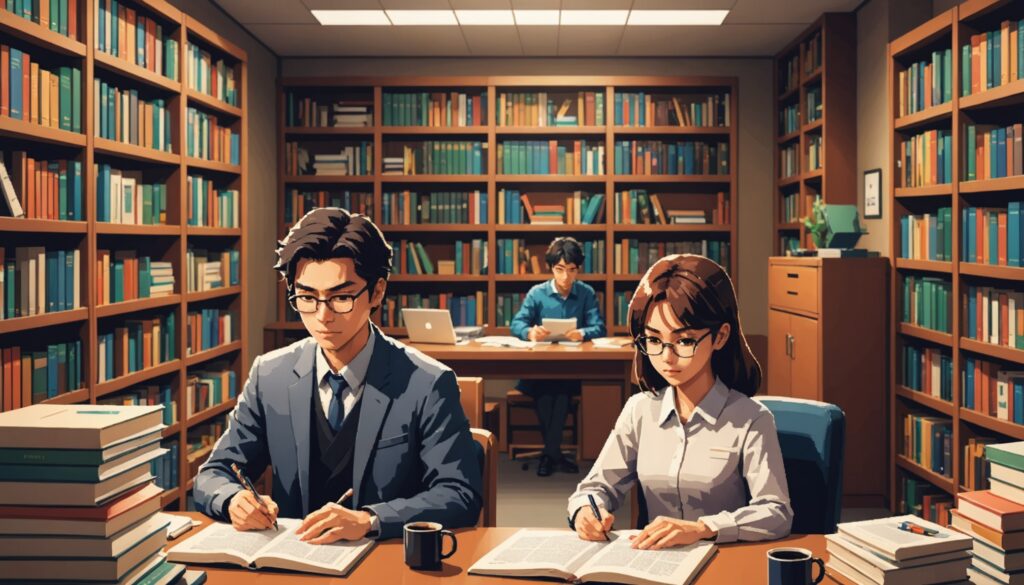
著者名:原田
所属:株式会社リーフェホールディングス経営企画室部長
資格と経歴:法学部-政治学研究科<修士><博士>-政治学教員
自己紹介:幼少期より病気がちで、こんにち無事に生活できているのは、医療とそれに関わる人たちのお陰です。将来の医師として、社会に貢献できる医学生の方を積極的にサポートしていきます。
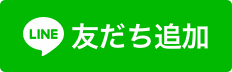
医学部生にとって、cbtは国家試験へとつながる重要なステップです。だからこそ、高得点を目指すためには効率的な学習法と早めのスタートが欠かせません。特に定期試験と重なる時期は忙しくなりがちです。そこで、少しでも早い段階からcbt対策のペースをつくることが、成績に大きな差を生み出します。今回は、過去の医学生道場ブログの中から、医学部cbt対策に関しとくに好評であったタイトルに絞り、ご紹介をいたします。
目次
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓そもそも医学部cbtとは? 「医学部cbtの概要とは?」
このブログのポイント:
【医学部cbtとは?】
医学部cbt(Computer-Based Testing)は、医学生が臨床実習前に受ける全国共通の筆記試験で、パソコンを使って実施されます。
【医学部cbtの歴史と導入の背景】
【 医学部cbtの導入までの経緯】
【医学部cbtの特徴】
【まとめ】
医学部cbtは、医師としての基礎的能力を全国統一の基準で測定するために導入された比較的新しい試験制度であり、現在では臨床実習に進む前の必須試験として定着しています。
医学部cbt、いつから勉強を始めるべきでしょうか?
医学部cbtは確かに範囲が広く、苦労する場面もありますが、自分に合った学習計画をしっかり立てて臨めば、目標スコアを達成することは十分可能です。大切なのは、早めの準備と継続的な学習です。自分の弱点を正確につかみ、計画を着実に実行していけば、医学部cbtそして国家試験さらにその先の医師生活へと自信を持って進めるはずです。医学部cbt対策の取り組み、勉強をいつ始めるかは、個人の進度によりますが、早めの計画的な取り組みがおすすめです。例えば、
☞三年次後半に基礎を整理して問題演習を開始
☞四年次前半には模擬試験で弱点を見つけ補強
☞定期的に集まって情報交換や勉強会
慌ただしい直前期を避け、少しずつ積み重ねることが大切です。
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓医学部cbt いつから? 昨年度、医学部cbtを受験した医学生の体験談 「5−6ヶ月前が理想的」「本腰を入れるのは1−2ヶ月前?」
このブログのポイント:
【受験生(筆者の)プロフィール】
大学4年生、cbt受験を終えた直後の医学生。
【受験前の不安】
【実際の対策と行動】
【受験当日の様子と感想】
【アドバイス】
1年生や2年生のうちから基礎科目をしっかり固めておくと、後々の応用問題にも強くなり、直前期にも焦らずに済むとされます。
医学部cbt対策で大切なのは、まず全体像を押さえることです。cbtで問われるのは臨床実習に必要な基本的知識が中心ですが、科目の範囲が広いため、過去問や問題集を解いて弱点を早めに把握しておきましょう。予習や復習を計画的に進めることで、定期試験との両立もグッと楽になります。
忙しい医学生であれば、いかに効率良く必要な勉強を修めるべきか、重要なテーマとなってきます。その方法とは、各医学部の先輩に聴くのが正確でありますけれども、おおむねどこの医学部でも通用する方法を以下のブログで紹介しています。「勉強スケジュールの立て方」をはじめ、「おすすめの勉強法」、よく陥りやすいミスなど、医学部の先輩が予め先回りをして、アドバイスをします。
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓効率のよい医学部cbt勉強法&スケジュール 「医学部cbt おすすめ勉強法」「医学部cbt 勉強スケジュールとは?」
このブログのポイント:
【医学部cbtとは】
【勉強を始める時期】
【勉強スケジュールの立て方】
【おすすめの勉強法】
【注意点・よくあるミス】
【医学生道場のサポート】
直前期には問題演習に集中し、多様な形式の設問に慣れながら自分の苦手分野を最終チェックします。集中力を高めるコツとしては、時間を区切って勉強するポモドーロテクニックの導入などです。対策のポイントは以下のとおりです。
✓まず学習範囲を整理し、短い目標を設定する。期間ごとに取り組む内容をッチなどを取にして集中力を上げます
✓ 苦手分野は早めに潰し、問題演習とテキスト理解を並行する。理解と記憶を繰り返すと定着度が高まります
✓計画が崩れたら柔軟に修正し、仲間と情報共有する。相談し合うことで不安が軽減されます
小さな達成を重ねるほどやる気が湧き、さらに実力も伸びます。学びの過程を楽しめば、その先の臨床実践で光る力につながります。知識を体系的に整理しながら、実臨床をイメージすることも大切です。
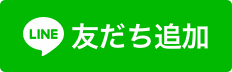
医学部cbtの直前期とされるのは、試験日の1−2ヶ月前であるかと考えます。その直前期には医学部cbtの対策を本格化させる–本腰を入れなくてはなりません。さて、直前期にはどのような心構えで学習に取り組むできでしょうか? そして時間が限られる中で、おすすめの教材は何か、何をチェックして何をやらないべきか。大事な試験で落ち込みがちの気持ちにモチベーションを維持する方法など、解説します。
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓医学部cbt 直前期の勉強法 「医学部cbt模試をどのように活用するか?」
このブログのポイント:
【医学部cbt直前期の特徴と心構え】
【効果的な勉強法】
【おすすめの教材と活用法】
【モチベーションの保ち方】
【医学生道場のサポート】
医学部cbtと定期試験を両立するには、学習の優先順位を決めて計画を立てることが大切です。試験範囲や日程を俯瞰し、どの分野に時間をかけるかを明確にしましょう。計画は細かく分割し、隙間時間も有効に活用しましょう。
✓過去問や重要ポイントを優先的に押さえる
✓到達目標を小分けにしてモチベーションを維持する
✓疲れすぎる前に休息を入れ、効率を保つ
毎日少しずつでも続ければ、力がついてきます。
医学部cbtが公的化され、早ければ8月中旬より試験が始まるようになりました。従来は定期試験と医学部cbtの実施時期が分かれていたところ、このために定期試験と医学部cbtの時期がほぼ重なり、両方を同時に対策しなければならなくなりました。さて、その両立させる方法とは何でしょうか? 昨年度(24年度)医学部cbtを受験した医学生より、提案です。
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓医学部cbtと定期試験の両立法 「医学部cbtの公的化で定期試験の出題法が変わった?」
このブログのポイント:
【背景】
【CBTの公的化による影響】
【難化する定期試験との両立】
【医学生道場の提案する学習法】
【結論】
CBTの公的化により、定期試験とのバランスがより重要に。今後は「計画性」「アウトプット重視」「専門指導」が鍵となる。
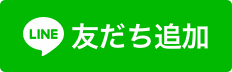
特に、医学部cbtで9割超えを目標とするなら、細かい暗記分野をおろそかにできません。基礎医学や臨床科目の全般にわたって、繰り返し確認する習慣をつくっておきましょう。苦手科目ほど早めに取りかかり、小さな成功体験を重ねてモチベーションを維持することが大切です。勉強仲間と問題を出し合いながら雑談形式で覚えるのも、定着度を上げる有効な方法になります。
詳しく知りたい方はこちらをクリック!⇒ ↓医学部生がcbt試験で9割超えを狙うための基本から実践まで 「効率的学習法と集中力アップのコツを紹介します」
このブログのポイント:
【CBT試験の概要】
【学習戦略の全体像】
①1. 基礎期(1〜3月)
②2. 応用期(4〜6月)
③3. 仕上げ期(7月〜試験直前)
【得点アップのコツ】
【直前1ヶ月のポイント】
【本番に向けた重要視点】
【先輩の声】
【まとめ】
さらに、効率よく学習を進めたいときは、プロの指導を受けるのも一つの手段です。医学生に特化した個別指導であれば、あなたの学習ペースや弱点に合わせたカリキュラムを組んでもらいやすく、モチベーション維持にも効果的です。留年回避を目指しながら、1年生から6年生までしっかりサポートしてもらえる環境があれば、医学部cbt対策も安心して取り組めます。
医学部cbtの合格には「正しい勉強法」と「精神面の安定」がカギとなります。
医学生道場では、一人ひとりに寄り添った対策サポートを提供しています(医師講師たちと専任の教務担当が相互に連携)。
実際に合格した先輩たちの声を活かした指導が受けられます。
つまりその医学部に沿って、最新の情報から学ぶことが可能です。
お問い合わせはLINE、メール、お電話から。