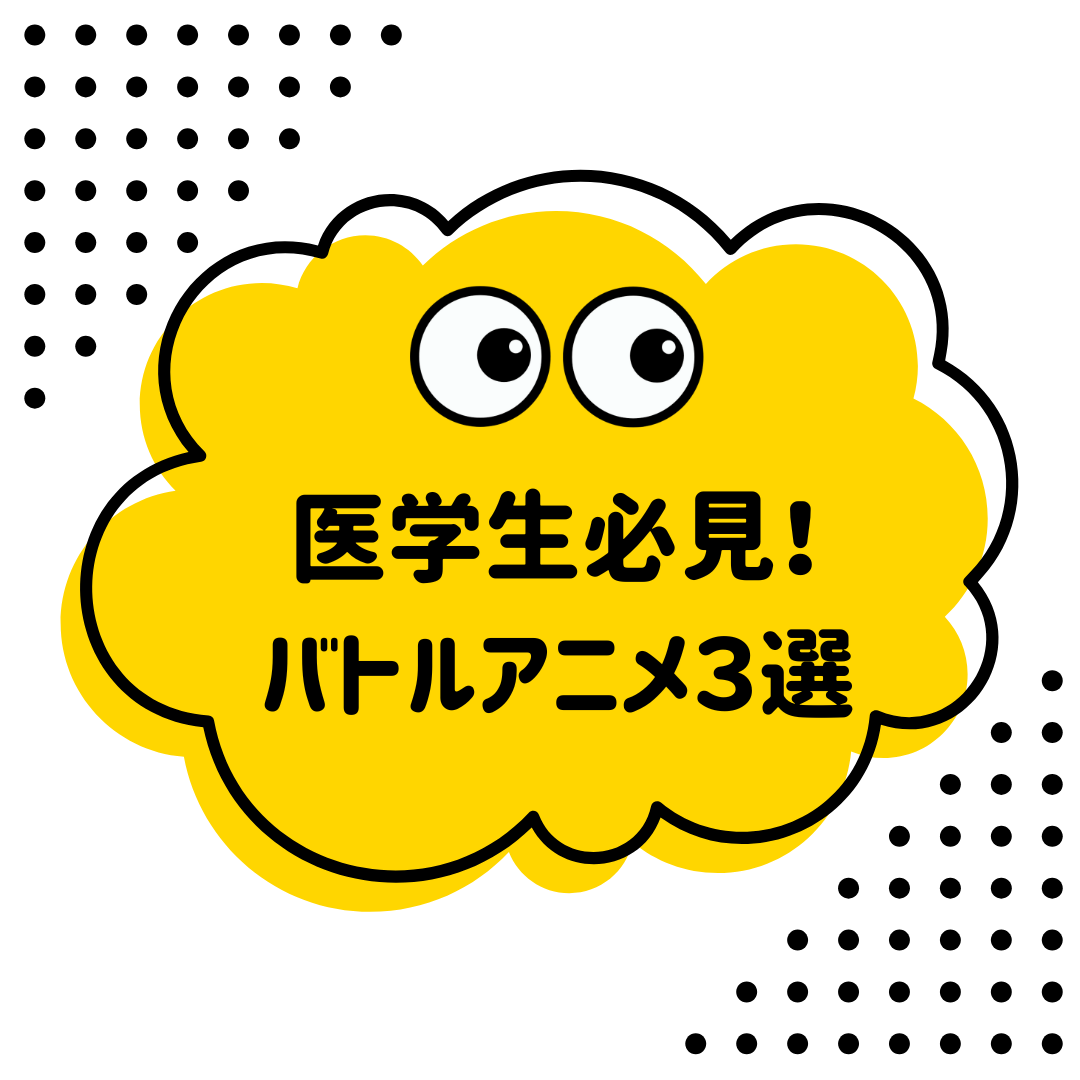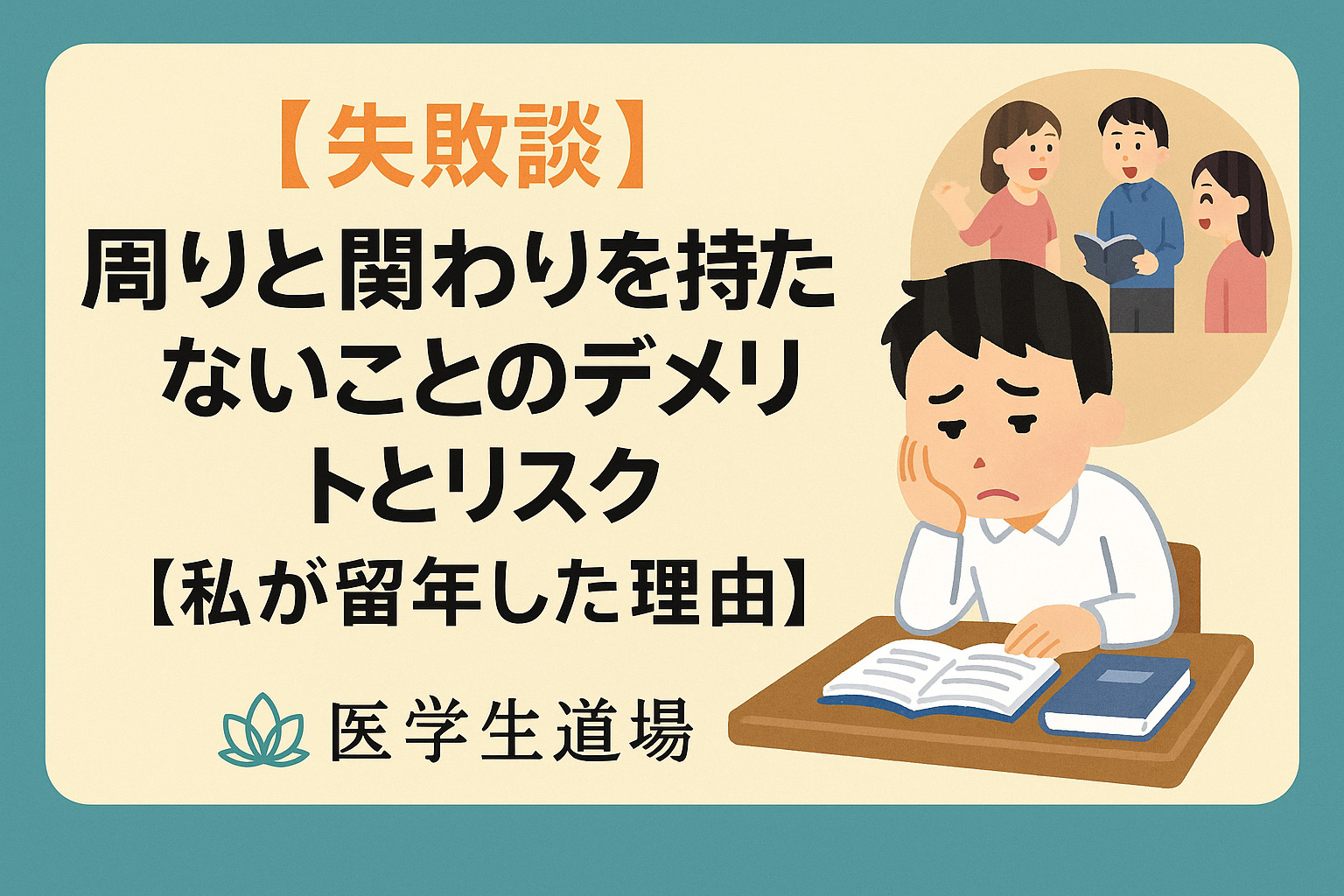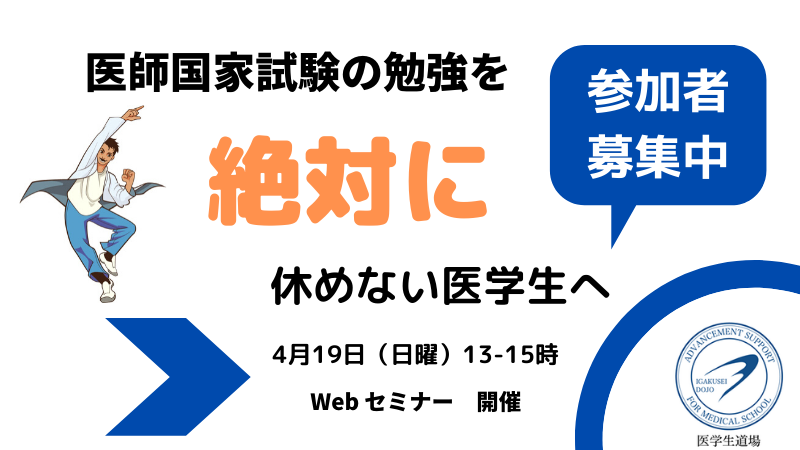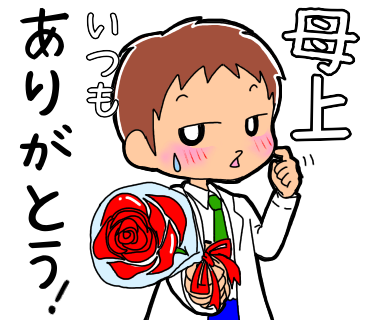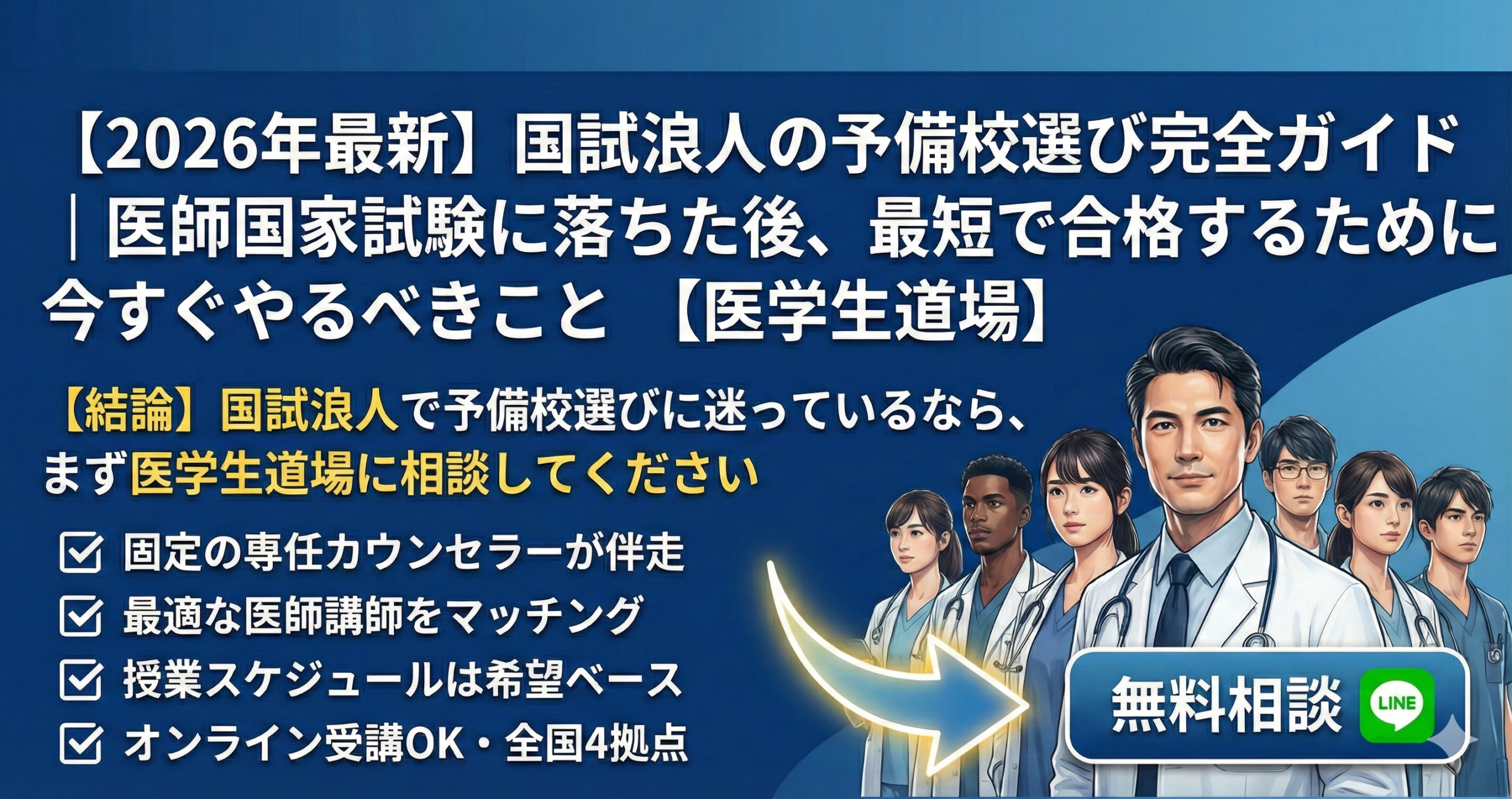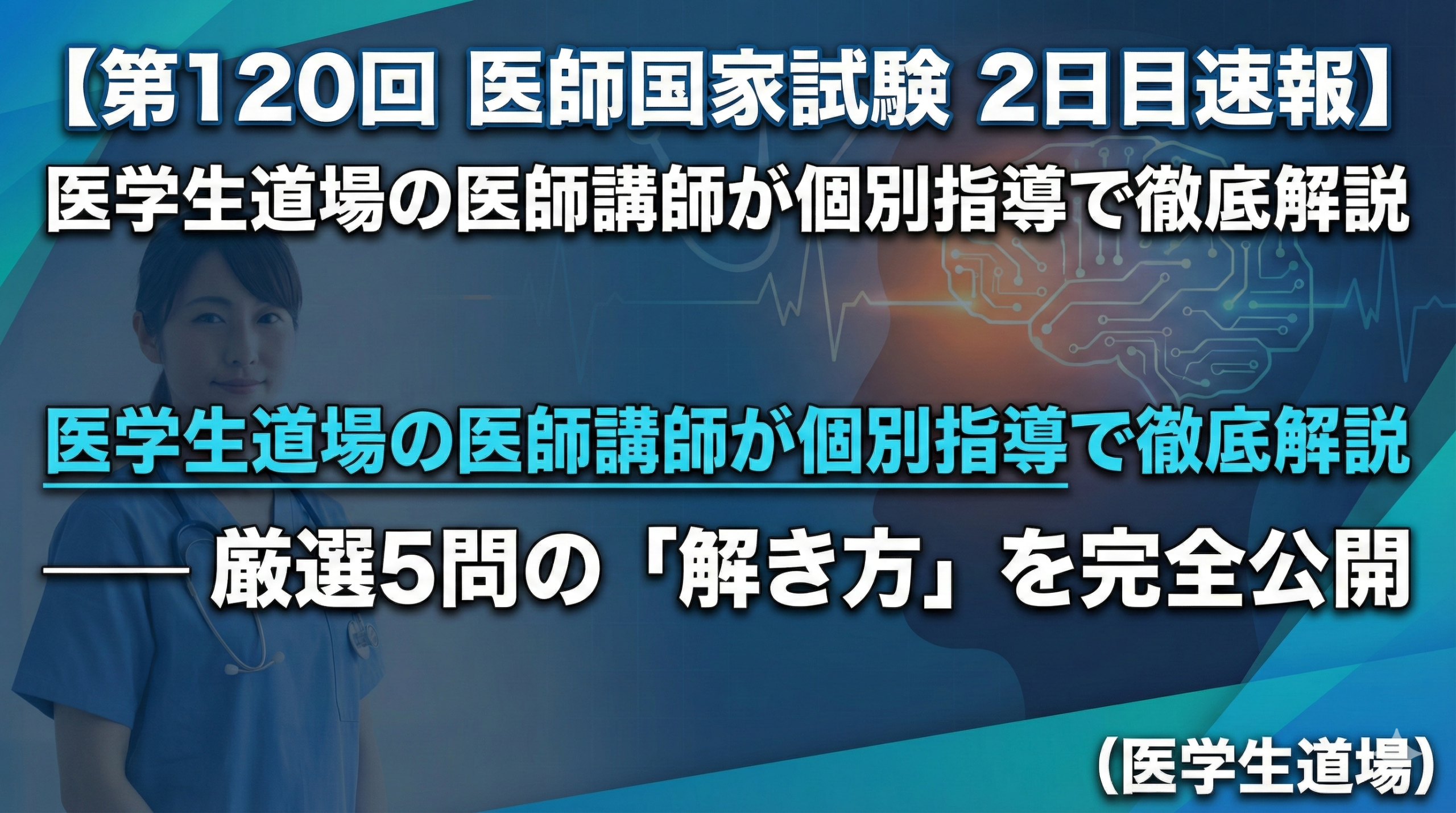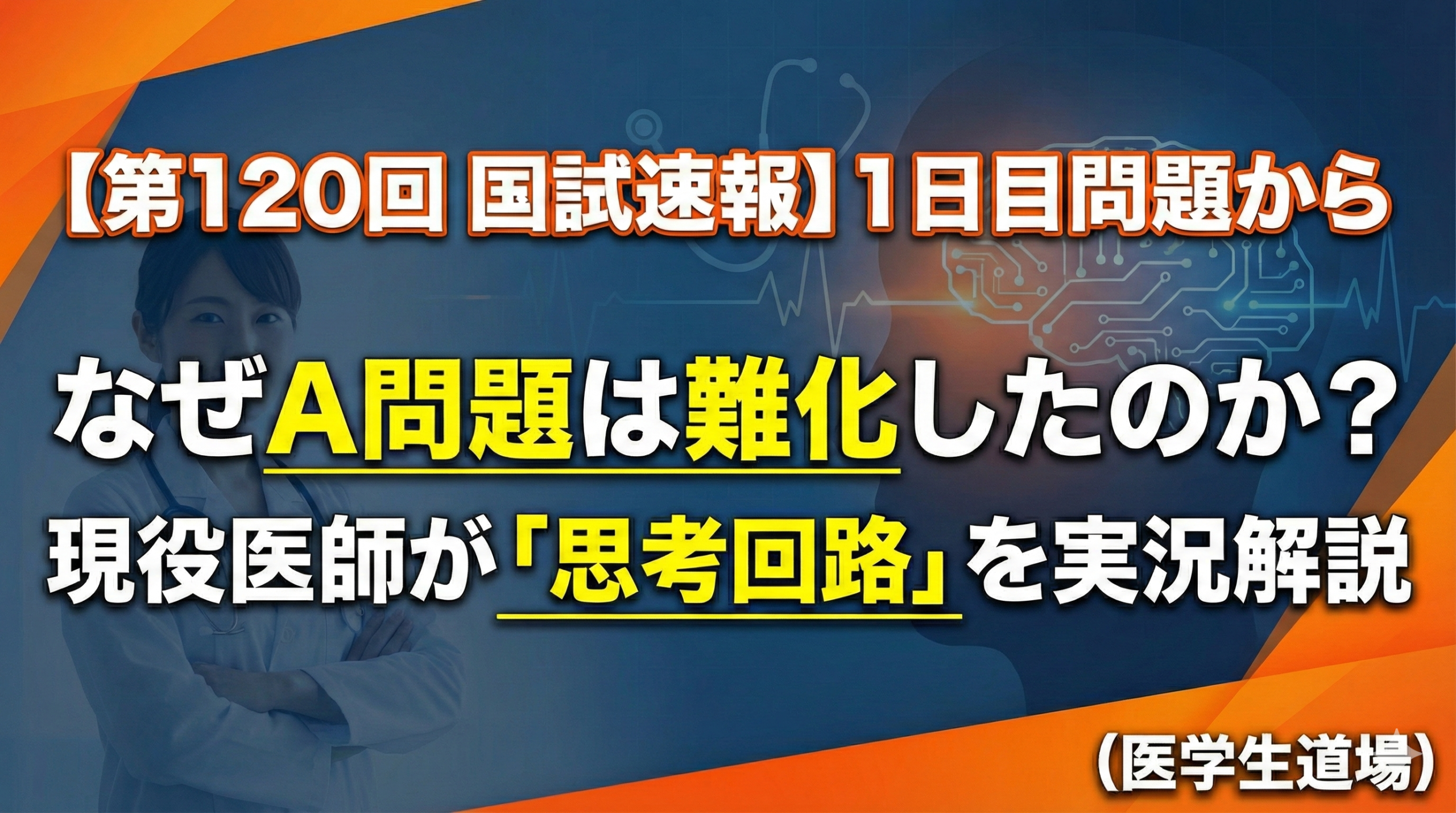はじめに
こんにちは!
医学生道場の竹田美穂です。

みなさんは進級試験の勉強はどのように進めているでしょうか?
私は、現在まで毎試験期間ごとになんらかの再試験にかかってしまっているので、次の定期試験では絶対にひとつも再試にかからないぞと意気込んでいます。
意気込んでいるだけですが…(;^ω^)
いまはひとまず今年秋に迎える医学部CBTに向けてQBの一週目問題を解き進めています。
さて、医学部って、やっぱり大変ですね。
課題も多いし、一科目一科目の勉強量も重い。
医学部は、他の学部に比べて留年しやすいってよく言われます。
私も、1年生の時は医学部の勉強をなめており、医学部の厳しさを身をもって実感しました。
ただ、振り返ってみると、その背景には「一人で判断していたこと」がたくさんあったと感じています。
周囲と情報を共有しなかった結果、それが留年という大きな失敗に繋がってしまったんじゃないかな、と思います。
さて、今回はそんな私の失敗を振り返りながら、
「一人で判断したことによる失敗」についてお話しします。
もし今、これを読んでいる人が私と同じような道をたどっていたら
私の失敗を反面教師にしてもらえたら嬉しいです。
著者名: 竹田美穂
所属:都内私立医学部医学科4年生
資格と経歴:3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次に大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。
過去著した主なブログ:「【経験者が語る】医学部の定期試験の特徴とは?留年するとどうなる?試験対策の方法を徹底解説!」「今どきの医学生の勉強事情を大解剖!【ご家族の方へ】」
アピールポイント:留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています。
自己紹介:留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!
医学部の勉強は暗記?
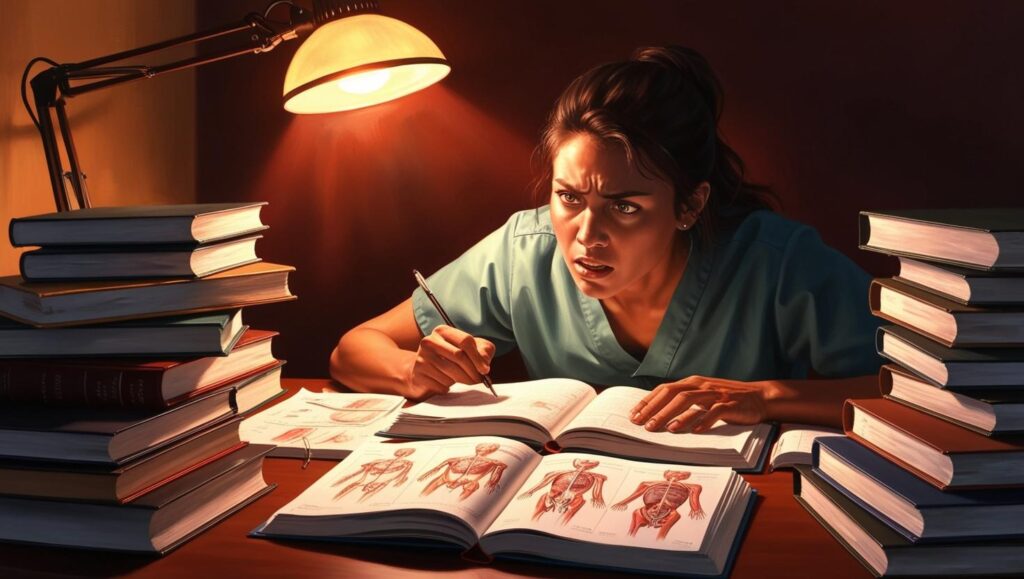
医学部の勉強って、とにかく量が多いですよね。
授業も多いし、初めて聞く用語はやたら出てくるし、新しいことがどんどん詰め込まれる。
早々に講義内容においていかれて一瞬焦るも、私は医学部に正規合格したし、謎のプライドから、いずれ試験勉強する時には身についているだろうとのんびり考えたりしていました。
当時、周りには1浪して補欠合格していた友人や、現役で推薦合格していた友人がおり、そんな周りの友人たちが焦っているところを見ても、まあ本気出せば余裕で巻き返せるでしょう笑、と思っていました。
実際は、進学校出身のポテンシャルが優れた友人や、頭の回転数が違うような友人ばかりで、地頭の悪い私は、あっという間においていかれてしまいました。
そんな私は、試験前、「結局、医学部の勉強って丸暗記なんでしょ」と思って、レジュメ一枚一枚を片っ端から覚えようとしていました。しかしながら、それでは試験までに間に合うはずもありません。
一つ一つを暗記するのは、到底無理なことでした。
それぞれはバラバラではなく、つながりを持って存在しています。土台となる知識や流れをよく理解しておけば、暗記は最低限で済むということを知ったのは、留年を経験してからでした。
さらに、過去問と問題を少しでも変えられると、単純暗記では全く歯が立たなくなってしまいます。
しかし、理屈を理解していれば、応用問題でも答えにたどり着く道筋が見えてくるのです。
医学部の勉強法は丸暗記じゃない!理解が大事!
ということを実感しました。
過去問だけに頼る
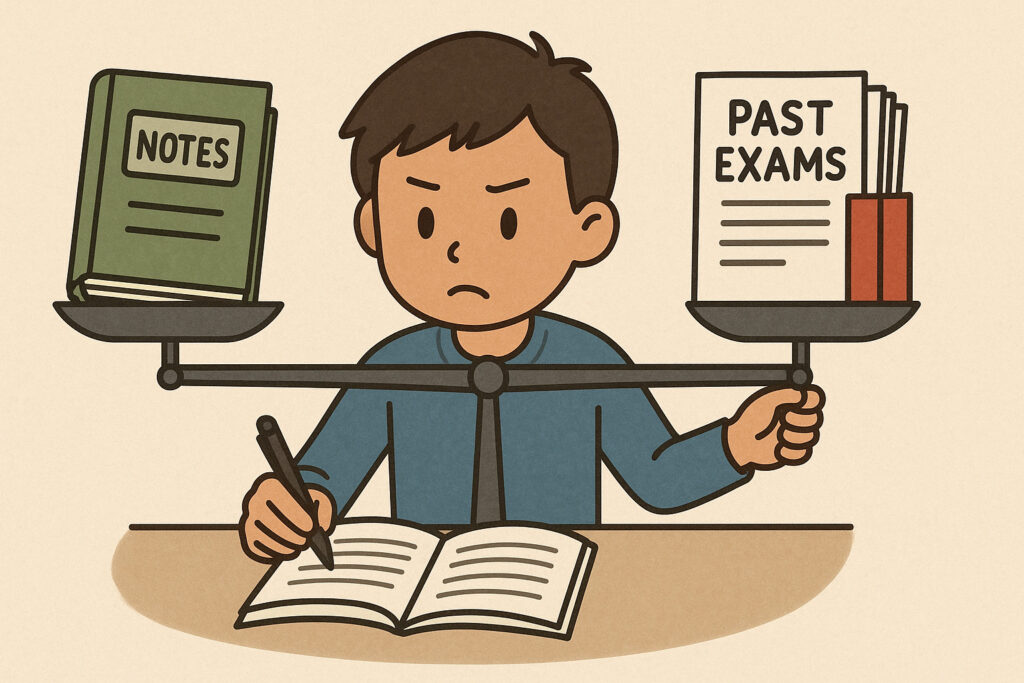
次に、私がやってしまった失敗が、「過去問だけ」に頼ってしまったことです。
1年生の初めての前期試験で、対策方法が分からないながらもとりあえずレジュメを丁寧に読んでいきました。当然試験直前まで覚えきれず時間が足りなくなり、本番当日を迎えることに。近くの席の友人が過去問の冊子を赤シートで隠しながら沢山書き込みを入れて解き込んでいるのが見え、(過去問全くやってなかったわ)と思い慌てて過去問冊子をざっと見て、試験に挑みました。
配られた問題は過去問と同じ問題がちらほらあり、「絶対これ過去問やり込んだ人は解けた問題じゃん…。もっと早く過去問暗記すればよかった」と試験時間中に泣きそうになりながら後悔しました。
次の後期試験で、過去問をやり込んで完璧にするのが大事なのかもしれないと反省を生かし、過去5年分を解いて丸暗記してから挑んでみたところ、「この問題見たことある!」と某ゼミのような状態ですらすらと筆が進みました。しかし、なぜか再試験に。
前期試験と比べたら手ごたえは確かにあったのに、なんで?と思いましたが、過去問と同様の問題は6割以上も出題されておらず、結果的に点数は50点台となっていました。
食堂で再試験の対策中、偶然通りかかった友達に声を掛けられ、「今ここ暗記中」というと、「そこ試験除外範囲だよ」と言われました。
たしかに、過去問は強力な武器です。
実際に同じ問題が繰り返し出題されたり、先生の出題したいポイントが見えてきたりもします。
効率を考えるなら、過去問の周回は大変良いのですが、しかしながら、過去問には載っていない分野が今年から新たに出題されたり、逆に毎年出ていたのに今年からは出題されないということもあったりします。
過去問だけでもダメだし、レジュメだけでもダメです。
どちらもバランスよくやるために、「いつもどんな風に勉強してる?私は今こんな風に勉強してるんだけど」と友達とお互いの勉強のやり方を共有しながら常に客観視できる姿勢を維持できるといいと思います。
周りに相談できない

私がもう一つやらかしたのが、「友人を頼れなかったこと」です。
「一人の方が静かだし、集中できる」「友達にわからないところ聞かれても答えられないし、逆に分からないこと聞けるほど理解できてないし…もうすこし自分で勉強しよう」
そんな風に思って、友達と勉強をすることがあまりできていませんでした。
しかし、周りに誰もいないと「まぁ、ちょっと休憩しようかな…」が何回も起きてしまいました。
友達と一緒に勉強したほうが監視の目があるからだらけにくい、というのが一つ利点としてあげられます。
また、友達と一緒に勉強していると、見逃していたポイントを拾えたり、友達から「これってどういうことなん?」と聞かれたりして、解説することで自分でもより深く理解できたり、分からなくても一緒に調べたり、分かる子に解説してもらって理解を深めることができます。
自分以外皆がわかっている状況に焦ることも、大事なことです。
また、一人でレジュメを読んでいて、「ここ難しいし、試験には出ないと信じて飛ばそう…」とスルーしていたところも、友達と勉強することで一緒にディスカッションしてざっと理解することもできました。
しかも、なんだかんだ試験で出題されたりするので、そういう時はざっとでも触れておいてよかった、となります。
同様に、大学の先生への質問も、「こんなことも分かってないのか、勉強不足だ」と思われるのが怖くて、なかなか質問が出来ずにいました。
「一人でやる、全部自力でやる」って、めちゃくちゃ非効率なので、友達と一緒に勉強することを推奨します。
効率の悪い勉強をしてしまう

次に紹介する私の失敗は、「まとめノート作りに夢中になりすぎたこと」です。
受験生の頃、私は覚えられない公式や苦手な分野の解法をノートにまとめて、試験直前にそれを見返すというスタイルをとっていました。
その感覚で、大学入学後も期末試験対策まとめノートを作成していました。
過去問やレジュメを読み込んで、わからなかったところを解説付きでメモしたり、覚えたい事項は語呂合わせやイラストを入れて、自分が記憶に残しやすいように工夫して、疾患ごとの比較表や経路図もつけて……と、科目ごとにファイリングして作っていました。
しかし、そのノートが完成する頃には、もう試験数日前になっていました。
肝心の「読む時間」「復習する時間」がない。
自分が一生懸命まとめたノートは、試験本番では何を書いていたか思い出せず、頭が真っ白。
あんなに頑張ったのに、覚えたはずのことが全然出てこない。
もちろんまとめること自体は悪くないですし、うまくやれば 人によってはアウトプットとしてとても効果的な方法だと思います。
しかし、今振り返ると、その時間繰り返し復習したり過去問を解いたりしていればよかった、と思います。
膨大な量をインプットしなければならない医学生は、「完璧を目指す」のではなく、「試験に間に合わせること」を最重視し、今の自分が必要なことに時間を使って、とにかく効率を重視し、無駄を排除していきましょう。
先輩に頼れない

そしてもう一つ、私がやってしまった大きな失敗は、「先輩に聞くのが怖くて、何も聞けなかったこと」です。
私は昔から、年上や先輩など“自分より上の立場の人”がとにかく苦手でした。
嫌われたくない、迷惑をかけたくない。気を遣わせたくない。
そんな気持ちが先行してしまって、「試験ってどんなふうに勉強しましたか?」なんて、到底聞けませんでした。
「聞いたところで、それが自分に合う方法か分からないし…」と、勝手に言い訳して、結局ずっと一人で対策をしていました。
でも、周りの友達たちはしっかりと先輩に聞いて情報を押さえており、それが試験の勝敗を分けたなと感じています。
「この科目は絶対に落としちゃダメ」「これは例年そこまで重くないから、力を入れるならこっち」といった情報は、効率的に勉強するためにもかなり重要です。
試験の形式、過去問の傾向、教授のクセなどは、実際に試験を乗り越えた先輩に聞くことで得られる情報です。
当時先輩に話しかけられなかった私は、ただ漠然と「とにかく全部頑張らなきゃ…」と手当たり次第に手をつけて、効率の悪い勉強をしていました。
ありがたいことに、私が所属している部活には、本当に面倒見のいい先輩が多く、こちらから質問しなくても、先輩の方から「この先生はここをよく出すよ」とか「この授業はこのまとめでOK!」など、試験対策を共有してくれましたが、私が遠慮してしまって深くまで聞けませんでした。もっとたくさん友達とも情報共有をしていたらよかったなと思います。
聞ける人がいることは、強みです。先輩に頼る勇気。友達と情報を共有する姿勢。
それがあるかないかで、試験結果が大きく変わってきます。
「先輩に聞くのが恥ずかしい」「迷惑かも…」なんて思わず、試験に向けて貪欲になっていきましょう。先輩の立場になって思いますが、案外頼られるのはうれしいし、LINEなら忙しくないときに返信するから「忙しいだろうし・・・」っていう遠慮はなくていいんだなと思います。
医学生道場では、再試対策や医学部CBT・OSCEの学習支援はもちろん、メンタル的な相談や学習計画の立て直しなど、「一人で抱えがち」な医学部生活を全力でサポートしています。
私自身、浪人・留年・再試を何度も経験してきたからこそ、「しんどいときこそ、誰かに頼っていい」ということを声を大にして伝えたいと思っています。
「なんとかしたいけど、どうしたらいいか分からない」そんなときは、ぜひ一度 医学生道場を頼ってみてくださいね。
https://igakuseidojo.com/official_2025/
まとめ:失敗を恐れず、頼る。話す。理解する。
私のように一人で判断して走り出すと、いつの間にか落とし穴におちてしまいます。
でも、あなたが今ここで立ち止まれたなら、軌道修正できます。
✔ 暗記だけに頼らず理屈を押さえる
✔ 情報を共有してレジュメも活かす
✔ 一人で抱え込まず、仲間と助け合う
✔ ノートは完璧よりも実用重視
✔ 恥ずかしがらず、先輩に相談する
“ひとりで判断する失敗”は、誰にでも起こりうること。
だからこそ、あなたにはこの経験をバネにしてほしい。
医学生道場は、あなたの学習を応援しています!
ひとりで抱え込まないで、いつでも頼ってくださいね。