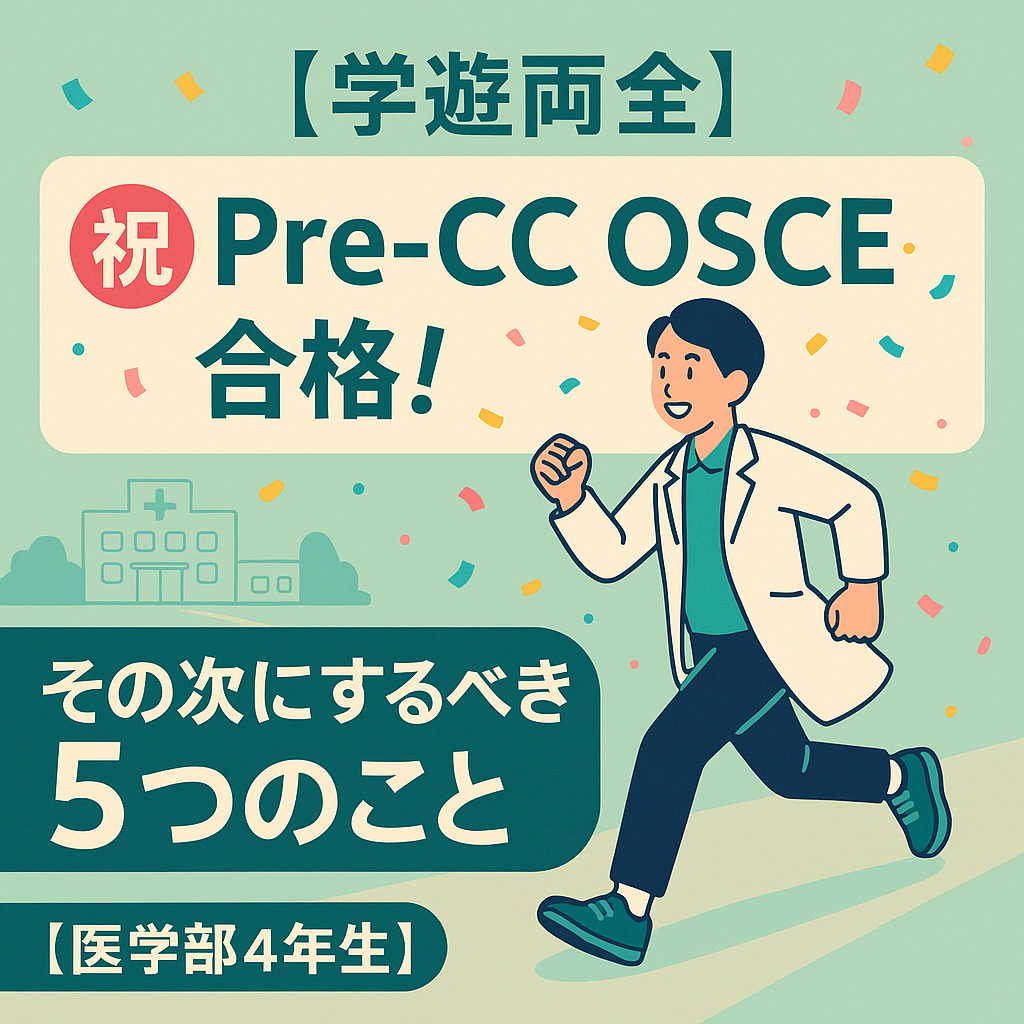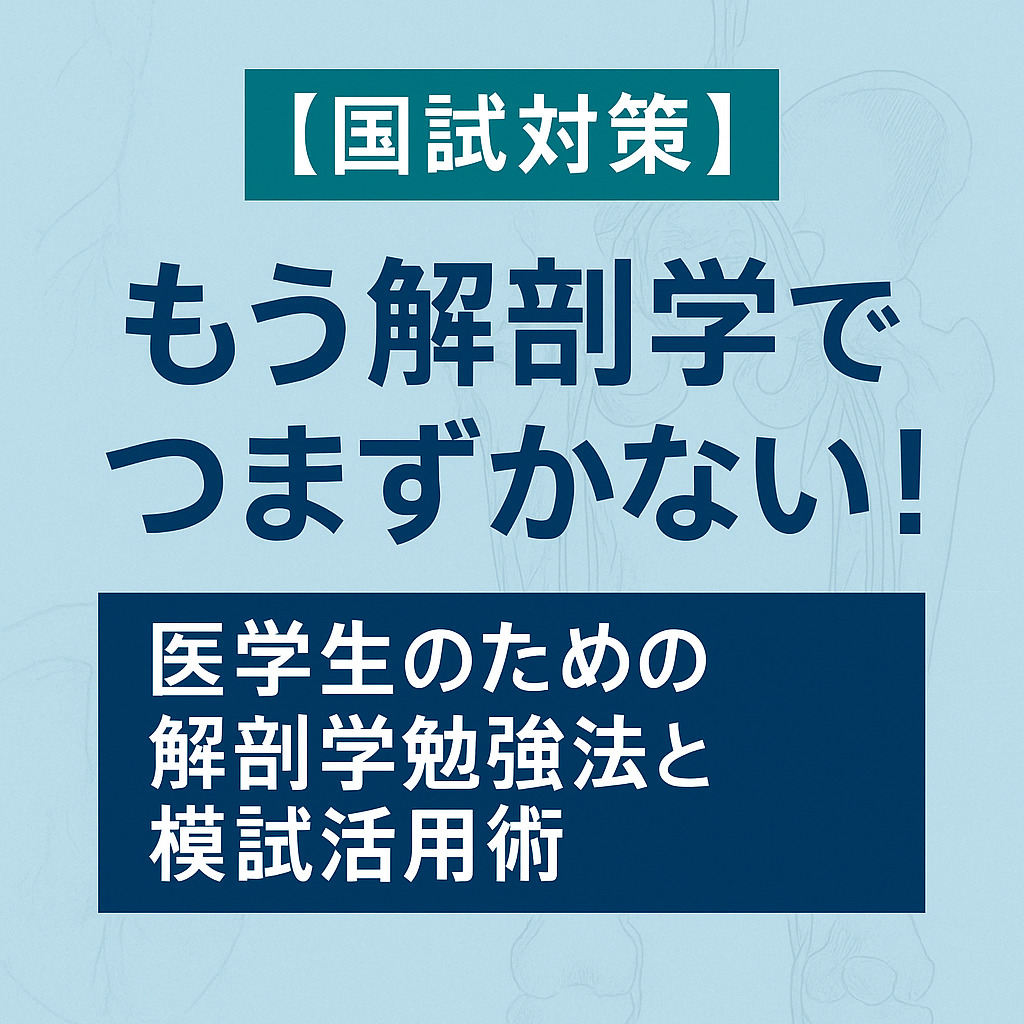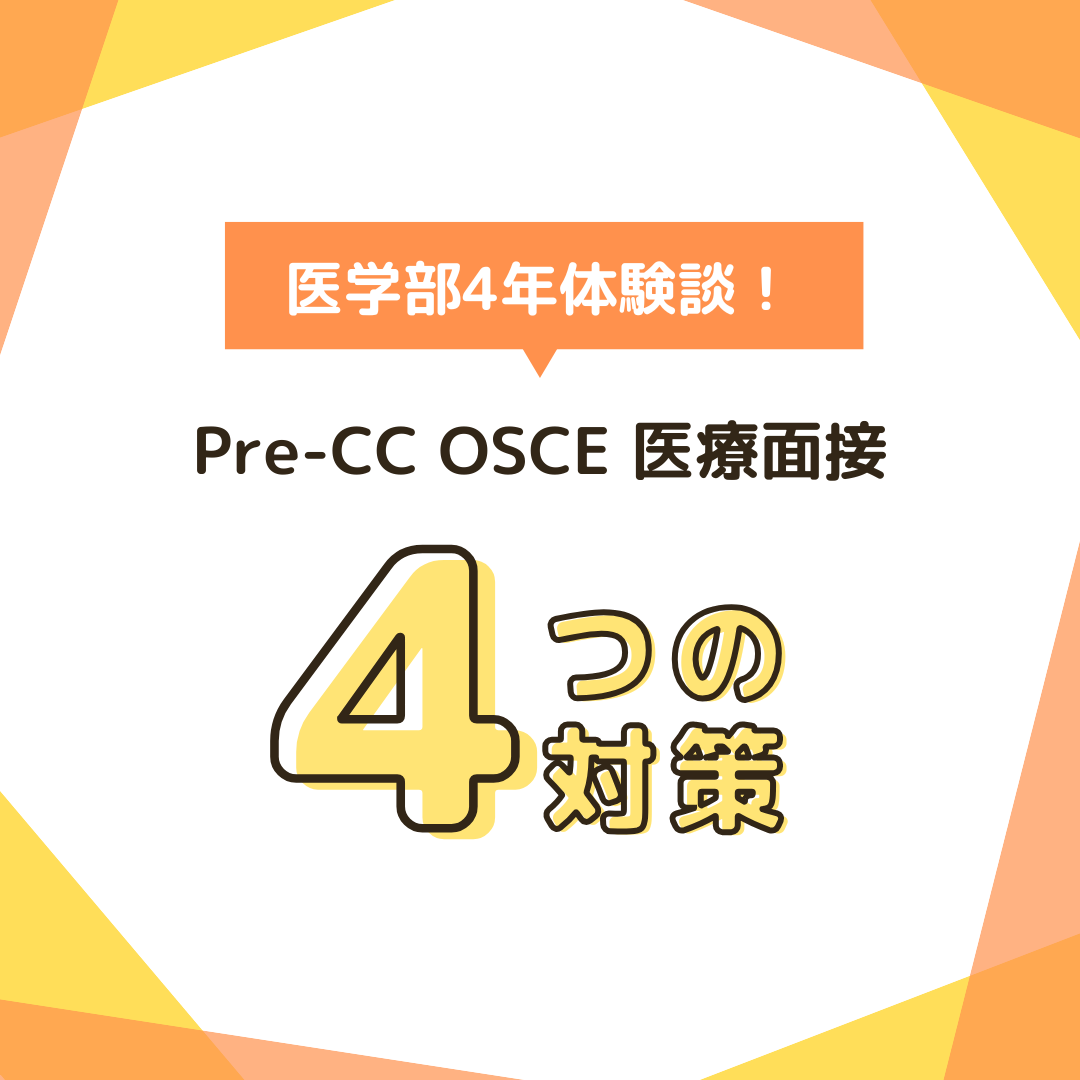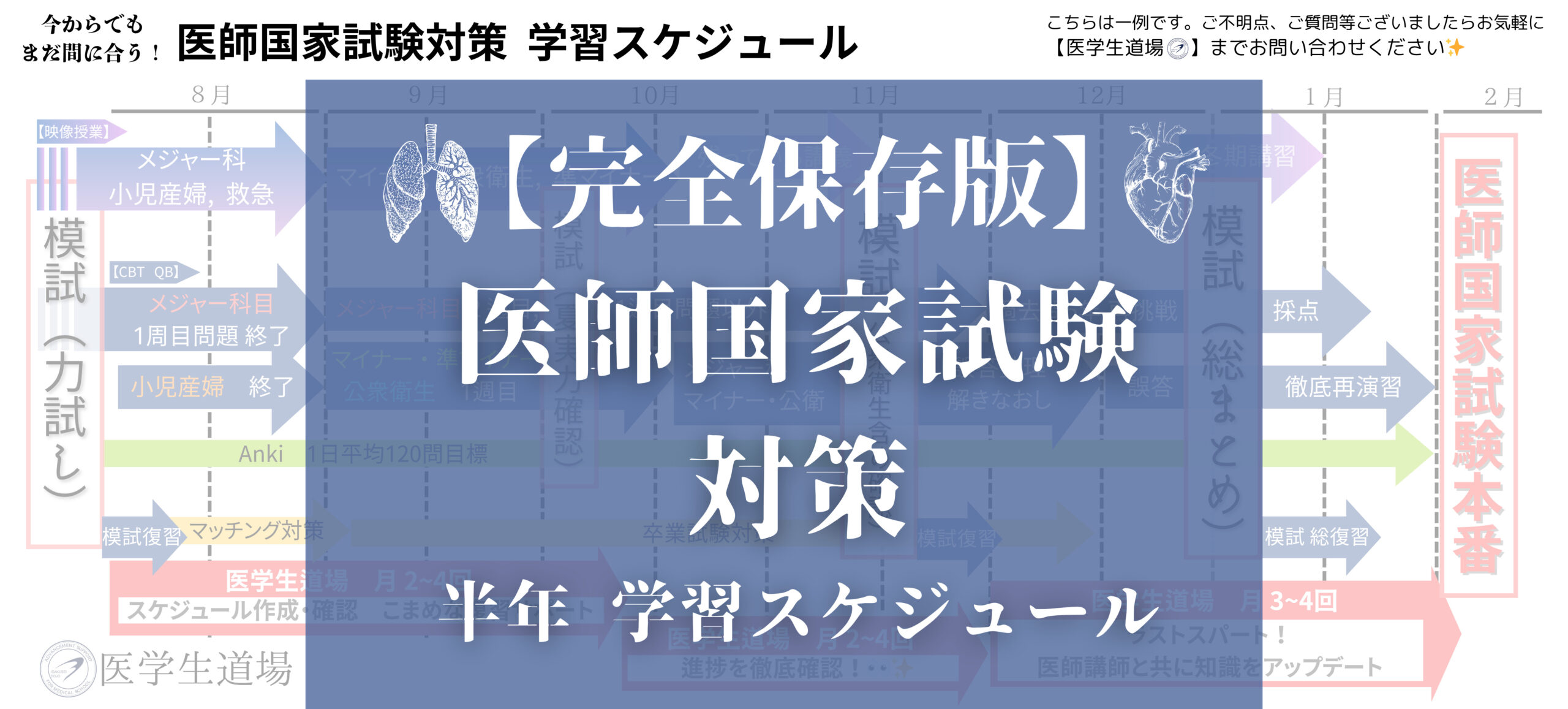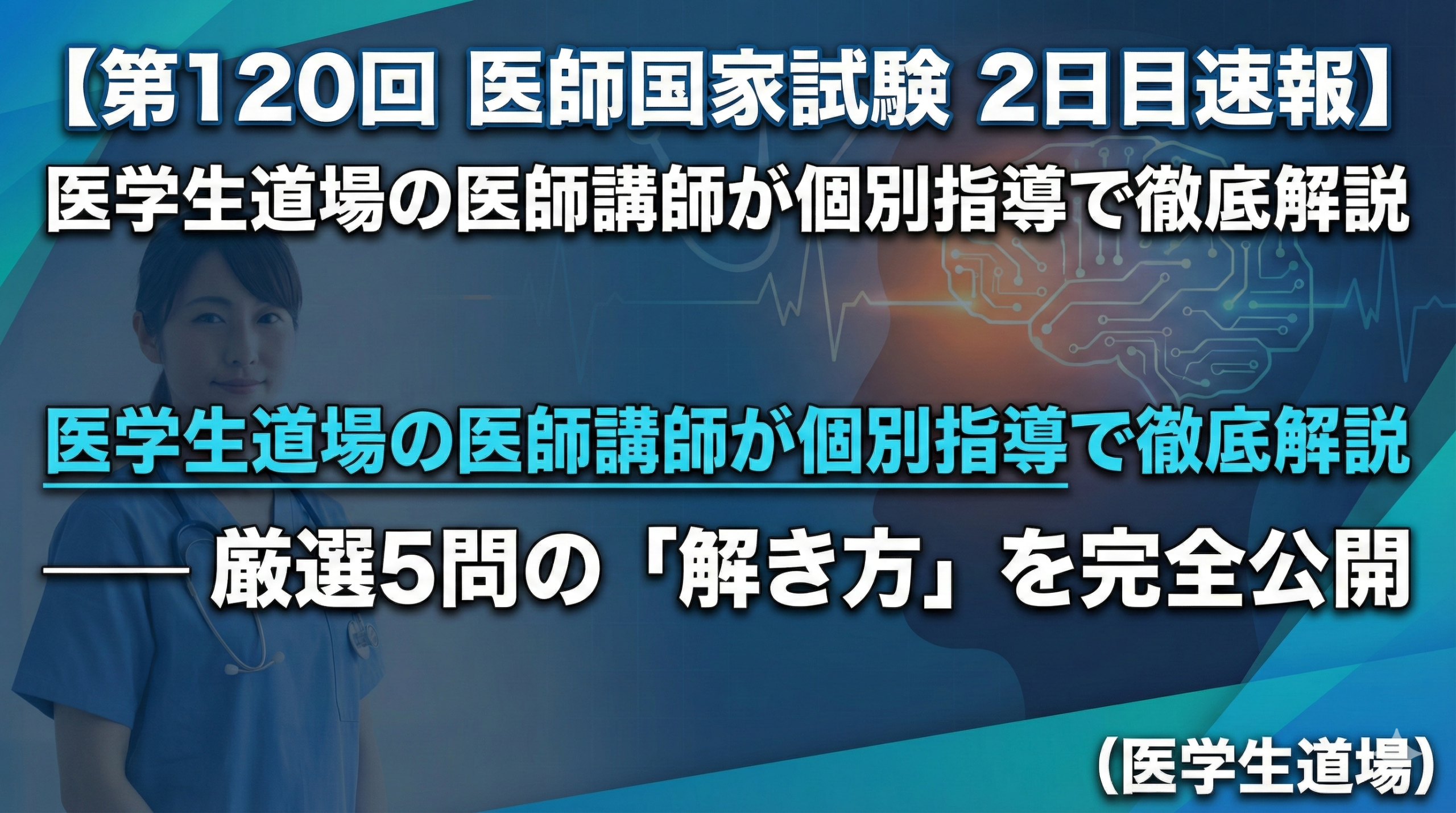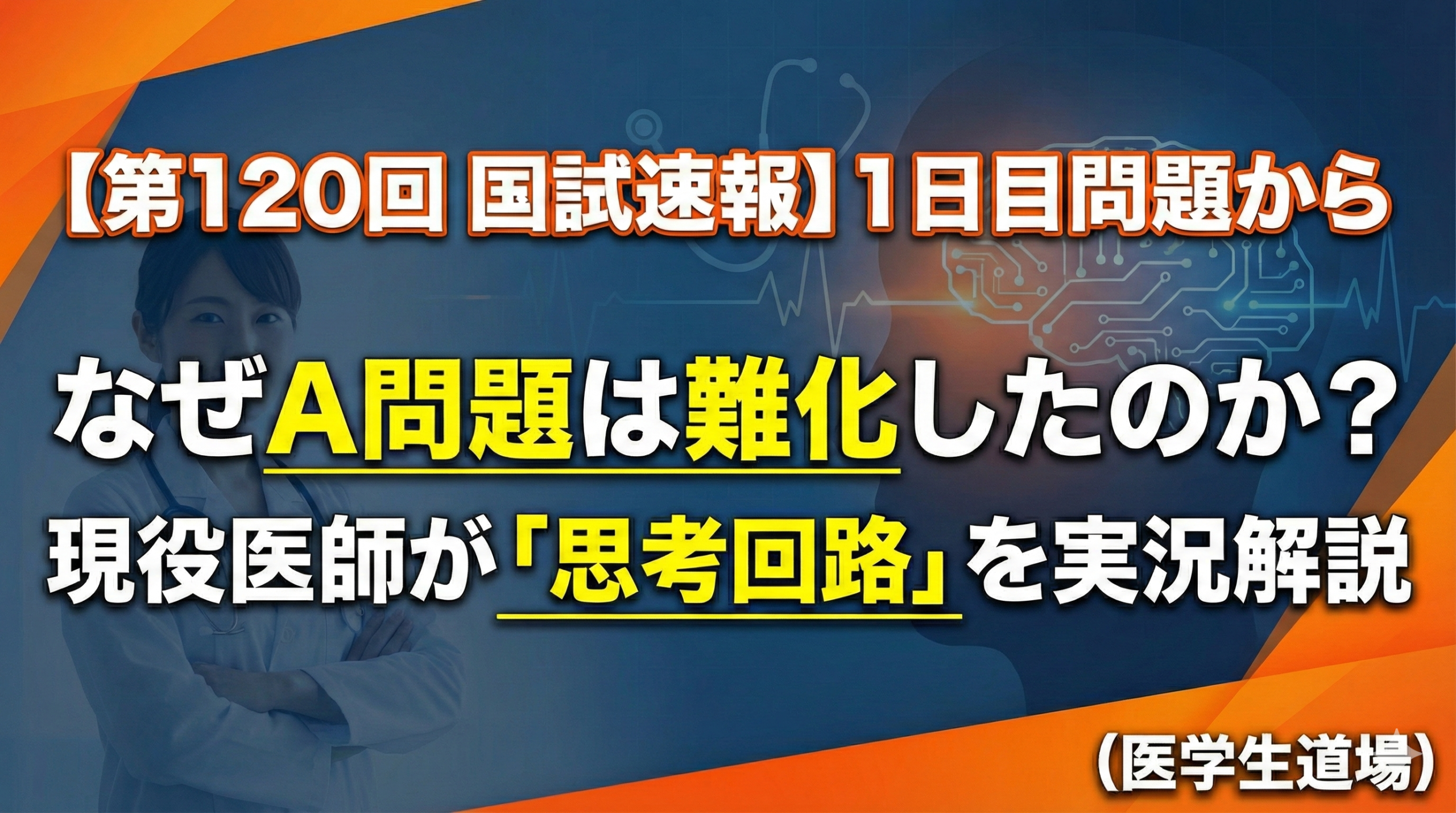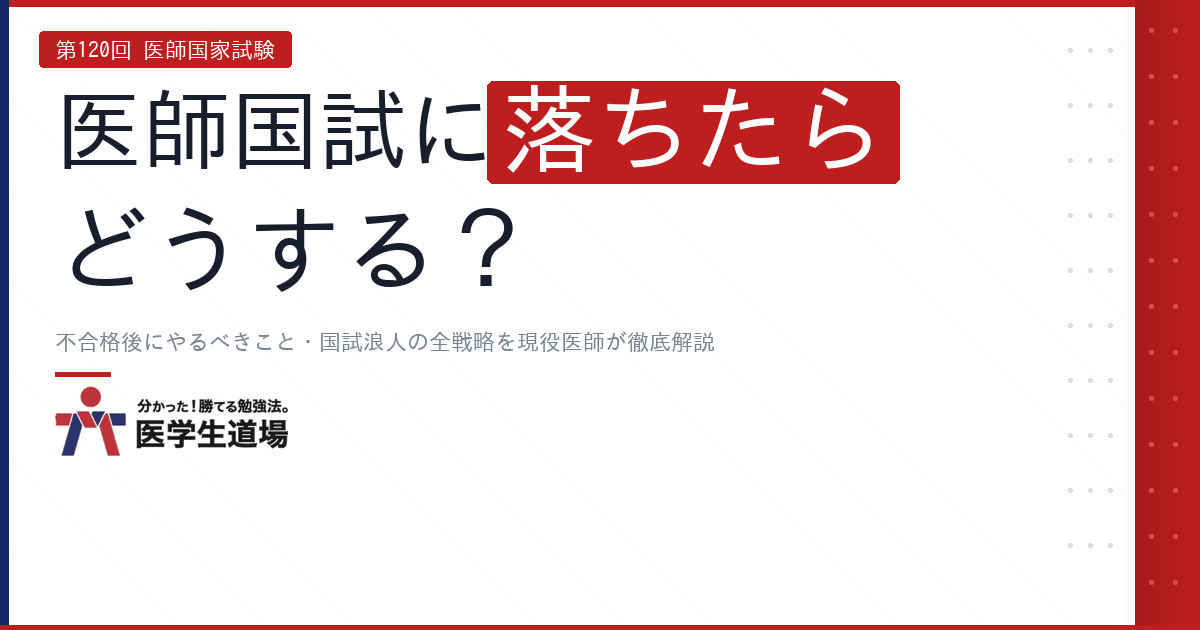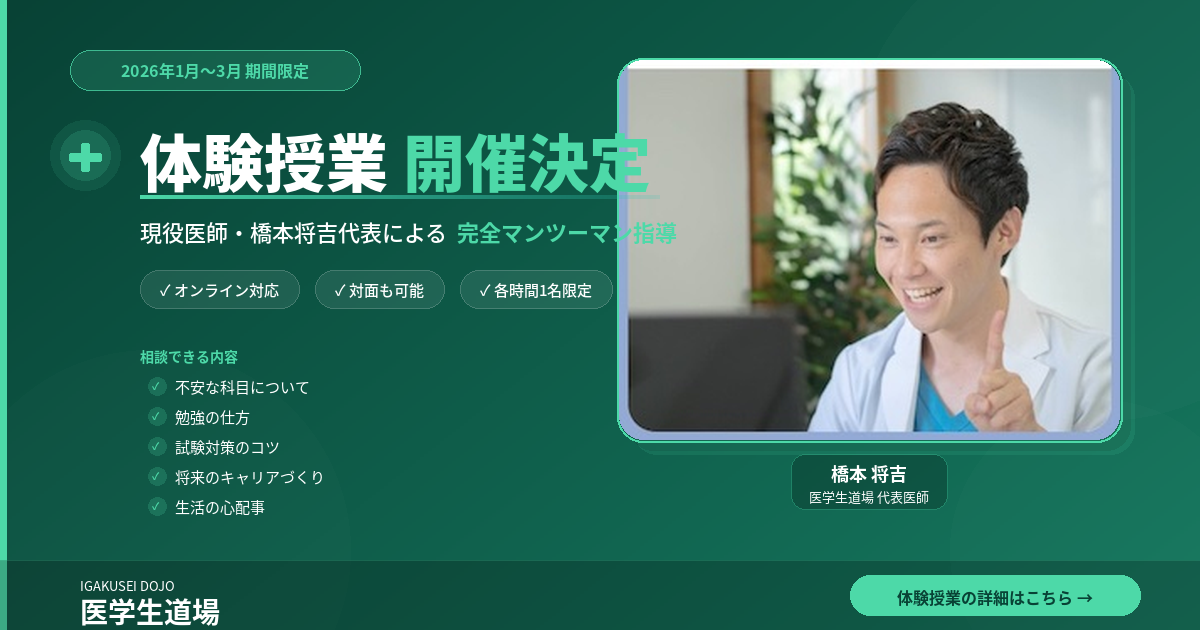著者紹介・概要
🖊著者紹介
竹田美穂 (医学部医学科4年生)
3浪を経て医学部入学、その後留年を経験。心電図検定3級取得。医学の勉強と課外活動を両立。
留年・浪人経験者だからこそわかる、医学のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。ギリギリでも何とか進級するために、実体験に基づく視点からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!
留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。「大学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!
【過去に著したブログ】
【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】
【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】医学生道場公式LINE
👉 医学生道場は医学生生活の不安や相談もOK!24時間メッセージ受付中!
🖊今回の概要
・医学部4年生にとっての大きな関門「OSCE」で落ちやすい人の特徴を3つ紹介。
・練習不足、1人練習の偏り、試験形式の理解不足について解説。
・合格に近づくための具体的な対策とは。
はじめに
医学部4年生にとって最大の関門のひとつが、臨床実習前OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)です。
Pre-CC OSCEでは、知識というよりも、「患者さんとどう向き合うか」「正しい手技ができるか」といった、コミュニケーション力・手技力が求められます。
つまり、CBTがあまり高得点ではなかった方も、再試験の常連者も、OSCEでは逆転できる試験です。
しかし一方で、毎年、OSCEで落ちてしまう学生が一定数います。
OSCEに落ちてしまうと、ほとんどの学生が他県の他大学医学部にて再試験を受けることになってしまうかと思います。
交通費もばかになりませんから、ここは一発で通っておきたいところです。
それでは、どういう人が落ちやすいのでしょうか?
今回は OSCEに落ちやすい人の特徴3パターン を紹介します。
これに当てはまらないか、ぜひ自分を振り返ってみてください。
医学生道場ではOSCEの手技やポイント、流れも実際の現場で働く臨床医とともに確認・練習ができます!
24時間公式LINEにて相談を受け付けています。心配な方、お悩みの方はいつでもご相談ください!
【失敗例①】 練習不足で本番に挑んだ人
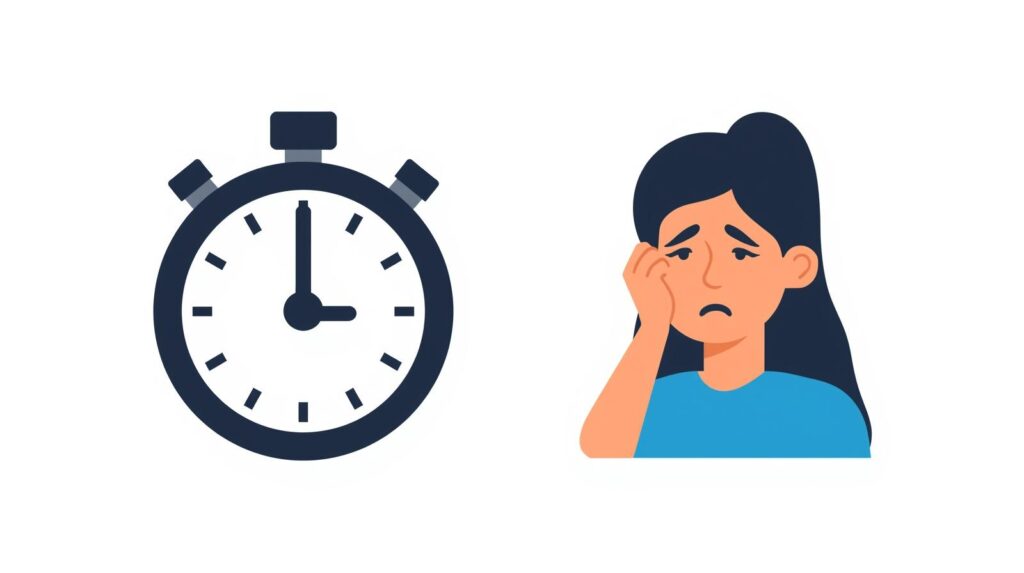
OSCEは、知識暗記だけでは合格できません。
学内試験やCBTとは全く別物の試験です。
何度も練習を重ね、体に流れを覚えこませることが大切です。
練習不足の人には、こんな落とし穴があります。
- 緊張で頭が真っ白になり、今までできていたところが分からなくなる。
- 患者さんに説明する時に、うまい言い回しが出てこない。
- 時間配分を間違え、最後まで終えられない。
OSCE本番は評価者にじっと見られながら、模擬患者さんを前にして行う試験です。
緊張して、頭が真っ白になってしまう学生も多いです。
普段はできることも、緊張で思うようにできなくなってしまいます。
また、時間制限がありますから、一つ一つ考えている時間もありません。
てきぱきと手際よくやらないと、時間切れとなってしまいます。
本来できたはずの手技や言えたはずの項目も途中中断となってしまっては、非常にもったいないですね。
そんな中、たくさん練習を積んできた人は体が覚えているので、緊張していても勝手に口が動いて上手く喋れたり、体が手順通りに動いてくれます。
正確な手順で、制限時間内に終わらせるためには、練習に練習を重ね、一連の動作を体に覚えこませるのが大事です。
【練習不足を避けるために☞CATO動画を何度も見直し、友人とともにできるだけたくさん練習をしましょう。】
【失敗例②】 一人練習しかしていなかった人

一人で練習をするのも悪いことではありません。
例えば、そらで一連の流れを言えるかどうか確認したり、CATOの学習用動画を何度も視聴するのも有効です。
しかし、友達と練習を積んでおかないと、次のことが生じる可能性があります。
- 間違ったやり方を修正できない。
- 打診や反射など、「コツ」や「うまくいかなかった時の対処法」を共有できない。
- 有益な情報を得られない。
たとえば、肝臓の打診・触診や脾臓の打診・触診を間違った箇所や間違ったやり方で行っている学生は少なくありません。友達や先生に見てもらえば、その場で修正できます。
また、「採血で逆血が来なかったとき」や、「項目を飛ばした・間違えたとき」などのトラブル対応も、本番でパニックにならないよう友人や先生とあらかじめ想定して確認しておくことで、万が一の時も落ち着いて対応することができます。
さらに、情報通の友人から何らかの有益な情報を得られる可能性もあります。
自分だけでは忘れていたこと、知りえなかったことを、他者と練習することで認識することができます。
【誤った手技で覚えてしまわないために☞1人練習で基礎を固めたら、必ず友人や先生と練習をしてください。】
【失敗例③】 試験形式を理解していない人

知識や手技が十分あっても、試験形式はきちんと理解しておくのが大事です。
OSCEについてよく知らないまま受験してしまう学生によくある失敗は、次のとおりです。
- 評価項目を十分理解できていないせいで、体感より評価が低い。
- 他の科目で挽回可能か、一発アウトかを分かっていないせいで、再試験に。
試験では、評価者が何を見ているかを知っておいたうえで練習をする必要があります。
「時間内に終わった、与えられた項目は全部できた!」と思っていても、「所見の言い忘れ」や「配慮不足」、評価者に対する”わかってますよ”アピールが不足していたせいで減点されてしまっては、もったいないことです。
そのため、きちんと評価項目はあらかじめ確認しておき、それが普段の練習に反映されているかどうか、確認しておきましょう。
試験本番では緊張するため、言い忘れ、評価者へのアピールなど、そこまで意識を割くことができない可能性があります。
普段から評価者にアピールするつもりで練習し、体に覚えこませておくと安心です。
また、各科目の時間制限はもちろん、複数領域で相補的に到達判定を行うのか、単一領域で到達判定を行うのかというのことも、事前に確認しておいてください。
医療面接や救急は、間違いなく合格するために、よく練習しておきましょう。
【思わぬ減点や不合格を食らわないために☞評価項目を事前にチェック。本番と同じ流れを想定して練習しておきましょう。】
まとめ

毎年OSCEに落ちてしまう人の典型的なパターンは、
- 練習不足
- 一人練習に偏っている
- 試験形式を理解していない
の3つです。
逆に言えば、
- しっかり練習を積む
- 仲間と切磋琢磨する
- 形式を理解して臨む
この3つを徹底すれば、合格はグッと近づきます。
OSCEは、定期試験やCBTと違い、今までの知識量は問われません。
評価項目を理解し、どれだけたくさん練習したかがものをいう試験です。
病院のマッチングでも、CBTの成績を見るところもありますが、それよりもOSCEの点数を見ているところの方が多いそうです。
病院側としても、最低限国試に合格できるだけの知識があるならば、手技やコミュニケーションがきちんとしている医師を取りたいということですね。
Pre-CC OSCEは、今まで日の目を見れていなかった学生も挽回するチャンスです。
今回紹介した3項目には気を付けて、たくさん練習してくださいね。
流れを体に覚えこませて、安心して本番を迎えましょう!
👉 医学生道場はOSCE対策に対応可!医学生生活の不安や相談もOK!24時間メッセージ受付中!
FAQ(よくある質問)
Q1. CBTの点数が悪くてもOSCEに合格できますか?
A. はい。OSCEは知識よりも「患者対応」や「手技」が重視されます。練習を積めば、普段勉強が苦手だった学生でも高得点で合格できる可能性があります。逆に、勉強ができるタイプの学生でもOSCEでは点数が低かったり、不合格になってしまうことも起こりえます。ナメずにしっかり練習を重ねましょう。
Q2. OSCEの練習は一人でやっても大丈夫ですか?
A. 一人での練習も意義がないわけではないですが、それだけでは不十分です。本番までに必ず友人や先生と一緒に練習し、フィードバックやトラブル対応を学ぶことが大事です。
Q3. 試験形式はどこまで確認しておくべきですか?
A. 時間制限や評価項目、到達判定の方法(複数領域か単一領域か)は、確認しておきましょう。本番の流れを理解しているかどうかで、焦りや減点を防げます。