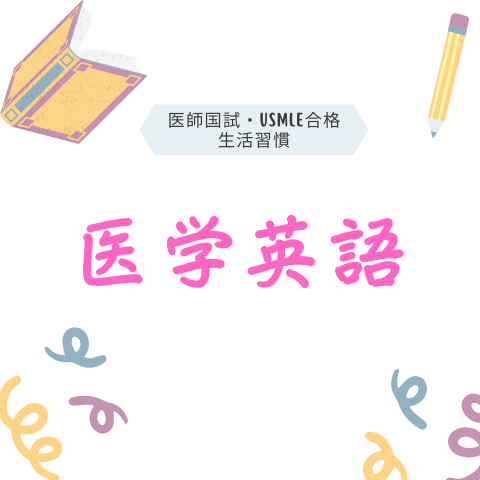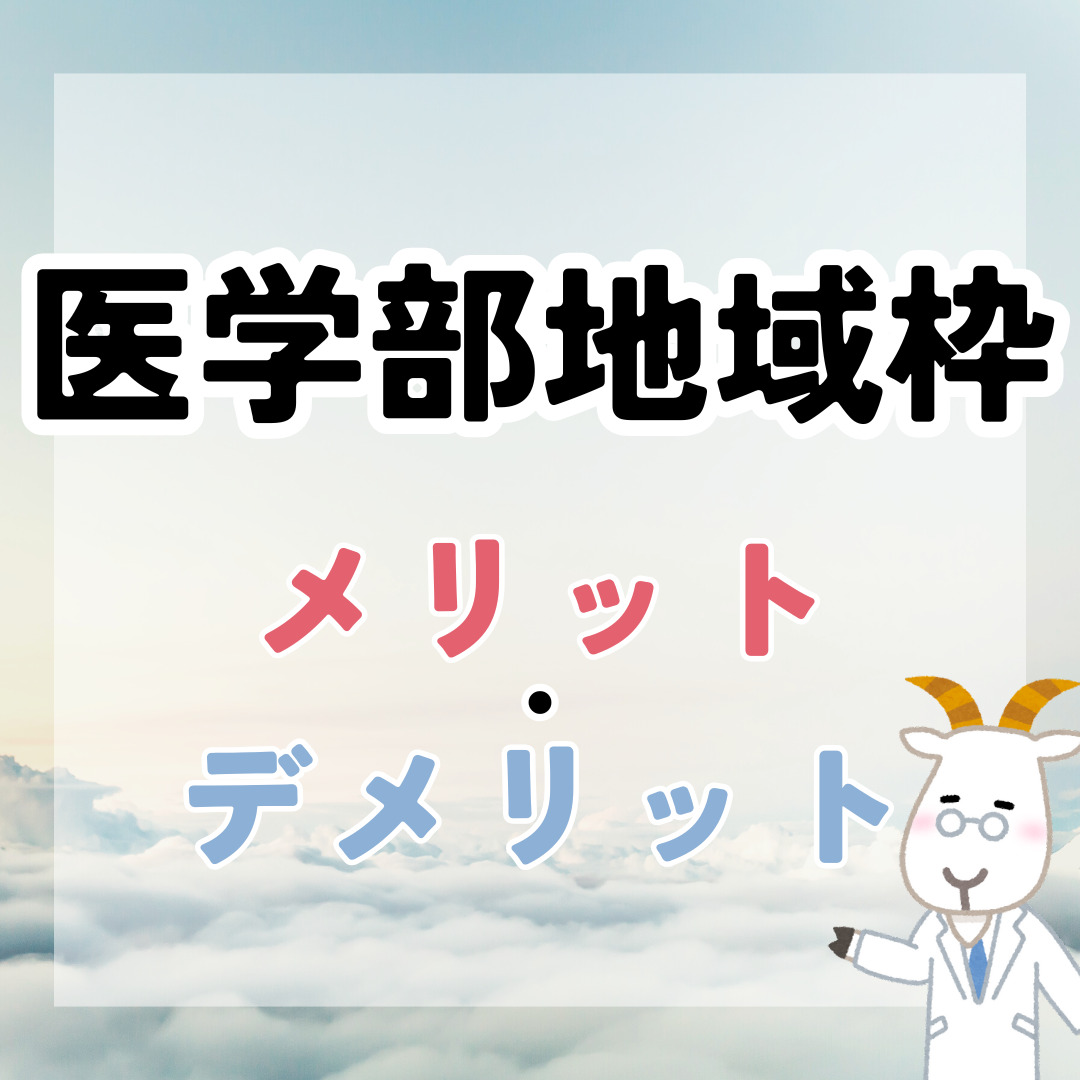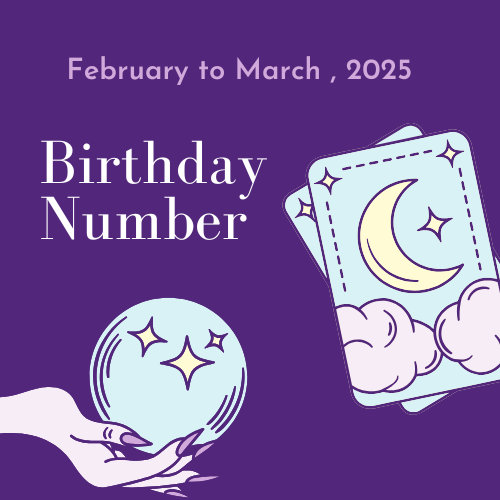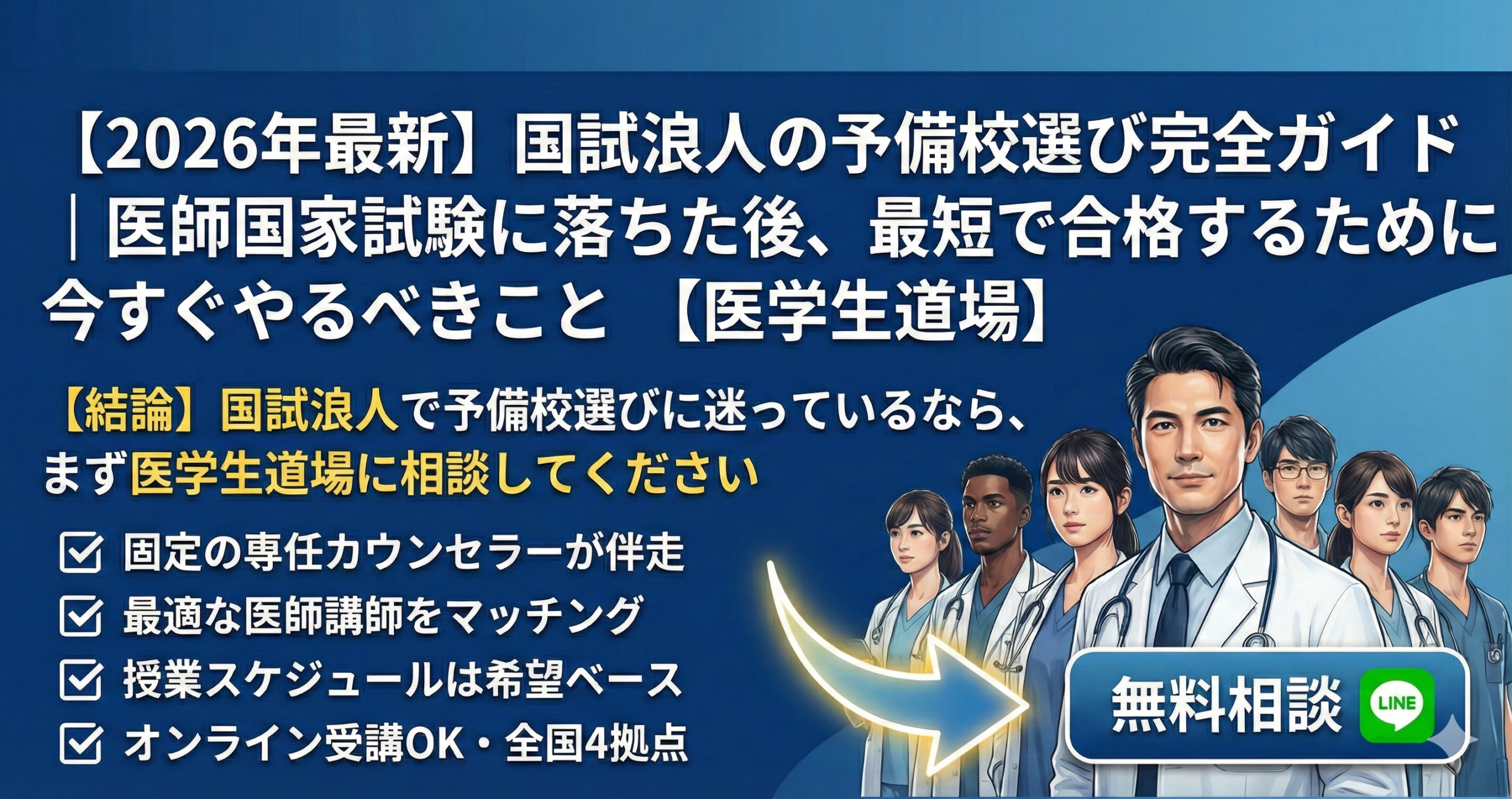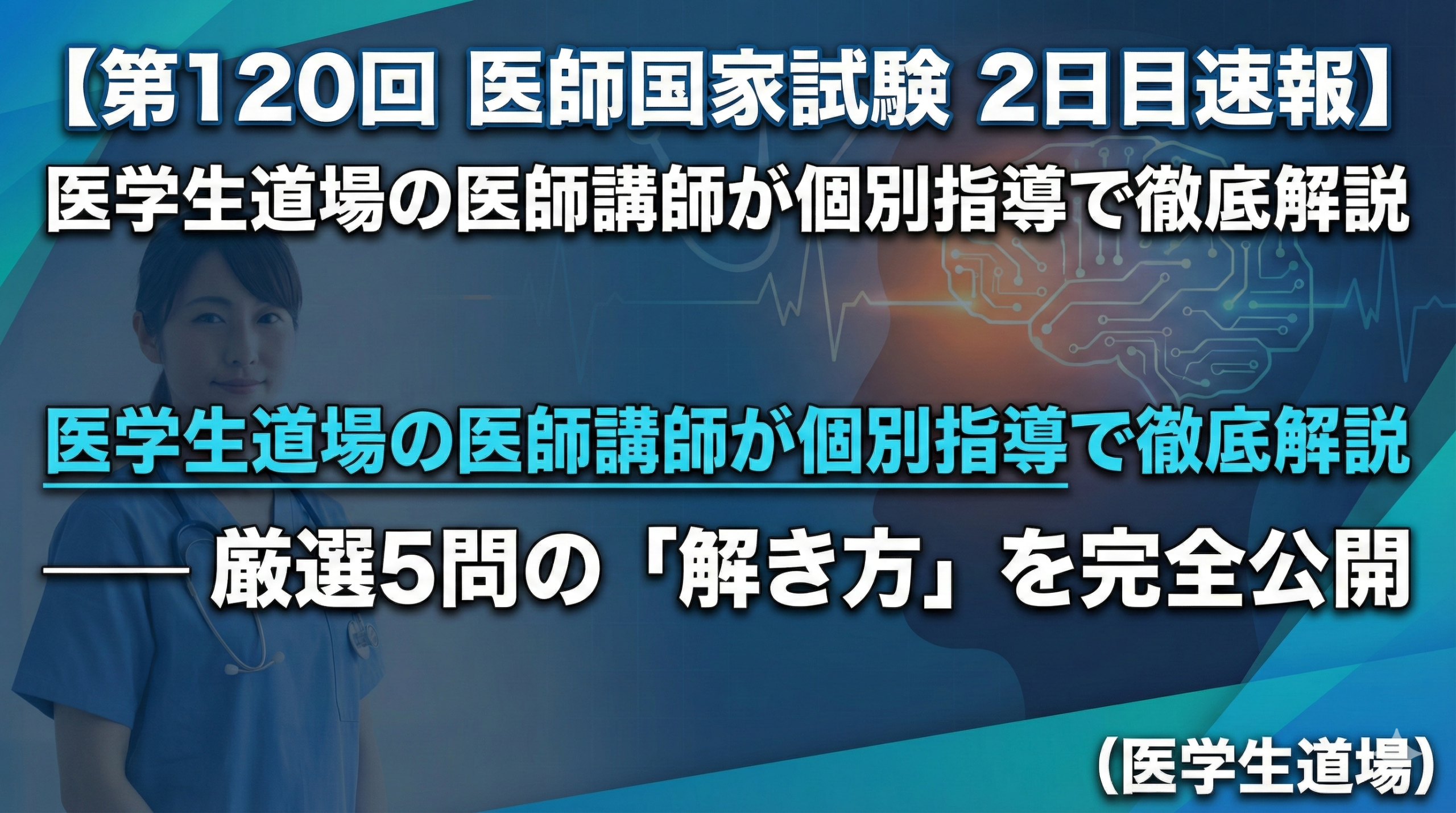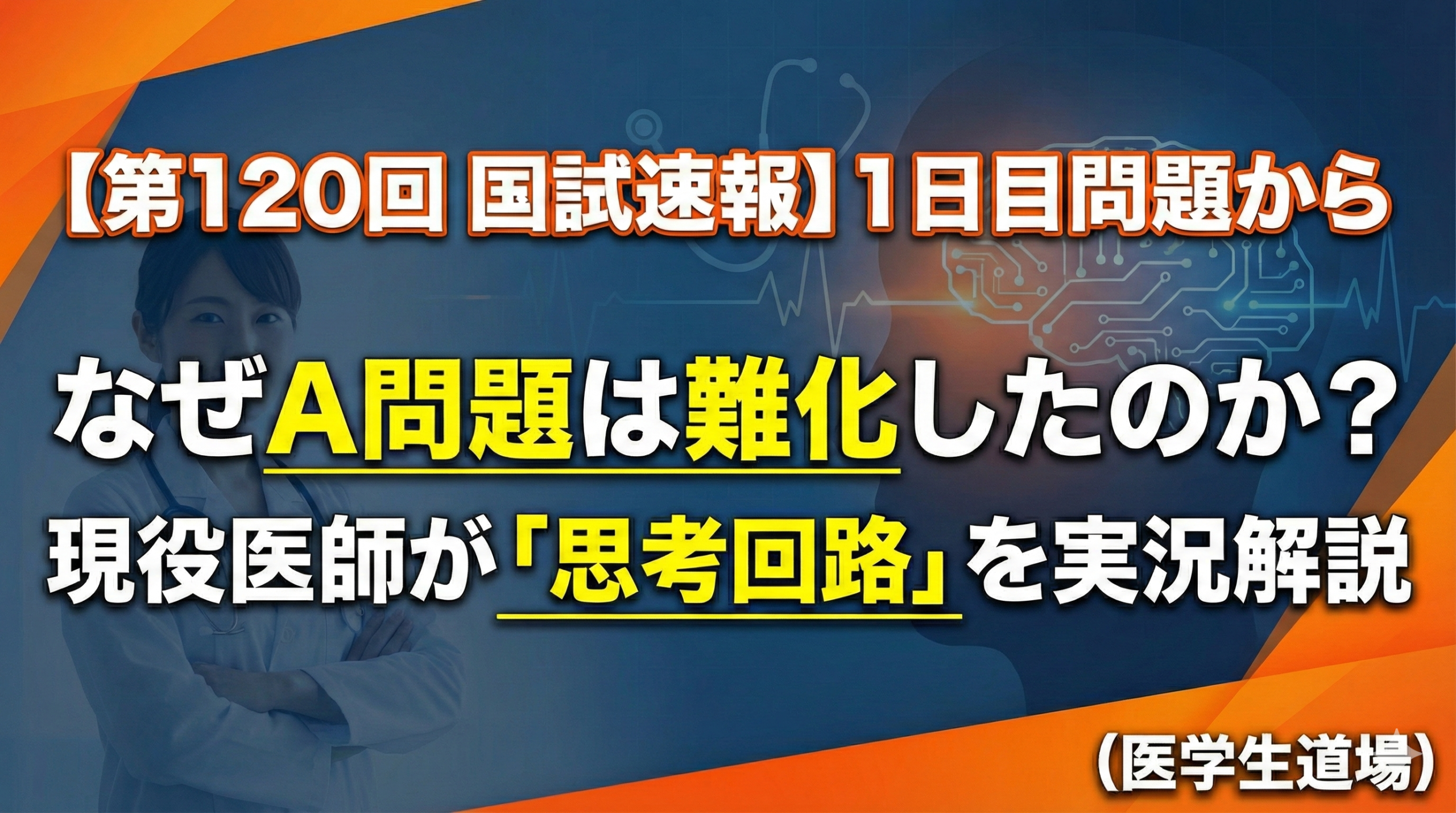目次
✓このブログのポイント
☞医学生にこそ金融リテラシーを身につけてほしい理由
☞奨学金返済のコツ
☞開業のために投資をしよう!
■筆者紹介
著者名:シマダ
所属:早慶三年生、医学生道場の学生アルバイト
資格・経歴:年間40本以上観劇、毎期多数ドラマ視聴、FP3級、証券外務員一種
アピールポイント、自己紹介:年間様々な舞台を観劇したりドラマ、アニメ、映画などを視聴しており、皆さんの好みに合わせたおすすめ作品をご紹介することができます!また、早慶に通う現役大学生として学習方法のアドバイスや大学生活の今をお届けします!
過去のブログ➡【医学生道場】忙しい日常やCBTの息抜きに! おすすめの2025年夏アニメ、【完全ガイド】FP3級の勉強法と対策まとめ 初心者でも合格できる効率的な方法とおすすめの理由、【医学生道場】医学生のための解剖学勉強ガイド:基礎から実践まで徹底解説!など
■ はじめに:お金のことを“今”から考える理由
医学生のみなさん、日々の勉強や実習、本当にお疲れさまです! 膨大な知識を暗記し、試験や実習でプレッシャーを感じながら過ごす毎日は、心も体も疲れ切ってしまうこともありますよね。
そんな中で「お金の勉強をしろ」と言われても、正直「今はそんな余裕ないよ…」と感じるかもしれません。
でも実は、お金の知識を少しでも早く身につけることは、将来の医師人生を大きく左右する大切な要素なんです✨

なぜなら、医学生の多くは卒業と同時に数百万円〜1,000万円近い奨学金を背負って社会に出ることが珍しくありません。その一方で、医師になれば収入は高くなるからと油断しがちですよね💦
でも、奨学金の返済、開業資金の確保、さらには結婚・出産・住宅購入など、人生の中でお金が必要になるタイミングは次々と訪れます。医師は「お金を稼ぐ力」が強い分、「お金をどう使うか・どう守るか」「どのように運用していくか」が他の人以上に問われる職業です。
そのためには学生のうちからでも、少しずつ簡単な金融リテラシーから学んでいくことが大切。そうすることで、返済の不安を減らすとともに、医者としてのキャリア選択の幅を広げ、将来のリスクにもばっちり備えられるようになります👀
ここからは、
・奨学金返済を効率的に進める方法
・開業資金やキャリアプランの基本
・初心者でもできる投資の始め方
・医師特有の税金・保険の落とし穴
という4つのテーマで、医学生・若手医師の皆さんに役立つお金の知識をわかりやすく解説していきます!一緒に将来に向けてお金の知識を蓄えていきましょう✨
■ 奨学金返済の計画を立ててみよう!
医学部の学費は、想像以上に大きな金額がかかります。私立医学部であれば、6年間で学費だけで2,000万〜3,000万円近くになる大学も珍しくありませんよね😿
これに加えて、教科書代や実習用の白衣・器具代、国家試験対策の予備校費用などを含めると、さらに数百万円は必要です。国公立に通っている方は私立医学部と比べて授業料は比較的安いものの、6年間の生活費や家賃、交通費を考えると負担は決して軽くはないでしょう。
こうした背景から、卒業時点で500万円〜1,000万円程度の奨学金を抱える医学生は少なくありません。なかには、自分や家族で借りた教育ローンも併せて、1,500万円を超える負債を背負ってしまう人もいます。
研修医になれば収入は得られるとはいえ、社会人生活のスタートラインでこれだけの負債を抱えている、という事実は心理的なプレッシャーも大きいはず。

だからこそ大切なことは、「自分が借りている奨学金の総額をきちんと把握すること」✨
なんとなく「いくらかわからないけどどこかから借りているなあ」という曖昧な認識のまま就職してしまうと、返済額や返済期間を知らずに日々の生活費をやりくりする羽目に💦
そのようにずるずると返済を続けてしまうことで、「思っていたより返済が重い!」と後悔するケースが多いのです。
✅まずは「見える化」から始めよう
予め奨学金の総額、利率、返済期間をしっかり書き出して、「自分の返済計画を見える化」しておくことから始めましょう!全体像が分かると安心ですよね✨
例えば:
・日本学生支援機構(JASSO)第一種奨学金:無利息。利息がない分、返済額は借入額そのまま。
・JASSO第二種奨学金:年利0.1〜0.3%程度と低利ではあるが、返済期間が長いと利息もじわじわ増える。
・大学独自・自治体奨学金:条件付きで返済免除のケースもあり、勤務地域や診療科の選択で返済額が減らせる可能性もある。
など、一口に奨学金と言っても様々な機関、形態のものがあります。
まずは、これらを一覧表にして「総額がいくらなのか」「毎月どこにいくら返済するのか」「完済は何年後か」を明確にしましょう!
これを把握しているだけでも、将来への漠然とした不安が減り、目の前のキャリア選択がしやすくなります☺
✅無理のない返済プランを立てる
初期研修医の給与は月額20〜30万円ほど。手取りはそこから税金や保険料が引かれ、さらに家賃・食費・交通費・教材代を払うと、自由に使えるお金はそれほど多くありません。
そんな中で無理な返済計画を立ててしまうと、精神的にも生活的にもより苦しくなってしまいます😿
そこでおすすめなのが、「最低返済額をコツコツと返済+収入が増えたら繰り上げ返済」という方法です!
・毎月の支出を考慮しながら、現実的な返済額を設定する
・専攻医や勤務医として収入が増えたら、その分を繰り上げ返済に回す
・ボーナスをもらえる職場なら、一部を返済に充てて利息を減らす
このように返済の仕方を自分の経済状況に応じて柔軟に変えていくのがおすすめ!
無理なく少しずつ元本を減らすだけで、返済総額はぐっと減り、精神的な負担も軽くなるはずです☺
✅奨学金の減額・免除制度を調べる
意外と知られていないのが、奨学金返済の減額や免除制度です。
・地方自治体や特定の病院には「一定期間勤務すれば返済が免除される」制度がある
・経済的困難や病気などの事情があれば、返済猶予や減額が可能
・JASSOも、返済額を一定期間減らせる「減額返還制度」を用意している
とても有用な制度ですが、「初耳だった!」という人もいるかもしれません。こうした制度を使うと、計画が大きく変わり返済が楽になる人も多いはず😲
勤務先やキャリア選択を考える上で、返済免除や支援の制度も視野に入れてみると良いでしょう。
✅借金をネガティブに捉えすぎない
「奨学金=借金」という言葉に抵抗があるかもしれませんが、これは自分の未来に対する先行投資だとポジティブに考えてしまいましょう!
むしろ問題なのは、「知らない」「把握していない」まま社会人生活を始めてしまうこと💦
数字をしっかり把握し、無理のない返済プランを立てれば、奨学金は決して人生を縛る足かせにはなりません!むしろ計画的に返済する習慣を持つことで、お金の管理力が自然と身につき、後のキャリア選択でも役に立ちます。
■ 開業資金:夢のクリニック開業にはいくら必要?
医師のキャリアは、他の職業に比べても本当に多彩で魅力的です☺
大学病院で研究・教育を行いながら一つの分野を極めて専門医を目指す道もあれば、地域医療を支える総合診療医として勤務する道、さらには自身でクリニックを開業して経営者になる道など、様々な道があります。どの道を選ぶかによって必要なスキルや働き方だけでなく、「お金の使い方や貯め方」も大きく変わってくるのがポイントです!

✅医師にとって夢の「開業」とは何か
開業は、医師なら誰もが一度は考える選択肢かもしれません。
「自分の理想の診療をしたい」「働き方の自由度を高めたい」「地域のニーズに応えたい」といった理由で、30代後半〜40代前半で開業を決断する医師も少なくありません。しかし、そこには現実的な資金の壁があります。
例えば、一般的な内科クリニックを開業する場合、4,000万円〜6,000万円ほどの初期投資が必要だといわれています。
かかる費用の例として、
・物件取得費(賃貸なら保証金、購入なら土地・建物代)
・医療機器や診療台、レントゲン、電子カルテなどの設備投資
・スタッフ採用・研修にかかる費用
・広告・患者さんを集めるためのマーケティング費用
などがあげられます。
さらに、開業してすぐに患者さんが集まるとは限りません。開業から安定経営までの間は赤字が続く可能性もあり、その赤字期間の生活費や運転資金も考慮する必要があります。
こうした金額を個人で全額貯めるのは難しいため、多くの医師は銀行などの金融機関からの開業ローンを利用します。
そのため、若いうちから金融知識を学び、ローンや投資について理解を深めることは医者を目指す皆さんにとって必須なのです!
✅若いうちからできる開業準備
開業を目指すのであれば、研修医や若手医師の段階から次のような準備を少しずつ進めておきましょう。
・経営感覚を磨く:クリニック経営には収支管理やスタッフマネジメントの知識が必要です。若いうちから経営に関する本やセミナーに触れておきましょう!
・投資・資産運用を学ぶ:開業時の資金繰りを助けるためにも、小額からでも給与の一部を投資に回して資産を増やす習慣を身につけましょう。
・人脈を作る:金融機関や医療コンサルタント、開業経験者とのつながりは開業を目指す際の後ろだてに直結します。
・理想の診療スタイルを考える:どの地域で、どの診療科で、どのような患者さんを対象にするのか、きっと皆さんの理想の病院像があるはず🔍ビジョンが具体的であるほど計画が立てやすいです。
✅「開業資金を準備する=夢を現実に変える第一歩」
開業資金というとハードルが高く感じるかもしれませんが、これは「夢を叶えるための投資」です。漠然と「お金が足りないから無理」と諦めるのではなく、今から小さく積み立て、金融の仕組みを理解すれば、数千万単位の資金調達も現実的な選択肢になります☺
逆に、キャリアや資金面を考えた際に「開業は考えない」と決めたとしても、資産形成の基礎を学んでおくことで、ライフステージの変化にも柔軟に対応できるようになりますよ!
■ 投資入門:月1万円でも「お金に働いてもらう」
「投資」という言葉を聞くと、「難しそう」「お金持ちがやること」「損したら怖い」と感じる人も多いのではないでしょうか?
特に学生や研修医のうちは収入も限られているため、「自分にはまだ関係ない」と思ってしまうのも無理はありません💦
でも実は、投資は「お金がたくさんある人」だけのものではないんです!
むしろ、若いうちから少額でもコツコツ積み立てを始める方が、時間を味方につけて資産を大きく育てられる可能性があります。

✅投資を始めるなら「つみたてNISA」と「iDeCo」がおすすめ
今の日本には、初心者でも安心して投資を始められるお得な制度が整っています!筆者が投資初心者の方におすすめしたいのは、つみたてNISAとiDeCoです🔍
・つみたてNISA
年間40万円までの投資で得た利益が非課税になる制度。普通の証券口座で投資をすると、運用益には20.315%の税金がかかりますが、この制度を使えばその税金がゼロに!
月3万円まで投資可能ですが、まずは月1万円からでもOK。対象商品も金融庁が選んだ長期投資向けの投資信託だけなので、初心者でも安心です。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金のための積立制度。最大のメリットは、掛け金が全額所得控除になること。つまり払った分だけ所得税や住民税が安くなるんです。医師になった後は収入が増え、税金の負担も大きくなるので、節税メリットを最大限活用できます。
デメリットは60歳まで引き出せない点ですが、老後資金を確実に貯めたいならiDeCoは最強の制度といえます。
✅まずは「証券口座を開設」から
投資を始めるには証券口座が必要です。今はネット証券(SBI証券や楽天証券など)で簡単に口座を開けるので、時間があるときにサクッと申し込んでみましょう!
✨最初の一歩はこれだけでOK
1ネット証券で口座開設
↓
2つみたてNISAを設定
↓
3インデックスファンドを1本選び、月1万円を自動積立
まずはここから始めてみましょう!くわしくはこちらから確認してみてくださいね🔍
✅投資は「お金の不安を減らすため」にやる
「投資=お金儲けの手段」と思うかもしれませんが、実は逆の考え方もできますよ👀
・お金をただ貯金しておくとインフレなどで価値が左右されてしまう
・将来の教育費や老後資金が不安に
・医師はキャリアチェンジや開業などでまとまったお金が必要になることが多い
こうした将来のリスクや不安に備えるために、投資は「お金に働いてもらう仕組み作り」なんです✨
✅学生・研修医でも投資を学ぶメリット
忙しい医学生や研修医が投資を始めるメリットは、単にお金を増やすことだけではありません。
・金融リテラシーが身につく:お金や経済の仕組みに強くなる
・将来のキャリアに活かせる:開業資金計画やローンの理解に役立つ
・早く始めるほど有利:少額でも時間を味方にできる
研修医時代は貯金も投資もなかなか難しいかもしれませんが、1,000円でも5,000円でも「習慣化」することに価値があります☺
■ 税金・保険・ライフプラン:医師だからこそ必要な知識📚
医師という職業は社会的にも収入的にも恵まれているように見えますが、その分だけ税金や保険など「お金に関する仕組み」の影響を強く受けてしまう職業でもあります。
特に、学生時代にお金の知識を持たないまま社会に出てしまうと、「せっかく高収入なのに税金でごっそり持っていかれる…」「よくわからない保険や投資商品を契約してしまった…」という落とし穴にはまる人が少なくありません💦
これは、忙しい医師が「目の前の業務に追われて、金融知識を学ぶ時間がない」ことが大きな原因。だからこそ、医学生や研修医のうちから少しずつ税金や保険、支出管理について知っておくことがとても大切✨
ここでは、医師だからこそ注意すべきポイントを具体的に紹介します!
✅税金の仕組みを理解しないと損をする
初期研修医の年収は手取りで月20万〜30万円程度なので、学生時代に比べると収入は増えても「税金が重い」という実感はあまりないかもしれません。
ですが、医師としてキャリアを重ねると年収は一気に上がり、30代で1,000万円を超えることも珍しくありません。その結果、所得税・住民税・社会保険料などの負担が急増してしまうことも💦
例えば、年収1,000万円を超えると、給与所得控除や各種控除を差し引いても課税所得はかなり高くなり、所得税率は33%、住民税と合わせると約40%近い税率になることもあります。つまり、稼げば稼ぐほど、同じ1万円でも税金で引かれる割合が大きくなるのです。
だからこそ、早いうちから税制を活用した対策を学んでおくことが重要です✍
■ 今からできる!金融リテラシーを鍛えるステップをおさらい📖
1,奨学金の状況を整理:借入額・金利・返済期間を「見える化」👀
2,キャリアとお金をセットで考える:「勤務医で一生?」or「開業?」自分の理想を言語化してみよう
3,毎月1万円から投資スタート:初心者におすすめのNISAやiDeCoを利用
4,税金・保険の基礎を勉強:確定申告や所得控除の仕組みを知ることが第一歩👣
5,情報源を選ぶ:金融リテラシーはネットの断片情報でなく本や講座で学ぼう!
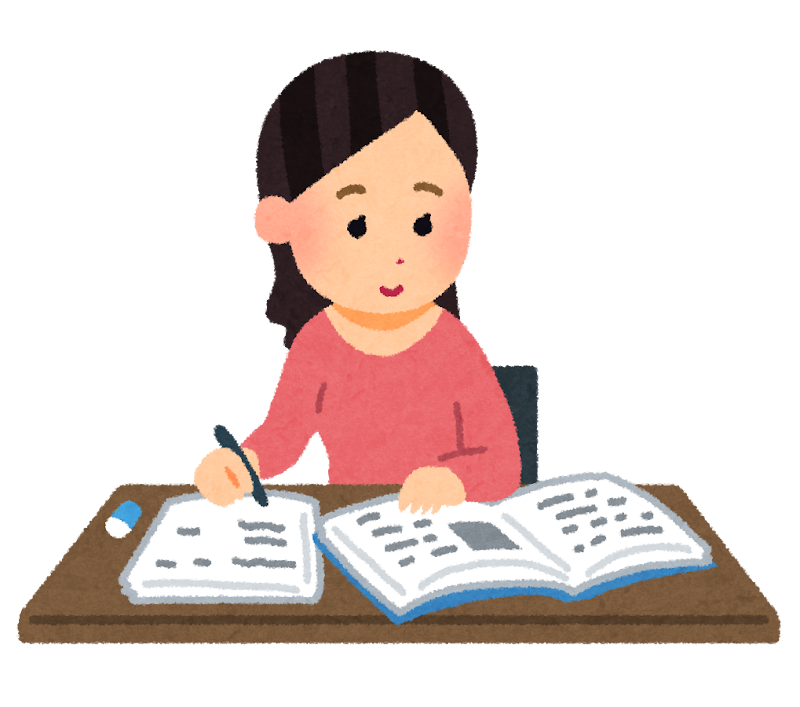
■ よくある質問
Q1. 研修医のうちはお金がカツカツで投資まで手が回りません…。それでも始めるべき?
💡 無理のない範囲でOKです!
研修医の時期は家賃・生活費・教材費などでお金に余裕がないのが普通です。でも、普段の生活を節約することで「月1,000円」「月5,000円」など少額でも投資や貯金を始めることが大切です!
金額よりも「積み立てを続ける習慣」を作るのが目的。将来の余裕資金ができたとき、すぐ増額できるので、今は習慣作りと割り切りましょう☺
Q2. 開業を目指すならいつからお金を準備すればいい?
💡 研修医の段階から「小さな積立」を始めてOK!
開業資金は4,000〜6,000万円が目安👀もちろん銀行のローンを活用できますが、「開業資金の自己資金比率」が高い方が金融機関からの信頼が高まります。
また、早めに投資や積立を始めておくと「複利の力」で自己資金を育てられます。30代後半〜40代で開業を考えるなら、20代から少しずつ準備するのが理想です✨
Q3. 忙しくて勉強する時間がない!金融リテラシーはどうやって身につければいい?
💡 スキマ時間の「ながら学習」がおすすめ!勉強の合間や移動時間など、月1冊ずつ金融や投資の本を読むだけでも、1年後にはかなり知識がつきますよ✨
■ まとめ
医師は一見「お金に困らない職業」のように思われがちですが、実際には奨学金の返済や開業資金、税金など、多くの金融課題に直面します💦
だからこそ、学生のうちからお金の知識を持っておくことが将来の安心につながります!
お金はただ稼ぐだけではなく、「計画的に管理し、増やす」力が必要です。忙しい医学生や研修医でも、月1万円からの投資や、奨学金の返済シミュレーションといった小さな行動ならすぐ始められます✨
未来の自分をラクにするために、今から少しずつ金融リテラシーを身につけていきましょう!
■最後に
このブログを執筆したスタッフが所属している医学生道場では、医学部に在学する医学生を対象とした個別指導を行っています。身近に医学部の学習や試験についてつまづいていたり、誰かに相談したいと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
そのような方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に医学生道場にご相談ください!