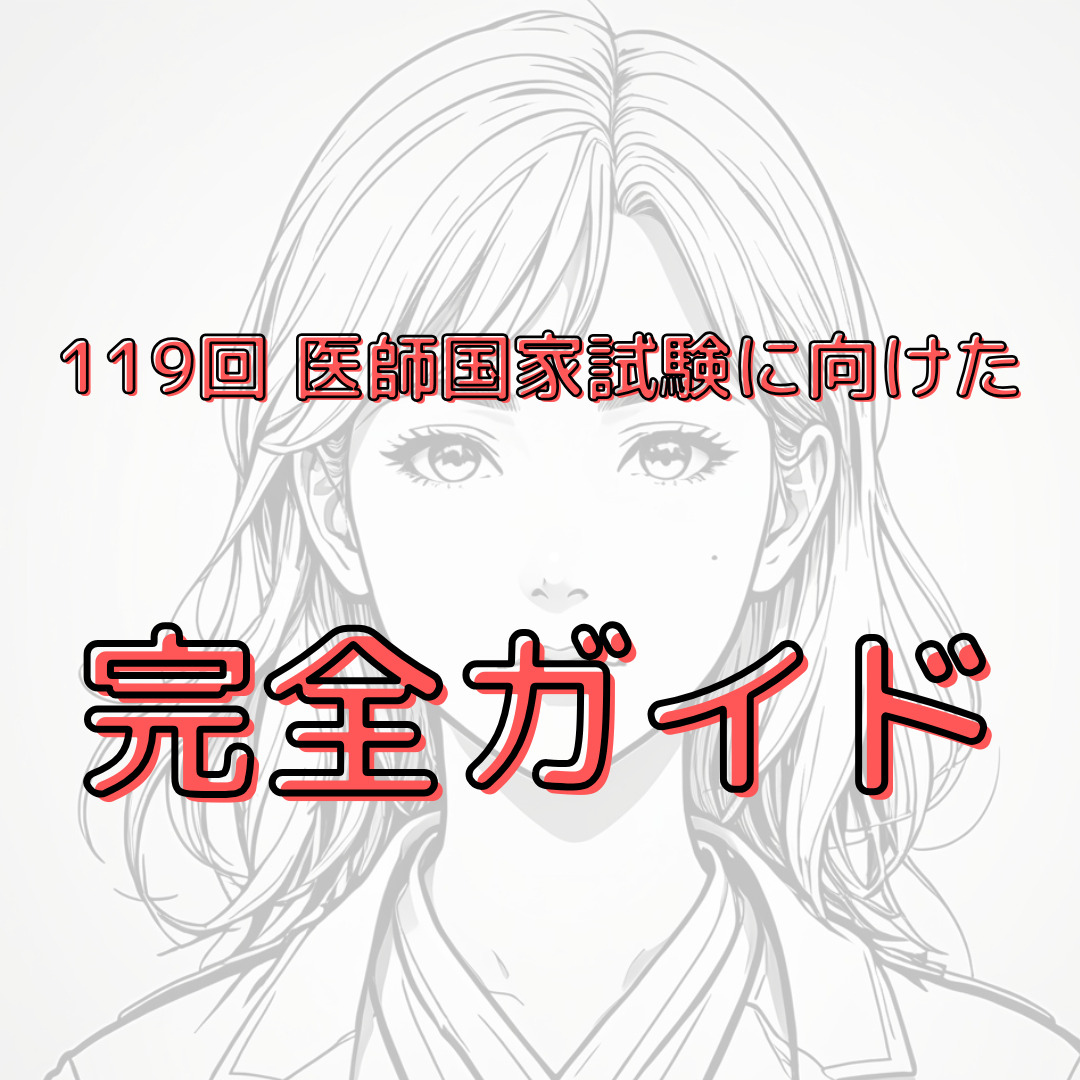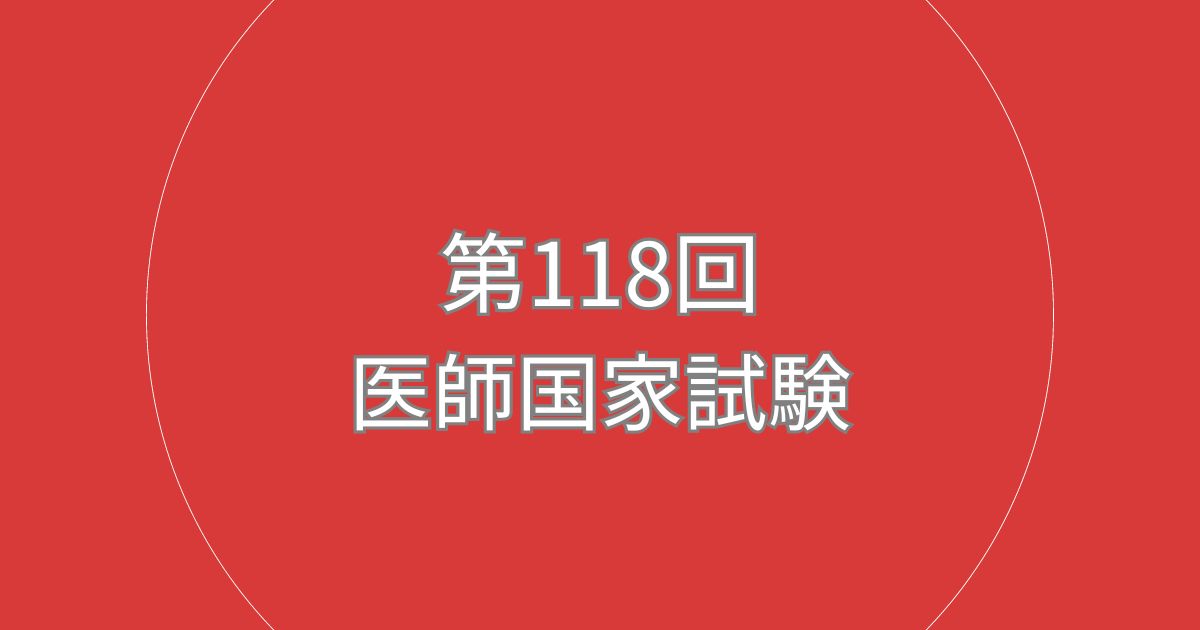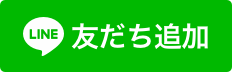
目次
はじめに
皆さんこんにちは医学生道場です。 前期で落としてしまった試験の再試におびえてるのではないのでしょうか。今回は私がどのようにして再試までのたった30日で立ち直ったのかをご紹介します。ぜひ最後まで読んでください。
今回のブログの内容
💡どのような気持ちだったのか
💡勉強のプランニング
💡具体的な勉強方法の変革
🖊 著者紹介
SH 都内私立医学部3年生
現在所属部活主将。2年の前期で成績を大幅に落とすも、対策を講じ後期の期末で成績を上げ無事進級。自分自身、不器用なためプライベートと勉強と部活の両立を目指し日々模索中。ブログでは自身の経験を活かしてどのように成績を上げればよいのかや効率的な勉強方法を紹介。現在、来年のCBTに向けて情報収集中。
☛執筆ブログ
医学部の解剖学って本当にきつい?!乗り越えるコツと試験合格勉強法【医学生道場】
医学生道場【医学部再試験】基礎医学の再試で「詰んだ」と思ったあなたへ 今からできる最短合格ルートとは?
■1. 絶望の再試験通知
「再試験対象:内分泌代謝学」
その文字を見た瞬間、頭が真っ白になりました。
大学ポータルに映る赤い文字。
“あんなにやったのに、なんで落ちたんだろう…”
いや、冷静に考えれば“あんなに”なんて言えるほどやっていなかったとおもいます。授業には出ていたけど、要点を理解せずに過去問をなぞっただけ。講義中も「あとでまとめよう」と思って結局そのまま。そんな積み重ねの結果が、今目の前に突きつけられたのだと今になって思います。
再試験の日程は、ちょうど30日後。
このままでは確実に留年。医学部で留年すれば、卒業が一年遅れ、国家試験の受験も先送りになる。
正直、終わったと思いました。
でも、その夜。絶望しすぎて眠れず、YouTubeをなんとなく開いた時、目に飛び込んできた言葉があった。
「人は、追い詰められたときにしか、本当の意味で変われない。
変わらなきゃと確信した瞬間でした。
■現状を“数字で”直視する(1〜3日目)

最初にやったのは、“今の自分の位置”を正確に把握することでした。まず自分の中での理解度を明確にするために5段階中自分の理解度はどのくらいなのかを以下のように書き出しました。
- 内分泌の構造と機能:理解度★☆☆☆☆
- ホルモン合成とフィードバック:理解度★★☆☆☆
- 甲状腺・副腎・下垂体系:理解度★☆☆☆☆
- 糖代謝異常・糖尿病:理解度★★☆☆☆
- 性ホルモンと月経周期:理解度★★★☆☆
- カルシウム代謝:理解度★★☆☆☆
改めて数字で見ると、ほぼ全滅に近く自分でも驚きました。
でも、同時に「どこを重点的にやればいいか」が明確になりました。
次に、過去3年分の再試験問題を分析。
「どの先生がどのくらいの割合でだしているか」のパターンを抽出しこれをもとに、「一番担当している授業が多い先生つまり出題数が多い先生ところだけを完璧にする」戦略に切り替える。全範囲は完璧にするという目標は捨てました。
■勉強の“仕組み”を作る(4〜7日目)
これまでの勉強は、まさに「気合いと根性」タイプでした。時間をかければかけるだけ勉強の成果がでると考えていました。でも、それでは続かないことを、何度も経験してきました(笑)
だから今回は、“気合いに頼らない”勉強システムを作りました。
4〜7日目は、再試験・留年危機からの30日リカバリープランにおいて、勉強を“自動的に進む状態”へと整える重要な期間です。最初の3日で現状分析と優先順位づけが終わったら、この4日間で「やる気や気分に左右されずに学習が進む仕組み」を徹底的に作ります。人は誰でも集中力に波があるため、仕組みのない状態で精神力だけに頼ると必ず失速します。逆に、一度仕組みを作ってしまえば、学習は惰性でも前に進み、追い込みの時期ほど大きな差が生まれます。この仕組み化のポイントは三つあります。
第一に、時間の固定化
4〜7日目の間に「毎日・同じ時間に必ず勉強するコアタイム」を設定します。理想は90〜120分の集中ブロックを2回確保することですが、朝の1時間+放課後の90分といった形でも構いません。時間を固定することで脳が“この時間は勉強するものだ”と認識し、意志力を使わず自然に学習が始められるようになります。
第二に、学習手順の固定化
毎日の勉強内容を「迷わなくてよいレベル」まで具体化します。たとえば、
①前日の復習15分
②苦手単元の例題演習40分
③教科書該当箇所の理解整理20分
④過去問・類題を30分
といった“固定ルーティン”を作ることで、勉強開始までの意思決定を最小化できます。
第三に、環境の最適化
机の上を勉強以外のものを置かない状態に整え、スマホは別室かアプリロックを徹底します。さらに、使用教材を一式まとめておくことで、着席から学習開始までのタイムラグをゼロにします。
この4〜7日目で仕組みが整えば、その後の20日間の勉強効率が劇的に安定します。追い込まれた状況こそ、“仕組み化”こそが最大の武器になります。
■4. 知識を“点”から“線”にする(8〜20日目)

8日目あたりから、ただの暗記では限界を感じました。
勉強をしていると、「覚えたはずなのにテストになると思い出せない」という壁にぶつかることがあります。それは、知識が“点”のままで止まっていることが原因であることが多いです。単語や公式を暗記しても、それらが互いに結びついていなければ、必要な場面で引き出すことができません。そこで大切になるのが、知識を“点”から“線”へとつなげていく学び方です。
まず意識したいのは、新しく得た情報を孤立させないことです。「これは以前のどの知識と関係しているのか」「どういう流れの中で生まれた考え方なのか」と自分に問いかけるだけで、理解の深さが大きく変わります。点が線につながると、単語や公式が“ストーリー”として記憶に残り、思い出しやすくなります。
次に、教科書やノートの内容を図にして整理する方法があります。内容を関連ごとにまとめたり、因果関係や構造を矢印で結んだりすることで、知識同士の位置関係が一気に見えるようになります。これは複雑な内容ほど効果を発揮する学習法です。
さらに、実際の問題に触れることで、点が線として機能し始めます。問題の中では複数の知識が同時に必要になるため、「どの知識とどの知識がつながるのか」が自然と明確になります。アウトプットは知識を線化する最も強力なステップです。
知識が線としてつながり始めると、学習は一気に楽になります。理解が深まるだけでなく、記憶の定着もスムーズになり、応用力も養われます。点の暗記で限界を感じたときこそ、知識を線でつなぐ学び方を意識してみてください。それが成績を伸ばす大きな鍵になります。
特に内分泌は、臓器・ホルモン・疾患が有機的につながっている。
単発で覚えるだけでは、問題文の中で迷子になりました。
そこでノートを一新し、A3用紙に「ホルモンマップ」を描きました。
- 視床下部 → 下垂体 → 末梢臓器の流れ
- 各ホルモンの作用点とフィードバックループ
- 異常時にどの値が上がり、どれが下がるか
たとえば、副腎皮質ホルモンの異常を考えるとき、ACTHとコルチゾールの関係を線で結ぶだけで、疾患の分類(原発性・二次性)がスッと頭に入る。
こうした「線の勉強法」は、時間はかかるが圧倒的に記憶が定着しました。
この頃から、過去問を解くたびに「あ、このパターンはコレだ」と思い出せるようになりました。
■ 仕上げの10日間(20〜30日目
残り10日。ここからは試験本番を想定したトレーニングに切り替えました。
- 制限時間を設けて過去問を解く
- 間違えた問題は、原因と対策をセットでノート化
- 講義スライドを“目次だけ”見て内容を説明できるか確認
- 睡眠と食事を最優先
最終週には、点数が45点→68点→76点と上昇。
ついに合格ライン(60点)を超えた。
あとは当日、落ち着いて臨むだけでした。
■いま再試験を控える人へ
あなたが不安に押しつぶされそうになっている今こそ、
一番伸びる時期だと思います。
やるべきことを“削ぎ落とし”、
「今日、これだけやる」を明確に決めてください。
完璧じゃなくて大丈夫です。
毎日1歩、昨日の自分を超えられたら、それで十分。
30日という短い時間でも、人は変われます。あきらめずに挑戦しましょう
不安な方は医学生道場へ

医学生道場では、現役医師講師があなたに合わせた勉強法を提案してくれます。
- 試験で出題されやすい問題、過去問の傾向を効率よく整理できる
- 「ここのキーワードを押さえれば解答を導ける」など臨床問題の実践的なコツがすぐに分かる
- 一人では続けにくい勉強も、伴走してくれる環境があるから安心
👉 もしあなたが今、「留年かもどうしよう…」と感じているなら、ぜひ医学生道場に相談してみてください!