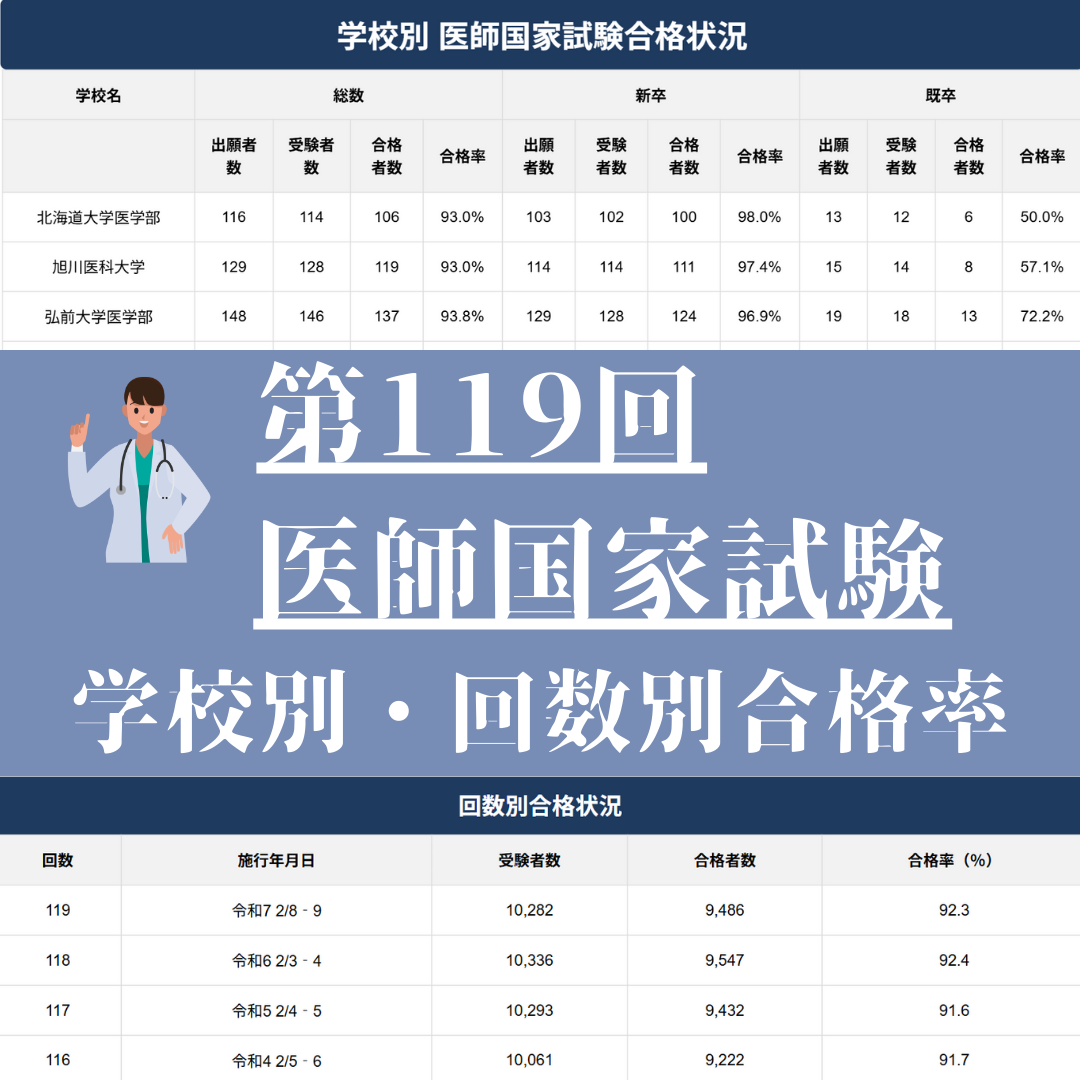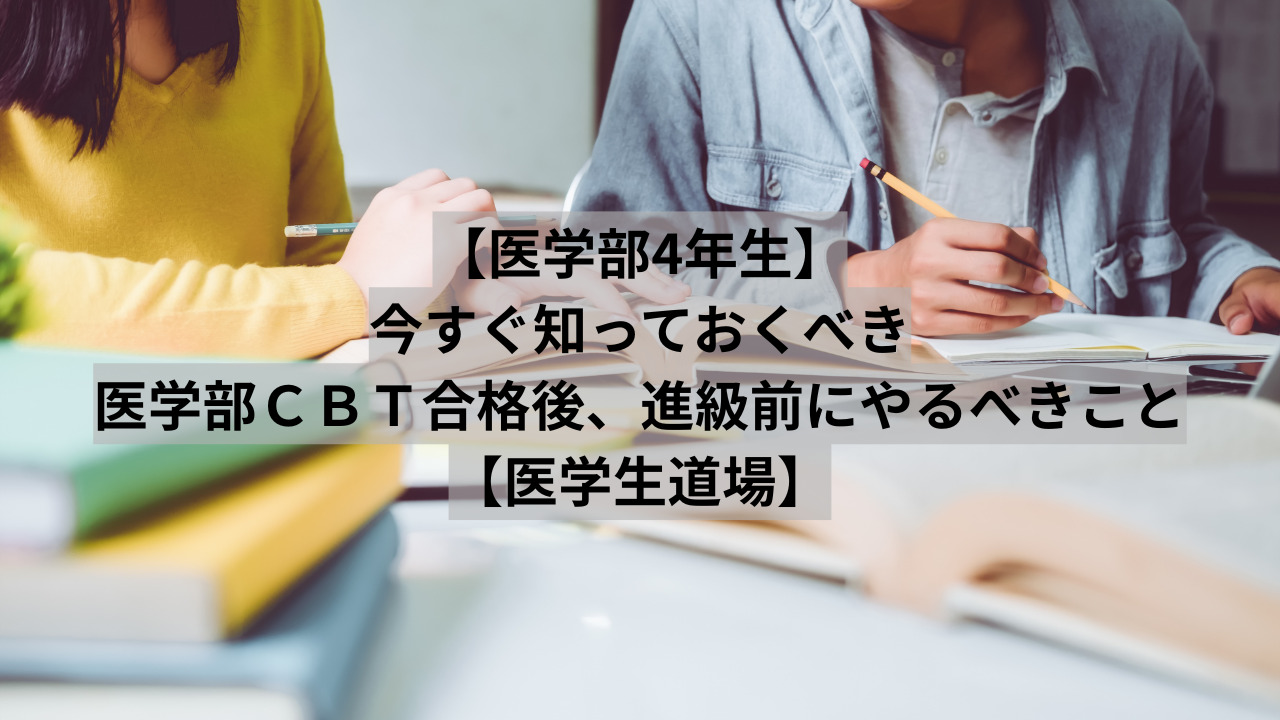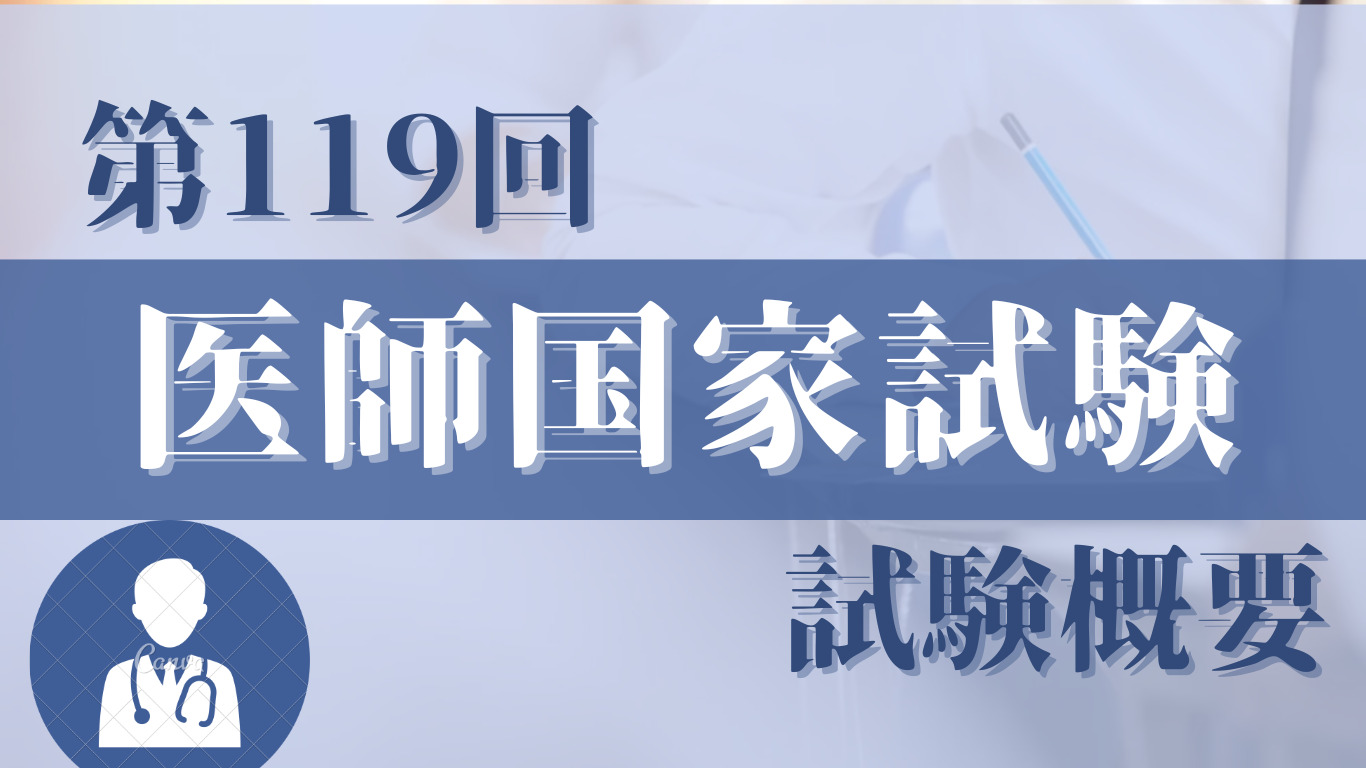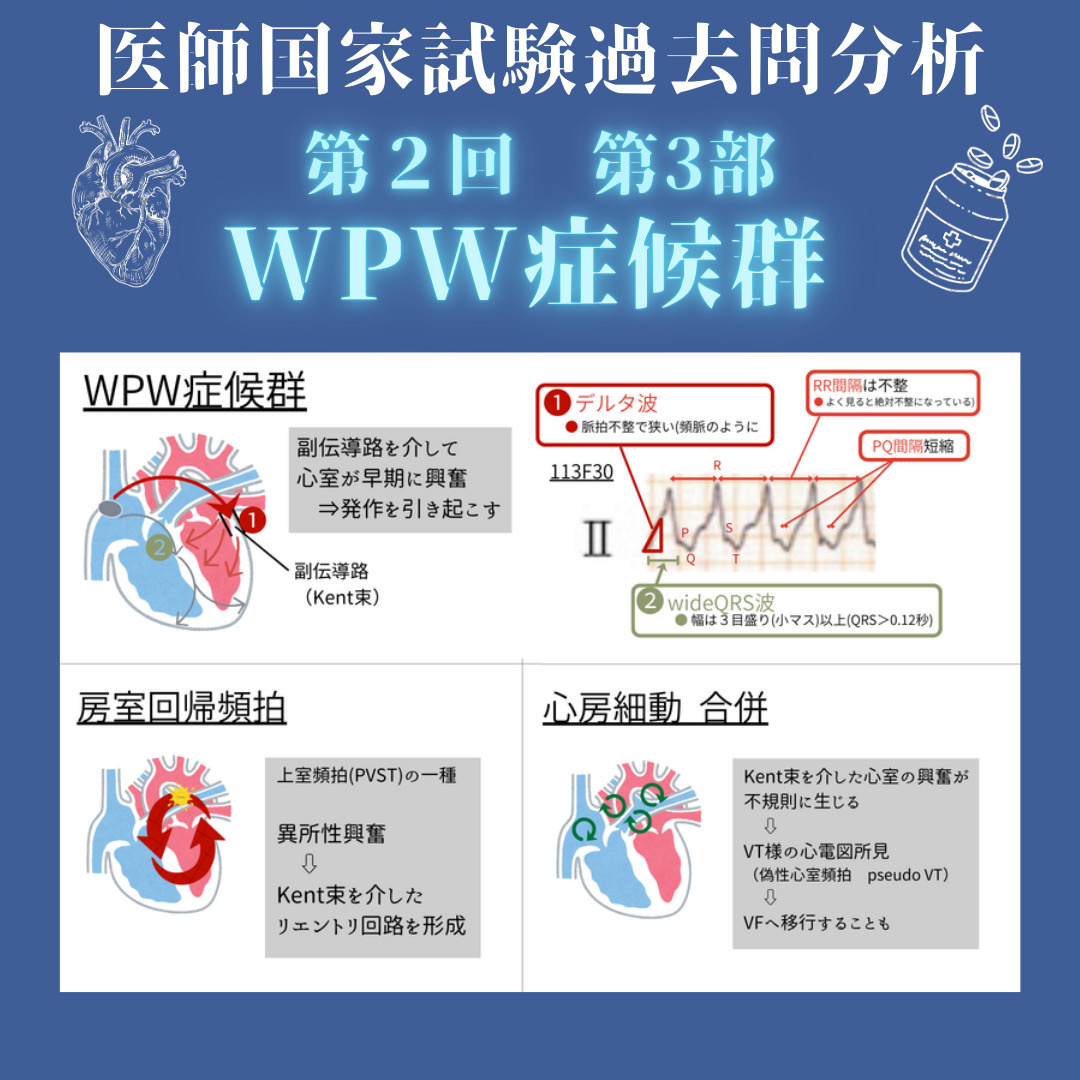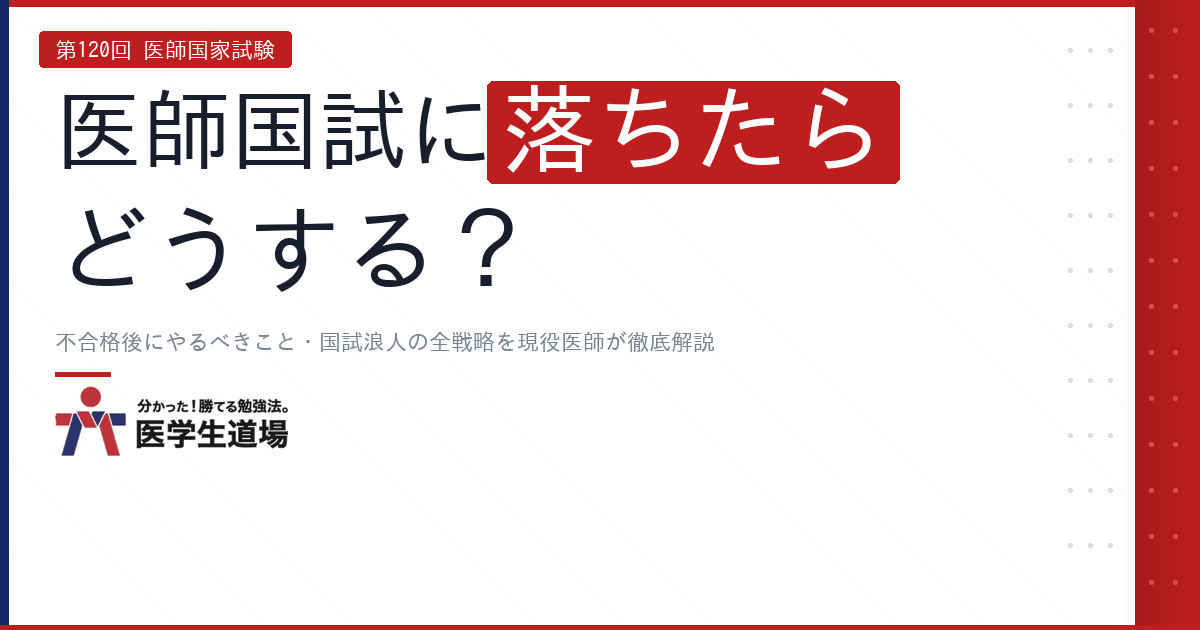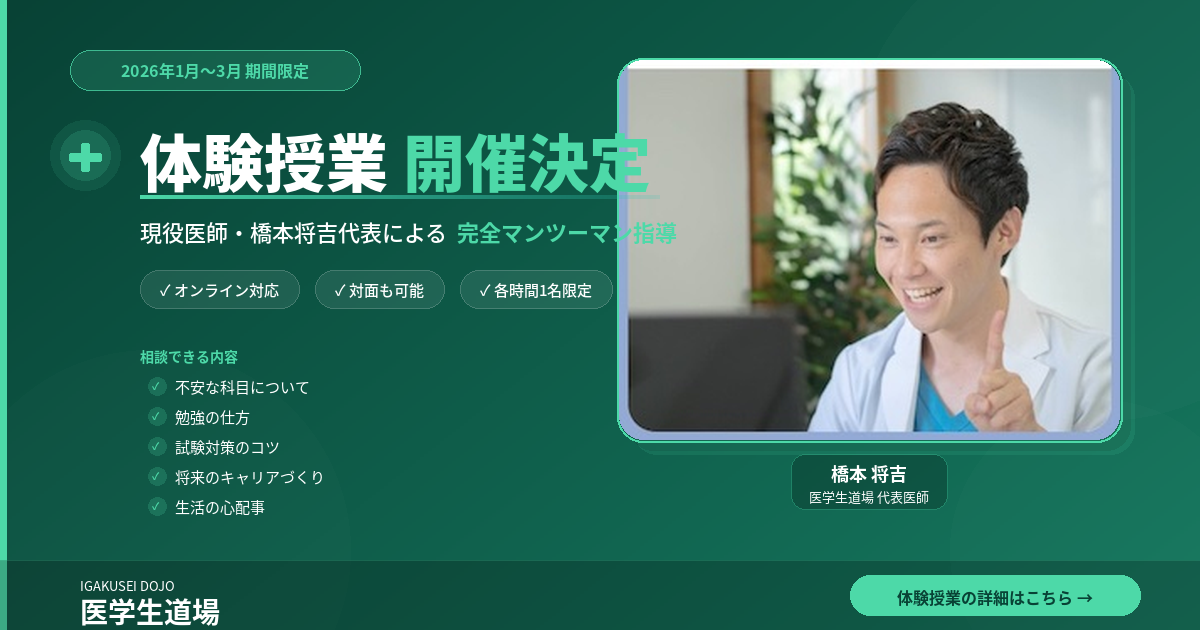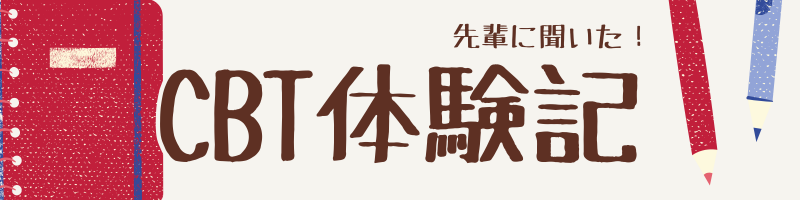
こんにちは!医学生道場です👐
CBT(Computer-Based Testing)は、全国の医学部生が通過する一大イベント。
でも、
「CBTっていつから始めるべき?」「何を使って勉強するの?」
といった悩みを抱える医学生も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、実際にCBTを乗り越えた2人の医学生にインタビューを実施し、リアルな体験談を語ってもらいました!
それぞれの体験を通して、勉強法や塾の活用法、当日のリアルな様子までお届けします。
この記事が、これからCBTに挑むあなたのヒントになりますように💫

|
おおしお みなさんが気になるであろうことをたくさん質問します!ぜひ最後までご覧ください♩ |
📌著者情報
おおしお
関東国立大学法学部 4年生
医学の専門知識はありませんが、だからこそ医学部のみなさんが見落としがちな視点や一般の人にもわかりやすい形で情報をお届けすることができます。医学の知識を学ぶ中で感じた疑問や気づきをシェアしていきます😊
(過去ブログ)
・【必見】2024年「医師の働き方改革」を分かりやすく解説
・【病理学】道場流の勉強法!2つのポイントで効果的な定期試験対策をしよう【医学生道場】
・【不安ゼロ!】授業は?受講料は?医学生道場に通う前に知っておきたいこと【医学生道場】
目次
まずは2人のCBT対策をざっくり比較!
| 項目 | Sさん | Wくん |
|---|---|---|
| 勉強開始時期 | 3年生の終わり頃 | 再試験が決まってから本格スタート |
| 勉強スタイル | 勉強の習慣化 | 短期集中 |
| 医学生道場の利用法 | 月ごとの学習計画+苦手対策授業 | 1週間ごとの計画+授業 |
| 使用教材 | QB、病気がみえる | QB |
| CBT当日 | プール問題で対策万全 | 時間配分⚠️ |
| 成功のポイント | 勉強の習慣化 | 環境の活用と勉強意識 |
インタビューでは、タイプの異なる2人の先輩医学生にお話を伺いました!
1人はコツコツと長期的に準備を進めた派、もう1人は再試験から逆転合格を果たした派。
スケジュールの立て方や塾の使い方、使った教材など、それぞれ全く異なるアプローチを取っていましたが、共通していたのは「自分に合ったやり方」を見つけていたことでした。
本編では、そんな2人の違いを詳しく掘り下げながら、CBT対策のヒントをたっぷりお届けしていきます!
CBTってどんな試験?
インタビューに入る前に、まずはCBTがどういう試験なのかについてお伝えします!
まず、CBTは、全国共通の試験で、各大学独自の試験ではありません。
医学部のCBT(Computer-Based Testing)とは、OSCEと一緒に行われる共用試験の一つで、臨床実習に必要な医学的知識を総合的に理解しているかを問う試験です。
出題範囲は4年生までに学んだ基礎医学、臨床医学、公衆衛生など幅広く、30,000問以上といわれる問題のプールからランダムに選ばれた問題を解くので、受験生それぞれに解く問題が異なる点が特徴です。
受験に当たっては、一人一台パソコンが用意され、全6ブロックに分かれている320問のテストを6時間かけて解いていきます。
一日中パソコンと睨めっこ、というなかなかハードな試験になるため、実はかなり体力面での勝負にもなってきます✊🔥
以前までは臨床実習開始直前である4年生の8~2月にかけて各大学ごとに実施されいましたが、現在は全国で実施時期が統一化され、8~9月頃までには受け終わるように定められました。
早期化によって、「思ったよりも早い!やばい💦」となっている医学生も少なくないかもしれません。
しかし、CBTの合格基準は、そこまで高くありません。
目安としては、IRT396前後(おおむね65%以上の得点率)が最低ラインだと言われています。(※ 大学によって若干異なります)
…と、ここで出てきたIRTという言葉。「何それ?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか?💭
CBTの評価方法『IRT』ってなに?
IRTは「Item Response Theory」の略語です。(日本語で「項目反応理論」)
簡単に説明すると、試験問題と受験者を公平に評価するための理論で、CBTで受験者ごとに違う試験問題が出たとしても、問題の難易度や正答率を考慮し、一律に同様に評価をすることができます。
つまり、IRTはCBT試験特有の偏差値のようなもの、ということです。
一般的には、『偏差値×10=IRT』とも言われています。
ということは!
CBT試験の合格基準IRT396は偏差値40未満程度ということになります。
「CBTは偏差値40を切らなければいい試験である」と聞くと、少し肩の荷が下りた感じがしませんか?😼
ですので、恐れず、過度に怖がらず、適切な対策を行っていくことが何よりも重要になってくるんです!
ちなみに、以下のブログでは『試験不合格の下位1割になってしまう人の特徴』を紹介しています!
「勉強の仕方などに不安がある…」という方はこちらの記事を参考にCBTの勉強の仕方を見直してみてください!
医学生の先輩2人に聞いてみた!
お待たせしました!それでは、いよいよ本題に入りましょう!
ここからは、CBTに合格経験のある医学生の方と一緒にお送りします。
今回インタビューに応じてくださったのは、以下の方々です👐
~ 今回話を聞いた医学生 ~
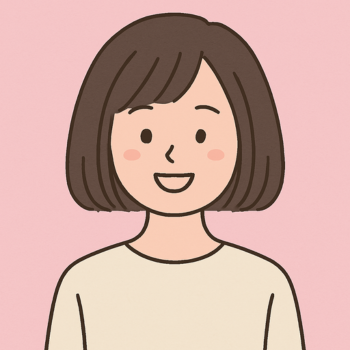
Sさん(◯◯大学・5年)
得意:循環器 苦手:公衆衛生
CBT試験日:4年次9月
CBTスコア:○○点
医学生道場の利用:スケジュール設計+苦手特訓
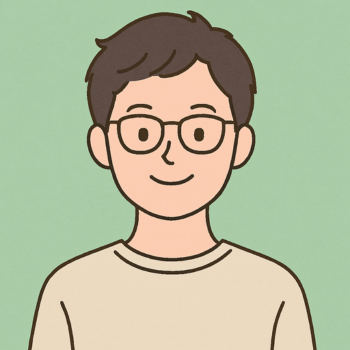
Wくん(△△大学・5年)
得意:消化器 苦手:神経
CBT試験日:4年次8月(再試10月)
CBTスコア:○○点(再試)
医学生道場の利用:再試に向けて集中講座
2人とも医学生道場の「医学部CBT対策コース」を利用していました!
では、2人がCBTに向けてどんな勉強をしていたか早速聞いていきましょう♩
勉強を始めたのはいつから?

|
おおしお お2人はいつからCBTの勉強を始めましたか? |
|
Sさん
3年生の期末試験が終わってから、少しずつ始めました! 最初は週に10時間を目安に、自習室に通う習慣をつけるところから始めました。 |
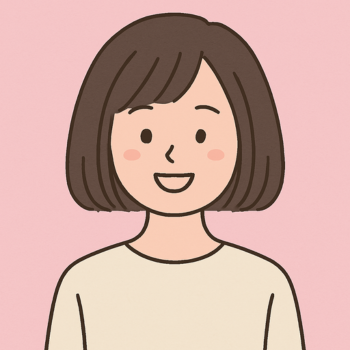
|
|
Wくん
正直、私は一度CBTに落ちてから本気になったタイプです…(笑) 再試験が決まってから、「やばい」と思って本格的に勉強を始めました。そこからは人生で一番勉強したと思います! |
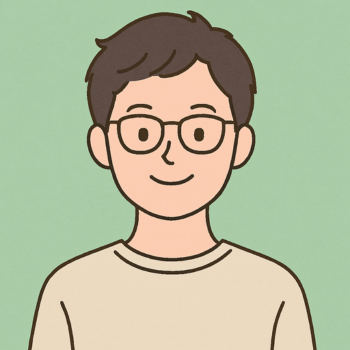
|
SさんはCBTに向けてコツコツと、Wくんは一度CBTに不合格になった後にガーっと取り組んだタイプということで、かなり対照的ですね。
CBTに向けた勉強を始める時期に決まりはありませんが、基本的にはコツコツと計画的に行うのが理想です。
先ほどもお伝えしましたが、CBTでは4年生までに学習した範囲が出題されるため、一朝一夕で対策するのはとっても困難です。
積み重ねによって確実に知識を習得していくことが重要になります❗
医学生道場の「医学部CBT対策コース」では、主にCBTを控えている3年生と4年生を対象としていますが、早い段階からCBT対策をしたいという1年生と2年生もご相談可能です。
実際に、勉強を先取りしたいという学生さんも多く在籍しています。
また、 CBTの本試験だけではなく、Wくんのようにこれから再試験を控えているという方も対象です。
再試験まで時間がないという場合には、実力をつける事よりも、まずは合格する事を重視して勉強する必要があります。
再試験に落ちてしまうと、留年の可能性がグッと上がってしまい大変です💦
早く対策をすれば、その分合格もしやすくなります。ぜひお早めにご相談ください!
さらに、医学生道場では各教室の自習室を利用することができるので、Sさんのように学習の習慣作りをしたい!という方にはもってこいの環境です🍃
また、全国8校舎での対面授業の他、オンライン授業も実施していますので、全国どこでも授業を受ける事が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
どうやって勉強してた?スケジュール&塾の使い方
勉強を始めるタイミングはそれぞれ違いましたが、次に気になるのは「医学生道場でどんな勉強をしたのか?」という点。2人がどのように道場を利用していたのか聞いてみました。

|
おおしお CBTに向けて、どのようなスケージュールで医学生道場で勉強していましたか? |
|
Sさん
私は医学生道場で1ヶ月ごとの計画を立ててもらっていました。 平日は18時以降に自習室で勉強、隔週の授業で疑問点を解消して、翌週の学習に活かすという流れで回していました。 |
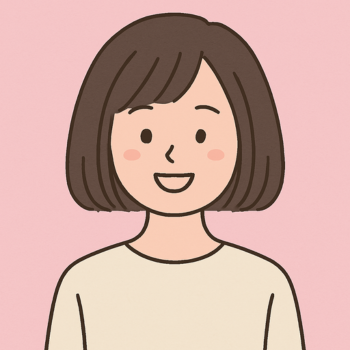
|
|
Wくん
計画的にやるのは苦手なので、週1回の授業を軸にして、「この1週間はこの範囲だけやる」と決めて勉強しました。 先生と一緒に作った「1週間スケジュール」がめちゃくちゃ役に立ちました! |
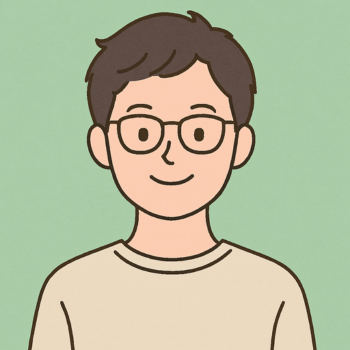
|
2人はそれぞれ違うスタイルで医学生道場を活用していましたが、共通していたのは「自分に合ったスケジュールを一緒に立てたこと」です。
Sさんは月単位の大まかな見通しを立てて、授業は隔週。対してWくんは週ごとの計画で、毎週の授業をペースメーカーとして活用していました。
CBTでは大きく分けて3分野(基礎医学、臨床医学、公衆衛生)から出題されますが、実は、その出題比率は分野ごとに大きく異なり、臨床医学の得点の占める割合がかなり大きいです。
そのため、基本的にCBT対策では以下のように勉強を進めていきますが、「どの問題をどのくらいの期間で解けるようにするか」ということを戦略的に考えていく必要があります。
基本のCBT勉強法❗
①インプット
すぐに問題に手をつけ始めるのも一つの方法ではありますが、まずは知識をインプット!
その診療科や、疾患について流れを掴むことが何よりも大切です。
CBT対策の講座を受講したり、今までの学校での学習を自分なりにノートにまとめたりしましょう!
②アウトプット
問題演習を実施しながら、自分の知識を確認していく作業です。
・まずは1周する
問題集を解いていくと、正解できた問題、間違えた問題、正解できたが自信がなかった問題が出てくると思います。
それぞれに〇、×、△などの印をつけながら答え合わせをしていきます。
間違えた問題や、よく分からなかった選択肢については、「ノートやテキストに戻って確認」し、知識を整理することが何よりも重要になってきます。
・復習として2週目以降に取り掛かる
時間がない場合は×や△の問題だけでもいいので、 『なぜ間違えたのか』『どんな知識が自分に足りていなかったか』『周辺知識で重要なものはあるか』などを意識しながら解き進めてください!
CBT対策ではこれらを繰り返して、完璧に問題が解けるようにしていきます。
そのためにも、勉強スケジュールを立てることはとても重要になってきます。
医学生道場では、多忙な医学生でも利用しやすいように固定時間の授業ではなく、予定に合わせて授業日程を決められるようになっています。
また、医師講師が予定や苦手科目を考慮しながら一緒に勉強スケジュールを考え、自信をもってCBTに臨めるよう全力でサポートします!🔥
使った教材と勉強法が知りたい!
では、そのスケジュールの中で使っていた教材は? 効率よく勉強するために何を選んでいたのか、具体的に聞いてみました。

|
おおしお 勉強で使ってよかった教材や、おすすめの勉強法はありますか? |
|
Sさん
QBオンラインを周回していました。 補助として「病気がみえる」を使用し、わからない部分を補っていました。 |
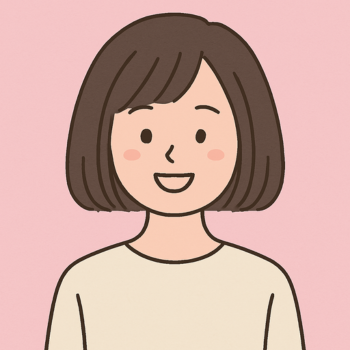
|
|
Wくん
とにかくQBを何周もしました。 でも、道場で「ただ解くだけじゃなく、どう考えて答えるか」が大事って教えてもらえて、取り組み方が変わりました。 |
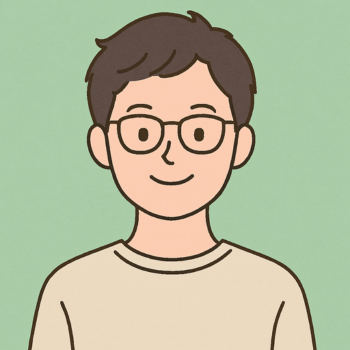
|
2人ともQB(クエスチョンバンク)を利用していたようです!
みなさんの中にも、QBを利用している!という方は多いのではないでしょうか?
QBにはCBTのプール問題(後述しています!)が多く収録されているので、CBT対策にはもってこいです。
取り組む際には「vol.2 臨床前編」 「vol.3 臨床後編」から先に解いていくこともポイントですよ💫
さらに、Wくんのいうように、医学生道場では「ただ解くだけじゃなく、どう考えて答えるか」を重視しています。
それはなぜか?
これまでCBT対策で悩む医学生をたくさん指導してきましたが、最終的にCBT対策で重要なのは「質」と「量」だからです。
「質」は分かりやすく言うと「効率」のことです。
ダラダラと勉強するのと、実際の臨床経験のある医師に分からない事をどんどん質問しながら勉強できるのでは、やはり質は大きく異なります。
そもそも、CBTの意義は臨床実習(ポリクリ)に移るための試験なので、臨床現場を意識した勉強を普段から行う事が出来ているかどうかは最も重要です。
つまり、臨床経験の豊富な現役の医師講師と一緒に学ぶ勉強法が最も効果的❗ということになります。
臨床医の視点からの解説を通じて、 「根本的な医学のの実力を身に着ける事」ができるので、結果として効率は上がっていきます。
そしてCBT対策では勉強の「量」も大切です。
つまり、どれだけCBT対策に勉強時間を確保できたか、何年分の過去問を解いたのかなども重要になってきます。
解いたら解いた分だけ理解が深まり、他の学生よりも一歩先に進む事が出来るので、まずは勉強スケジュールを作成し、自信をもって勉強を進める事の出来る環境を作りましょう。
とはいえ、医学部の授業に加え、部活やアルバイトなど、日々多忙な医学生は多いのではないでしょうか?
医学生道場では、受講生1人ひとりに合わせて、オーダーメイドの勉強スケジュールを作成しています📅
「何から勉強したらいいかわからない!」「計画を考えるのは苦手!」という方も、医師講師と予定や苦手分野を考慮しながら一緒に決めていきましょう✊
本番ってどんな感じ?CBT当日の感想
ここまでは、試験当日までの勉強について聞いてきました!次の質問では、実際に受けてみた感想を聞いていますので、ぜひ参考にしてくださいね👐

|
おおしお CBT当日の様子はどうでしたか? |
|
Sさん
緊張していましたが、プール問題で解いたことのある問題も多く焦らずに解くことができました。 |
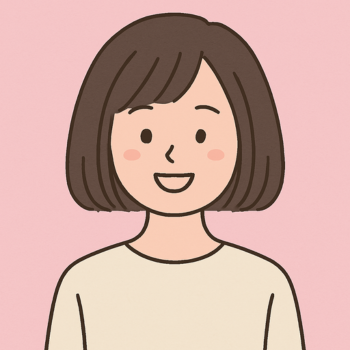
|
|
Wくん
PC操作は特に問題なし。ただ、時間配分がギリギリで焦りました…事前に本番形式の練習をもっとすればよかったと思いました。 |
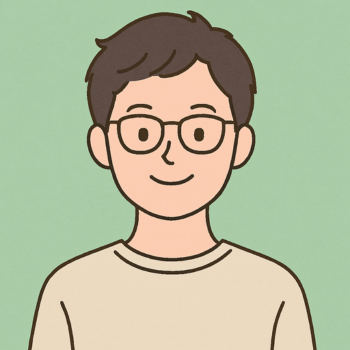
|
CBT試験本番は思わぬ緊張や焦りが出るもの。
Wくんのように「時間配分がギリギリだった」という声がある一方、Sさんのように「見たことのある問題が出た」と感じる人もいます。
これはCBTが“プール問題”と呼ばれる過去問から出題される特徴があるからです。
CBTでは、過去の出題から良問と判断された問題が「プール」としてストックされており、
そのなかから約240問が出題されます(全320問中)。
つまり、CBTの対策においては「とにかく過去問やプール問題を解いて慣れる」ことが最も効率がいい勉強法ということになります。
端的に言えば、CBTは1年生から4年生までのまとめ試験に当たるので、その試験範囲はとにかく膨大です。
そこでもし、CBT対策で過去問を使用しなければ、勉強する際に「理解するために調べる時間」も増えてしまい、時間がいくらあっても足りなくなってしまいます。
効率よくCBT対策をするためにも、過去問やプール問題を使った勉強法はとてもおすすめです💫
CBT対策で大切だと感じたことって?
勉強スタイルは正反対だった2人ですが、それぞれに合った方法で乗り越えてきたのが印象的でした。
これからCBTを受ける皆さんにとっても、自分に合った勉強法を見つけるヒントになるはずです!

|
おおしお CBT対策で一番大事だと思ったことは何ですか? |
|
Sさん
「勉強習慣を身につけること」が一番!すぐ結果が出なくても、地道にやれば必ず力になるって信じてました。 道場の確認テストで「解けた!」って感じられると、やる気も保てました。 |
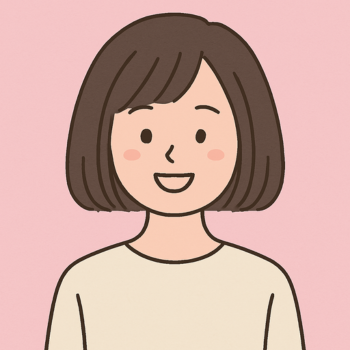
|
|
Wくん
僕は“追い込まれないとできないタイプ”なので(笑)、環境の力を借りるのが大事だと思いました。 あと、臨床現場の話を聞きながら学べたのがすごく楽しくて、「勉強=患者さんのため」って意識に変わったのが大きかったです。 |
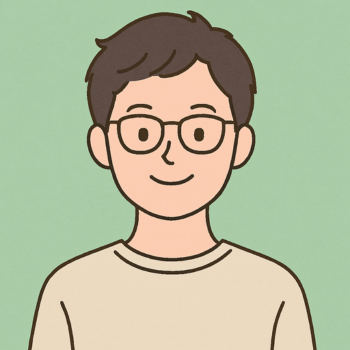
|
SさんとWさん、それぞれの取り組み方や考え方には違いがありましたが、共通していたのは「自分なりの方法を見つけて継続する」ことの大切さ。
ここで、2人の勉強スタイルを表にまとめてみました!自分に近いタイプを見つけるヒントになるかもしれません❗
まとめ:2人のCBT体験[比較表]
| 項目 | Sさん | Wくん |
|---|---|---|
| 勉強開始時期 | 3年生の終わり頃 | 再試験が決まってから本格スタート |
| 勉強スタイル | 勉強の習慣化 | 短期集中 |
| 道場の利用法 | 月ごとの学習計画+苦手対策授業 | 1週間ごとの計画+授業 |
| 使用教材 | QB、病気がみえる | QB |
| CBT当日 | プール問題で対策万全 | 時間配分⚠️ |
| 成功のポイント | 勉強の習慣化 | 環境の活用と勉強意識 |
CBT対策は一人で抱え込まず、時には環境や人の力を借りながら、自分なりのペースで進めていくことが合格への近道かもしれません。
「勉強法が合っているかわからない」「何をすればいいのか迷っている」という方は、ぜひ一度、医学生道場や周りの先輩に相談してみてくださいね。

|
おおしお これからCBTを受ける人へ一言おねがいします! |
|
Sさん
早めに自分の苦手や勉強スタイルを把握しておくのが大事です。 塾は「勉強の伴走者」って感じで、相談できるのが心強かったです。 |
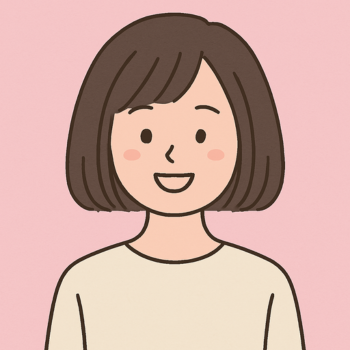
|
|
Wくん
落ちたからこそ気づけたこともあるけど、できれば一発合格してください(笑)! でも、失敗してもやり方を変えれば巻き返せるってことは、伝えたいです! |
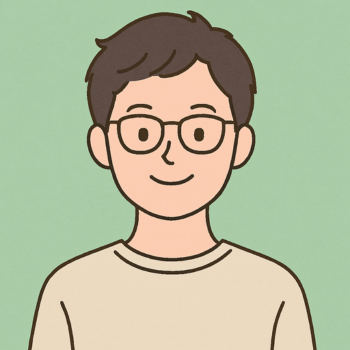
|
さいごに

最後までご覧いただき、ありがとうございました!
こちらのブログでは、2人の医学生へのインタビューを通して
・CBTの勉強法・対策法
・塾との向き合い方
・当日を振り返ってみての感想
を紹介してきました!
CBT合格は一朝一夕で果たせるものではないですが、頑張ればその分結果がついてきます!
この記事がみなさんのCBT勉強の一助になれば嬉しいです😊
医学生道場の各種SNSでは、医学生の皆様に向けて「お役立ち情報」を発信しています。
是非チェックしてみてください🙌
公式LINEでは、無料体験授業やキャンペーンなどのお得な通知や、医学生道場が独占入手した各医学部の試験情報、医師国家試験の最新情報をお届けいたします!
誰にも知られたくない悩みやご相談も、公式LINEから受け付けております。お気軽にご連絡ください!
電話やメールでのお問い合わせもお待ちしております。
試験が近いなど、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください📞
TEL:0422-26-7222
営業時間:13時~21時
定休日:水・木曜日