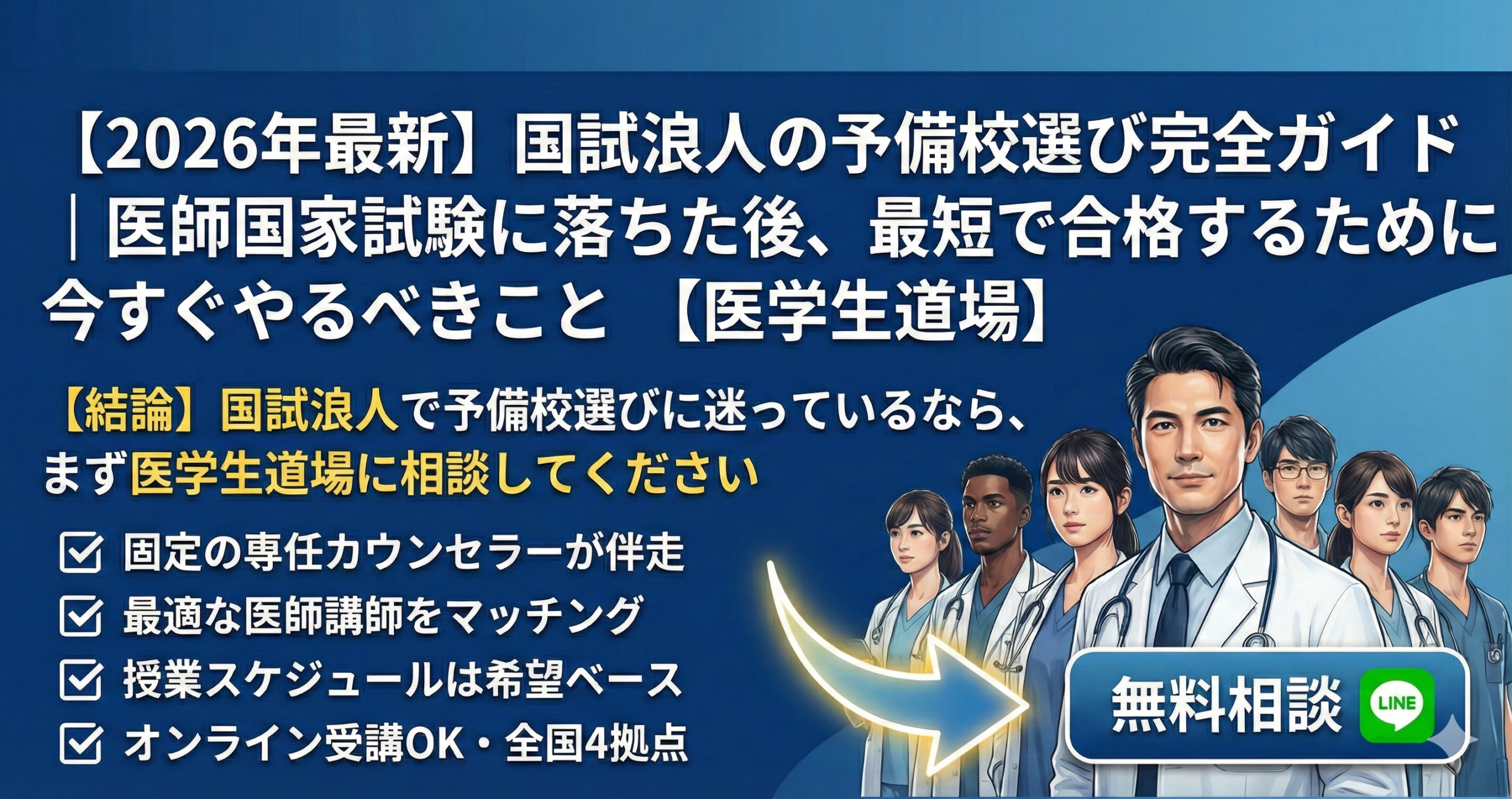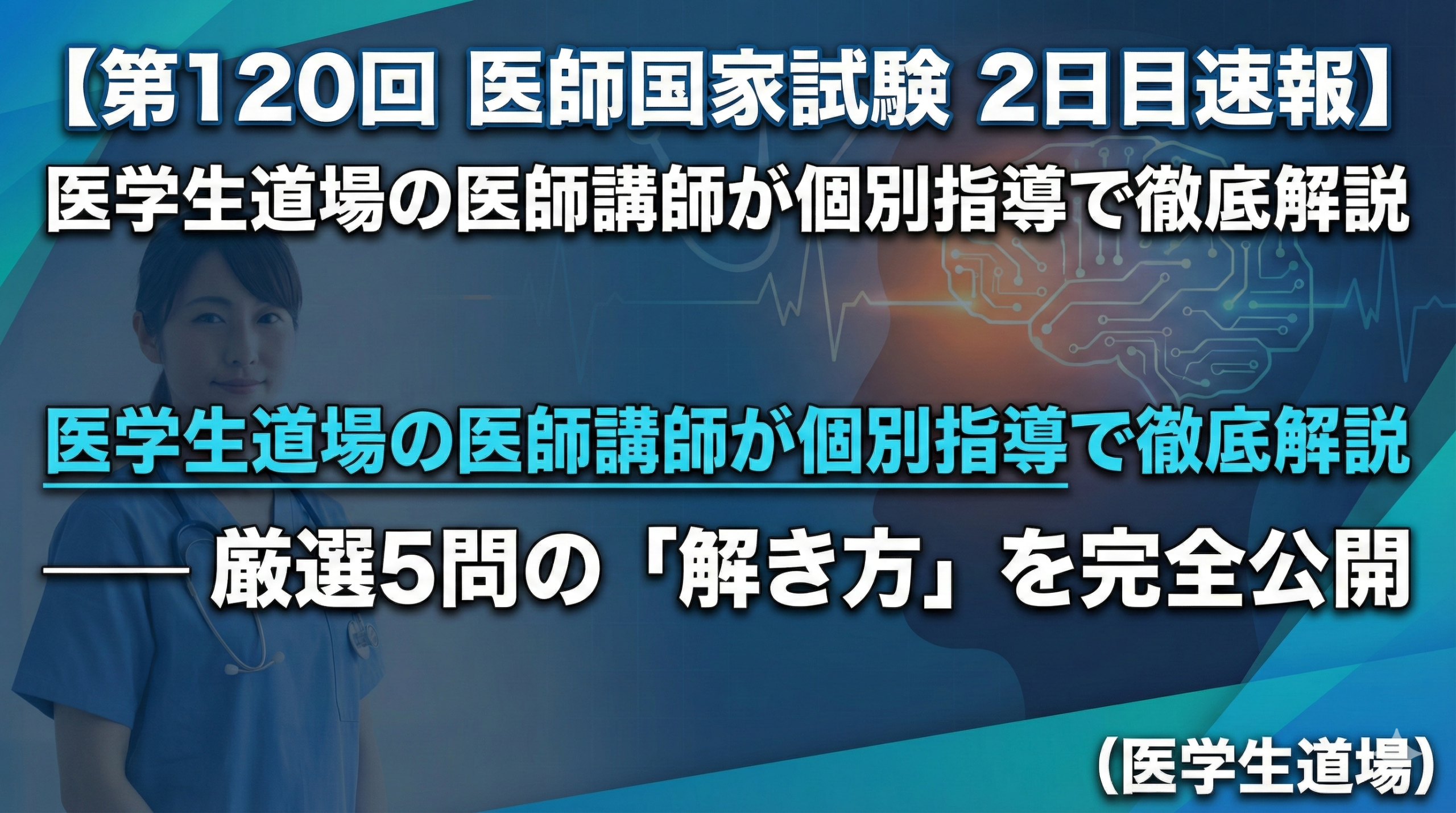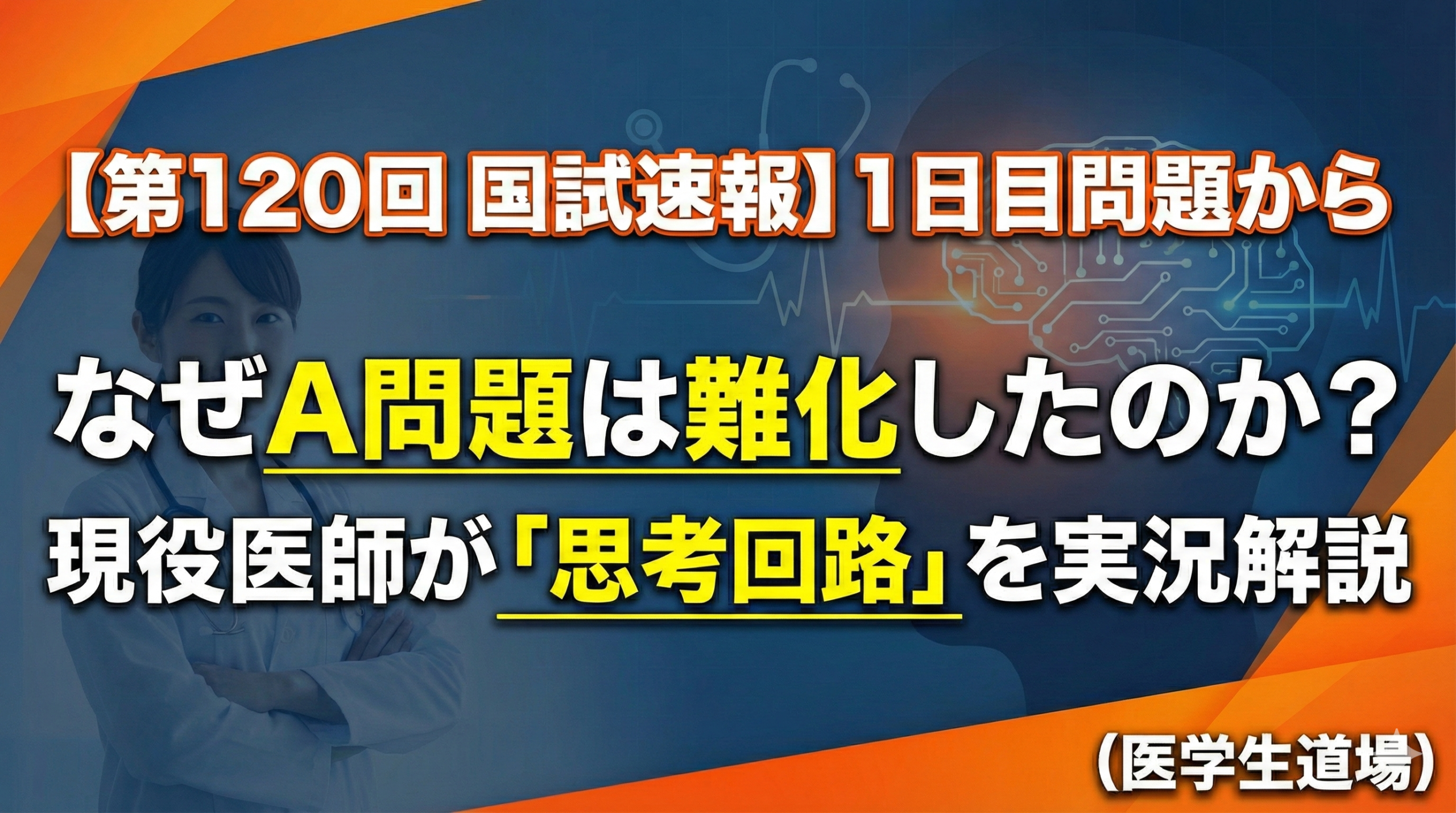目次
著者紹介・概要
🖊著者紹介
竹田美穂 (都内私立医学部医学科4年生)
3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次には大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。
留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!
留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!
【過去に著したブログ】
【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】
【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】
👉 医学部CBT直前の不安や質問もOK!24時間メッセージ受付中!
🖊今回の概要
・「こんなに勉強してるのに、なんで成績が上がらないの?」と悩んでいるあなたへ。
・合格者が実践していた「点数に直結する勉強法」とは?
・逆効果な勉強法、やってませんか?
はじめに
こんにちは、医学生道場の竹田美穂です。
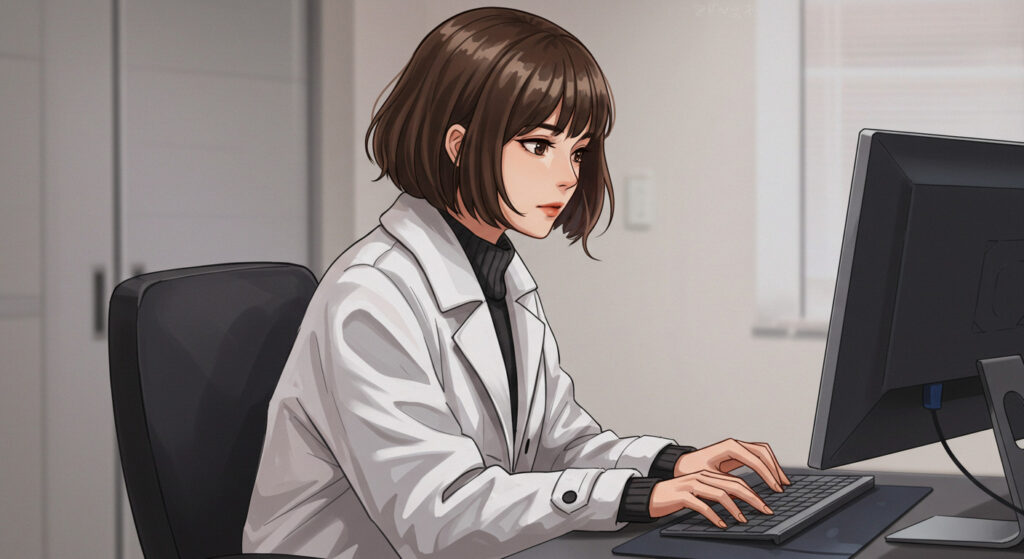
最近、周囲からこんな声をよく聞きます。
「今の自分では成績を上げられる気がしません……。」
「毎日勉強しているのに、力がついている実感がないです。」
「このまま進級できるのか、不安です……。」
私も、少し前まではまったく同じことで悩んでいました。
真面目に勉強しているのに点数が伸びない。
友達は部活や委員会で忙しいのに、なぜかスッと試験に合格していく。
そんな姿を見て、焦りや悔しさばかりが募りました。
それでも、「自分の何が悪いのか」が分からず、
とりあえず過去問解いてわからなかったところをノートにまとめてみたけれど、全然覚えられない。
本番では余計にわからなくなって、結局再試——そんな負のループにはまっていました。
このブログでは、「頑張ってるのに伸びない」と悩んでいるあなたに向けて、
最低限試験に受かるために必要な「成果が出る勉強法」と、
やりがちだけど逆効果な「やってはいけない勉強法」をご紹介します。
高得点を狙うのではなく、とにかく勉強と成績が比例するようになりたい方向けの記事です。
前に進もうとしている医学生同士、一緒にこの壁を乗り越えていきましょう。
勉強の効果が出るまで、どのくらい時間がかかるの?
まず大前提として、1回見ただけで理解したり覚えたりできる人は、ほとんどいません。
最近では進級試験も「過去問そのまま」の出題ではなくなっています。
その場で応用できるようにするには、知識を“使える形”で定着させることが大切です。
そのためには、過去問や問題集を繰り返し解く必要があります。
たとえば、医学部CBT対策や、医師国家試験対策としてよく使われるQB(クエスチョンバンク)。
これは何周もまわしてこそ効果が出る教材です。
ただし、最初から完璧を目指してはいけません。
1周目の目標は、「この問題なんとなく見たことある」くらいでOKです。
時間をかけすぎないことが大事。
何度も解く中で、
「これは○○だからAが正解だよね」と、
根拠を持って答えられるようになることがゴールです。
つまり、成績が上がるまでには、ある程度の時間と繰り返しが必要です。
逆に言えば、正しいやり方でコツコツ積み重ねれば、必ず伸びていきます。
焦らず、でも止まらず。
それが一番の近道です。

成績が伸びる勉強法とは?
ここからは、実際に多くの合格者がやっていた「成績が伸びる勉強法」をご紹介します。
① 過去問演習を中心に戦略的に進める

やるべきことは、とてもシンプルです。
- 過去問やQBを何周も解く
- 正解肢の意味をきちんと理解する
- 不正解の選択肢も「なぜ違うのか」を説明できるようにする
この3つを意識するだけで、得点力は大きく変わります。
特に大切なのは、「答えを見ずに、自分の力で正解できるか?」という視点です。
ただなんとなく正解を覚えるのではなく、
「なぜこの選択肢が正しくて、他はダメなのか?」
すべての選択肢に理由をつけられる状態を目指しましょう。
② 臨床問題は「診断名当てゲーム」だと思え!
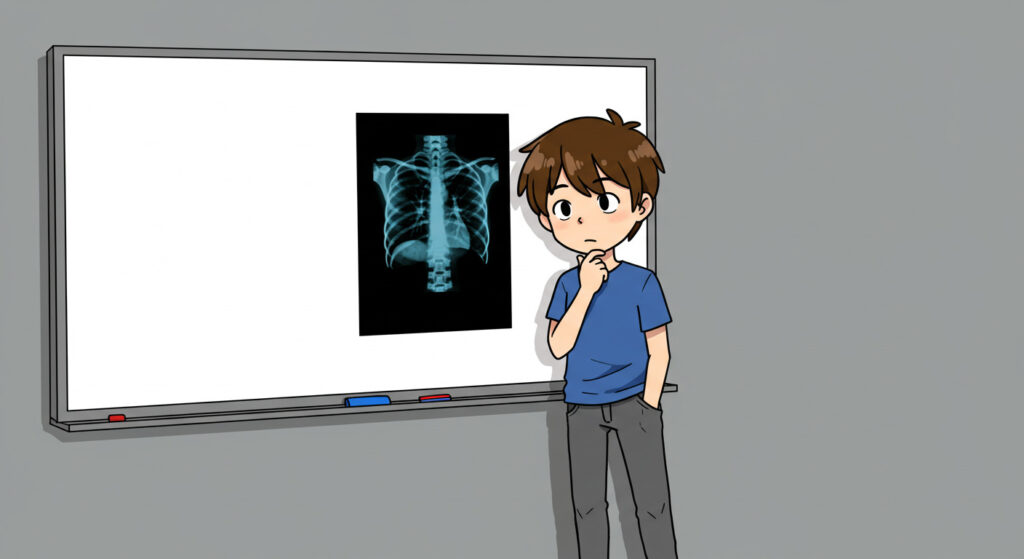
臨床問題って難しそうに見えますが、
要は「この症状・経過・検査値・画像なら、どんな病気?」という診断クイズです。
以下のステップで解くことで、定着が早くなります。
🩺 診断までの流れ
- 主訴・年齢・経過を読む
→ ここでまず、ざっくりと病気の候補を絞る - 検査値や画像をチェック
→ 鑑別をしぼり、診断を確定させる - 診断がついたら次に考えること:
→ 必要な検査は?(優先順位は?)
→ 治療は?(禁忌がある?)
この流れを毎回なぞっていくことで、
知識が「つながって」定着し、どんどん応用力がついてきます。
③ 暗記ポイントを早めに把握し、繰り返す

「覚えるのは最後でいいや」
と後回しにしていると、結局どれも覚えられないまま試験日が来てしまいます。
演習の段階で「これは覚えるべき!」と思った情報は、
すぐにAnkiなどの暗記カードにしておきましょう。
とくにAnkiのような間隔反復ツールを使うと、
「忘れかけた絶妙なタイミング」で問題が出てきます。
Ankiに頼らずとも、毎日見直しなどをすることで、定着率がグッと上がります。
暗記は“まとめて一気に”より、“少しずつ何度も”の方が確実に強いです。
忘れる前に、ちょっとだけ思い出す。
それを積み重ねていくのが、効率の良い記憶法です。
逆にやってはいけない勉強法とは?
今から紹介する勉強法は、正直言って「成績が伸びない典型パターン」です。
時間だけが過ぎていく割に、得点にはつながらない。
「やってるのに伸びない」と感じている人は、このどれかに当てはまっていないか確認してみてください。
① 答えだけを丸暗記する
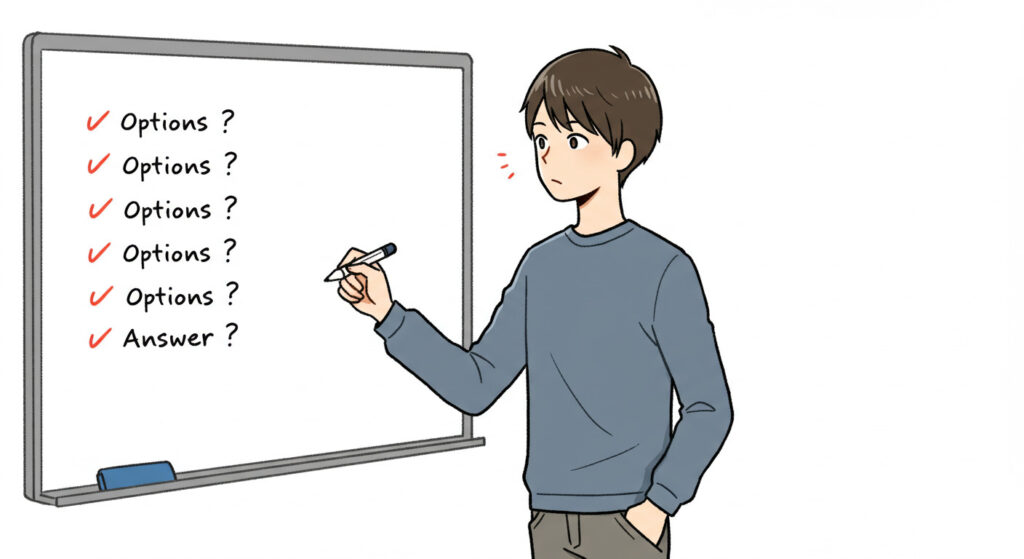
「この問題は確かaが正解だったな」
「この問題は確か一番下の選択肢が答えだったはず」
このような覚え方は、当たり前ですがなにも身についていません。
医学の知識は、理由や根拠とともに使えることが重要です。
ただ答えを記憶するだけでは、初見問題や応用問題に対応できません。
「なぜその選択肢が正しいのか」
「他の選択肢はなぜ誤っているのか」
までセットで理解することが大切です。
仮に何度も解いていて選択肢を覚えてしまったのなら、
どういう根拠を元にその回答にたどり着けるのかということを言えるかどうか確認する必要があります。
知識に根拠が伴ってはじめて、試験で使える“本物の力”になります。
② 1周目から全部調べる

初回からすべての問題を完璧に理解しようとすると、
膨大な時間がかかり、学習が前に進まなくなります。
1問に30分かけて調べ尽くすよりも、
まずは全体の流れをつかむために、ざっくりと10問を解く方が効率的です。
そもそも、1周目は「わからないことだらけ」で当然です。
完璧を求めて立ち止まるよりも、
まずは全体を1周し終えることを優先しましょう。
繰り返す中で、自然と知識は積み重なっていきます。
③ ノート作り・まとめ作業に時間をかける

丁寧にノートをまとめることに安心感を覚える方は多いと思います。
しかし、そのノート、本当に見返していますか?
確かあのページのあそこに書いたはず……とちゃんと思い出せますでしょうか。
色ペンを使って整えたり、マーカーを引いたりして満足してしまうと、
実際にはあまり活用されないまま終わることが多いのが現実です。
試験で問われるのは、
「きれいにまとめた知識」ではなく、
自分の手で演習を通じて使えるようになった知識です。
どうしてもまとめたい場合は、
Ankiなどを活用し、復習に直結する形に変えることもおすすめです。
Ankiは文章や画像をコピペできるので、ノート作りに時間をかけすぎるよりも、
その時間を演習や復習に使うほうが、合格への近道になります。
合格への最短ルートは「早く始めて、何度も繰り返す」

ここまでの内容を、もう一度整理しておきましょう。
- 勉強の成果が見えるまでには、ある程度の時間がかかります。
- しかし、正しい方法で、十分な量を、繰り返すことで、確実に力は伸びていきます。
- 演習の回数こそが、得点力の土台になります。
- CBTや国家試験では、模試などで定期的に実力を確認することも大切です。
そして何より、不安でいっぱいなときほど、手を動かすことがその不安を打ち消す一番の方法です。
「このままで大丈夫かな」と悩んでいる時間があるなら、まず10問だけ解いてみる。
それだけでも、前に進んでいる実感が得られるはずです。
私自身も、かつては同じように不安でいっぱいの時期がありました。
でも、過去問、QBを繰り返し解き、できることを1つずつ積み重ねた結果、少しずつ手応えを感じられるようになりました。
そして、ちゃんと前に進むことができました。
あなたも、必ず進級できます。
そのために、今やるべきことを一緒に整理してみませんか?
医学生道場では、あなたの現状に合わせて、最短ルートを一緒に設計します。
FAQ
①「1周目はわからないままでいい」と言われても不安です。
→ 「できない」が当たり前という前提を持つことが大事です。焦るとどうしても深堀して一問に時間をかけたくなったり、ノートにまとめたくなったりしてしまいます。しかし、まずは全体像を掴んでからのほうが効率よく理解を深めることができます。一度目を通しておくことで「この問題解いたことあるぞ」と自信を持つことができますし、同じ問題を何度も解くことで、「これは前に見たことある」から「こうだから正解はこれ」と根拠づけて答えられる状態になります。初見問題にも応用が効くようになるので、繰り返し演習をできるようにまずは1周目はさらっと行うことをこころがけましょう。
②勉強時間は取っているのに成績が上がりません。何から見直すべきですか?
→ まず「演習量が足りているか」「ただの丸暗記になっていないか」「ノート作りに偏っていないか」など、時間の使い方を具体的に見直すのが第一歩です。特にまとめノートに関しては、 完全に否定するわけではありませんが、「まとめること」が目的になってしまうと時間を浪費してしまいます。もし作るなら、復習に使える形(Ankiや1問1答形式)に変換して活用することをおすすめします。
③何から手をつけていいかわからず、勉強が止まってしまいます。どうすればいいですか?
→まずは「問題を10問だけ解いてみる」ことをおすすめします。完璧を目指さなくてOKです。手を動かせば、だんだん調子が付いてきますし、少しでもやることで不安も少し和らぎます。それでも悩んでしまう場合は、医学生道場に相談して、一緒に作戦を立てましょう。
📌 医学生道場 公式LINEから無料相談受付中!
「何から始めたらいいか分からない」「勉強法を見直したい」という方は、ぜひLINEでご相談ください!