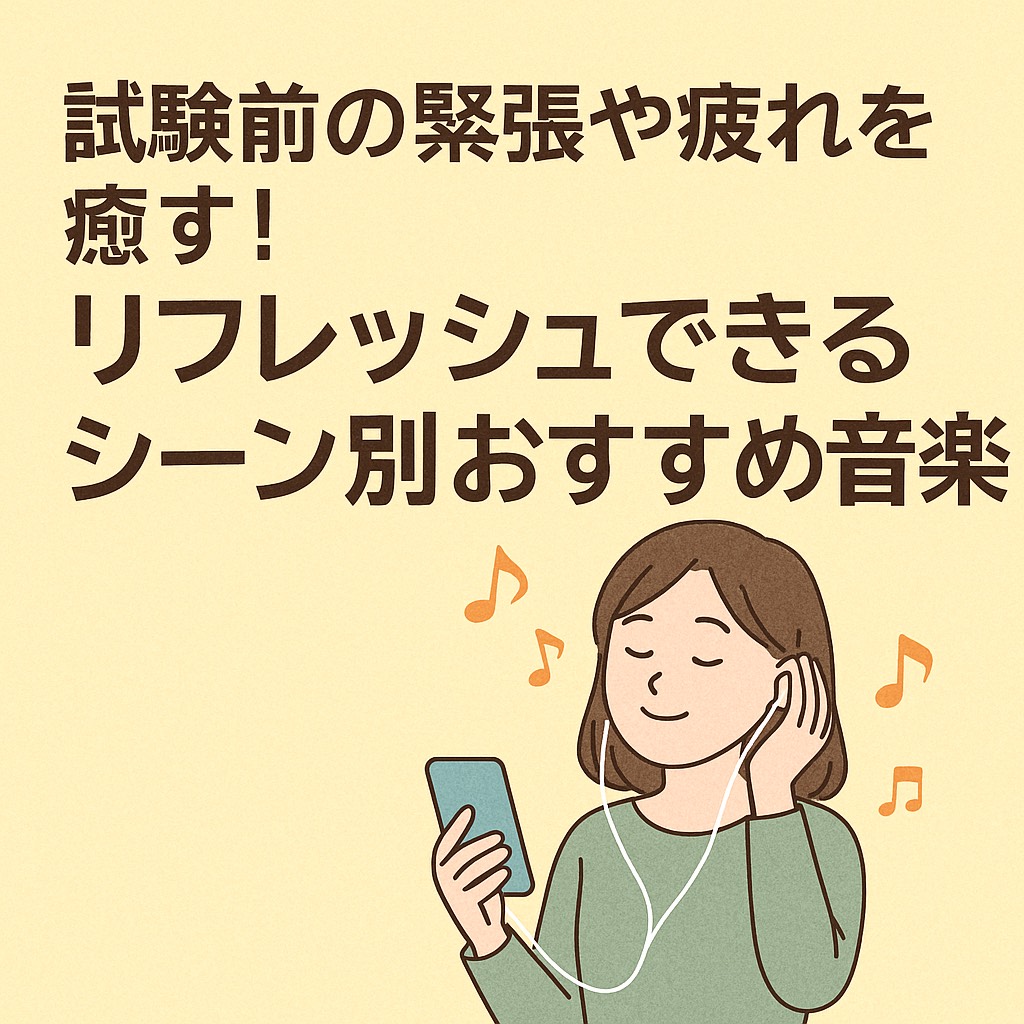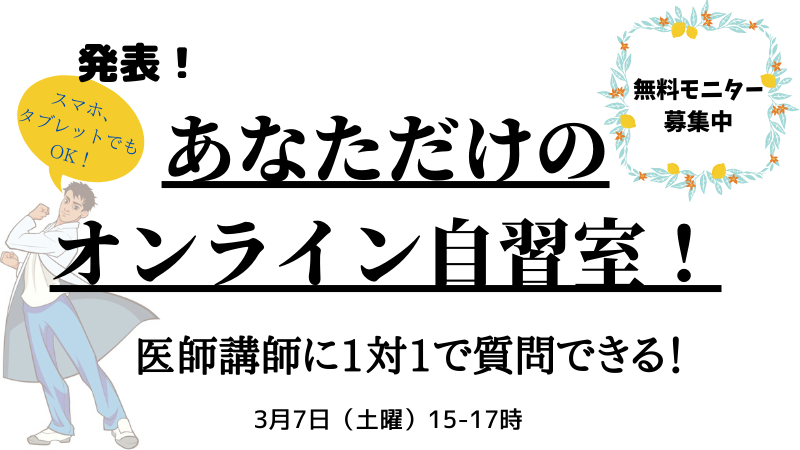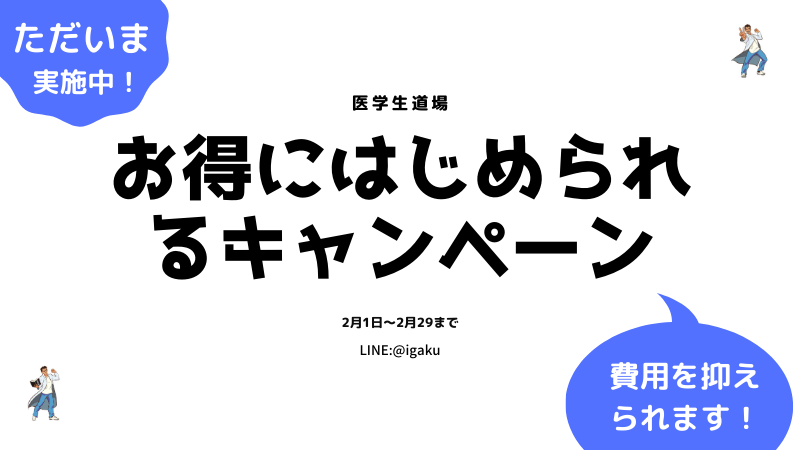目次
はじめに
こんにちは、医学生道場の竹田美穂です🌸
みなさん、解剖学は得意ですか?
医学生のつまずきポイントNo.1とも言われる解剖学。解剖学って、なんであんなに難しいんでしょうか。
筋肉、神経、血管、骨、臓器、リンパ…
1つ1つの細かい部位にそれぞれ見慣れないカタカナや漢字の名称がついていて、混乱してしまいませんか?
例えば、肺や心臓だけでも…
iPhoneの絵文字、よくみると結構細かく再現されてて、私が2年生の時興味本位で名称を書き込んでみた画像です笑
これが解剖の試験では身体全身の部位分問われますから、量がとんでもなく膨大であることがよくわかりますよね。映像記憶能力のない一般の平凡な医学生がこれを半期ですべて覚えきるのは、なかなか至難の業だと思います。
さて、今回は解剖が苦手だったり、どう勉強したらいいかわからない医学生に向けて、
医学生道場ではどんなふうに解剖学を教えているのか?を、実際の指導法をもとにご紹介します。
ぜひ参考にしていただければ幸いです(^▽^)/
🖊 著者紹介
竹田美穂 (都内私立医学部医学科4年生)
3浪を経て医学部入学、1年次に留年を経験。2年次に心電図検定3級合格。3年次には大学祭実行委員長や所属部活の主将としての経験もあり、医学の勉強と課外活動を両立。
留年・浪人経験者だからこそわかる、医学の勉強のつまずきポイントを紹介。単なる暗記に頼らない、理解を深める勉強法を模索し発信中。「やる気が出ないときでも勉強を進めるコツ」を実体験からアドバイス。医学部生活を充実させるためのヒントや、課外活動との両立術も共有しています!
留年のこわさ、勉強の挫折、精神的なリカバリーの方法などを身をもって経験しています。実体験に基づき、「医学の勉強がしんどい…」と思っている人に寄り添った、役立つ情報を発信していきます!
【過去に著したブログ】
【失敗談】孤独な医学生のデメリットとリスク【私が留年した理由】【医学生道場】
【失敗談】「一人で判断してしまう」医学生がやりがちな勉強法【私が留年した理由】【医学生道場】
文章だけで理解は無理。見る・描く・説明するが基本!図を活用した徹底理解
まず、前提として解剖は“言葉”だけでは限界がある!
道場ではとにかく図で理解することを大切にしています。
「この血管、どこ通ってるの?」
「この神経、どの筋肉と関係あるんだっけ?」
どこに何があって、どのようにつながっているのか。こういった身体の接続がきちんとわかっていないと、試験で少し過去問と文言の違う聞き方をされたときに答えられなくなってしまいます。
ここの知識があやふやな学生には、医学生道場では専属の医師講師がネッター解剖学の資料やネットの画像を用いたり、イラストを描いて解説しています。
![ネッター解剖学アトラス[電子書籍付]原書第7版](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/L/9784524230082.jpg)
医学生道場では、学生が分からないところをそのままにせず、医師講師が正しい知識をもとにその場ですぐに解消できます。
しかし、見て解説を聞くと、その場では分かった気になってしまうものです。覚えた、と思っても後で問題を解いてみると『アレ?』と思うこともしばしば。
そこで、医師講師は学生に対し、ただ「見る」だけじゃなくて、学生さんに自分で解剖イラストを描いてもらうこともあります。
やっぱり実際に自分で描いてみることで、あやふやだったところも明確になります。さらに、もちろんそのイラストが正しいかどうか、現役の医師講師がその場でしっかりと確認してフィードバックをおこなってくれるため、誤った知識のまま覚えてしまうということもありません。
加えて、医学生道場では授業終わりに先生から口頭試問を行っており、覚えたイメージを言語化できるか確認します。
こうすることで、構造の理解だけでなくワードの暗記や瞬発力も磨かれていきます。
まとめると、医学生道場では
・血管や神経の走行をイラストや画像から覚える
・友達に見せられるくらい整ったイラストを描けるようになる
・覚えたことを“自分の言葉”で説明する
といった、見る・描く・説明するの3ステップで定着率アップを目指しています。
解剖をイメージで覚えられるようになれば、文字で覚えるよりも早く、忘れづらく定着させることができますよ👀✨
「全部覚えようとしない」が合格のコツ。覚えるべきところにメリハリを!
先述の通り、解剖学は量がかなり多いです。当然、全部完璧に覚えるのは到底無理なので、試験合格のためには「取捨選択」が命になります。
だけど、初めての解剖の試験で、一人だと何から手をつければいいか分からなくて、
気がついたら全体をぼんやりしか覚えてない……なんてこともあるでしょう。
医学生道場では、効率の良い学習のためポイントを絞って学習することを大事にしています。
医師講師は多くの先生が医師国家試験を乗り越えた若手の医師ばかりなので、直近のCBTや医師国家試験に出題されがちな内容の傾向や、普段の臨床で大切な部分をしっかりと理解しています。したがって、試験に出題されやすいポイントもしっかりと分かっています。さらに、大学のレジュメで先生の強調した部分や過去問をもとに、大学それぞれの「出るとこ重点」で効率的に対策をおこないます。
✔︎ 先生が講義で強調してたところ
✔︎ 臨床でよく使う知識
✔︎ 過去問で頻出の部位
医学生道場では、上記のように極力コスパよく学習が出来るよう、出るとこ重点で指導していきます。
医学生道場では無料で24時間相談を受け付けています。医学生道場の指導方法に興味が湧いた方は、ぜひ下記公式LINEからお気軽にご相談ください!
「筋肉・骨・神経をバラバラで覚えない」有機的な学習法
解剖は、一つ一つの要素をバラバラに覚えるのではなく、
「この筋肉、何神経で動くの?」
「この動作、どの関節と関係ある?」
「この神経、どの血管と並走してる?」
とつながりを意識して覚えるのが解剖の学習方法です。
長期的な理解のためには、筋肉・神経・血管・骨をバラバラに覚えるのではなくて、 有機的に、ひとつのユニットとして覚えるのがコツ。
たとえば「肘を曲げる」って動きだけでも、
・どの筋肉?
・支配神経は?
・血流はどこから?
・損傷したらどうなる?
というような形で、1本の線につなげていくことで、試験本番で思い出す引き出しが増えていきます。
医学生道場では、現役の医師が、実際の臨床現場での出来事や症例を元に、解剖学の知識を動きや症状に結びつけて学ぶスタイルで学習するから、記憶に定着しやすいです。
臨床現場の出来事や症例から学ぶことで、解剖の学習を「症状」や「神経診察」と関連づけて解説していくため、実践的な知識の使い方を学ぶことができます。病態をもとに「どの神経がやられているか」をイメージで逆算することができるようになります。
「この神経がやられると、どういう症状が出るんだろう?」
「この部位が腫れるって、どういう状態?」
こういった疑問にも、資料を使いながら、現役医師講師が 臨床と絡めながら解剖を解説していきます。
ただの図じゃなくて、「症状がイメージできる」ようになると、
記憶に残るし、実習やOSCEでも役立ちます。
口頭試問とフィードバックで理解を深める
医学生道場では、絶対に単なる暗記では終わらせません。解説後には「自分の言葉で説明」してもらったり、指導者からの声掛けや理解確認で安心感とやる気UPに繋げていきます。自分で説明してみるのは、初めは緊張するかもしれませんが、“分かったつもり”を撃退するためにはとても大事なポイントです。
理解があいまいなところも、その場で先生がフォローしてくれます。
さらに、「ここまでできてるね!あと少しだね!」といったような前向きな声掛けもしてくれるので、メンタル的にも心強いです。
「過去問データベース×ノートで反復」戦略的な復習法
過去問キーワードごとに情報を整理した“解剖ノート”を活用する場合もあります。繰り返し見直すことで、知識がよりいっそい定着していきます。
またさらに、過去問に出たことのある問題は確実に解けるよう、過去問は5年分は仕上げることが多いです。
そのノートを見ながら、またさらに過去問を繰り返し解き、 解けなかった問題だけピックアップして復習することで、 “出るとこ”だけに時間を集中させることができます。
医学生道場では、先生とスケジュールを立てた上で、無理のない程度に定期的に先生からのサポートやフィードバックを行った上で自分や大学に合ったやり方で進めていきます。
さいごに 解剖はイメージ勝負!道場で一緒に乗り越えよう!
解剖学って、覚えることが多くて、しかもなかなかイメージしづらい分野ですから、つまずきやすいです。
でも、医学生道場では
✔︎ 図で理解
✔︎ 描いて覚える
✔︎ 臨床と結びつける
✔︎ 口頭試問
✔︎ 声掛け&フィードバックでやる気キープ
というフルサポート体制です!
またこれに縛られることなく、生徒さんの要望があればそれも聞いた上で、先生が生徒さんに合ったスケジューリングや学習方法を考えていきます。
解剖は苦手な人ほど、学び方で変わる科目です。
医学生道場では、あなたのレベルや悩みに合わせて、一緒にサポートをしていきます!
あなたも医学生道場で、解剖を得意科目にしてみませんか?
不安な方や興味がある方は、ぜひ公式LINEからお気軽にご相談ください!